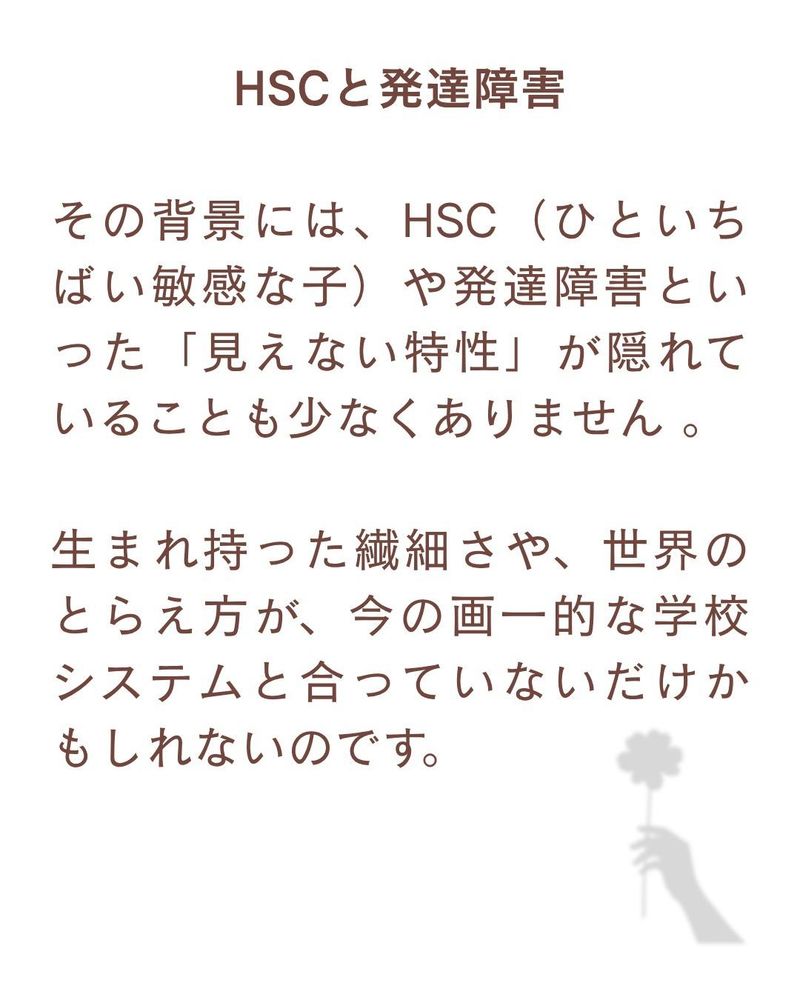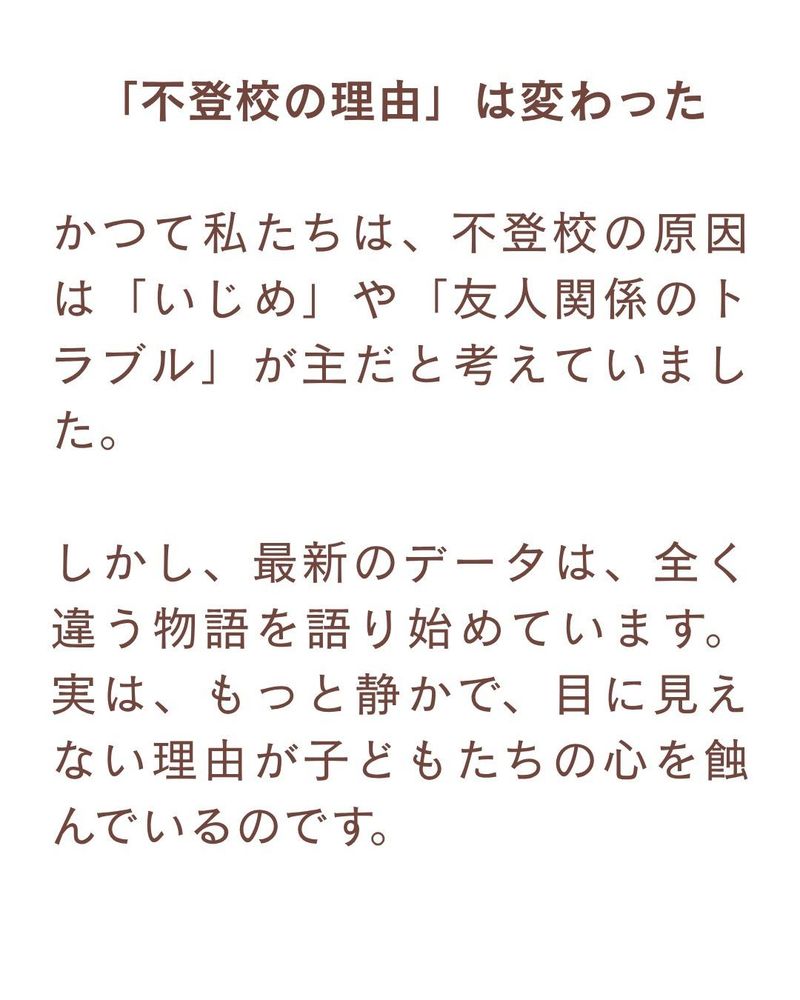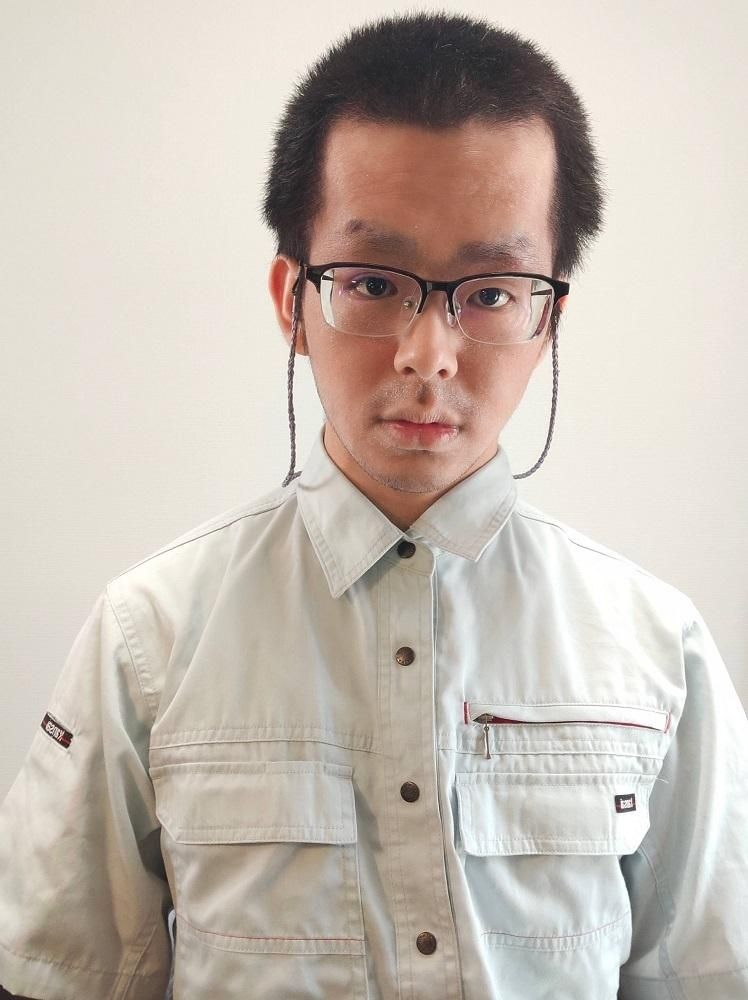コーチング🌻不登校児の悩みに寄り添う
@tashicoach.bsky.social
33 followers
77 following
50 posts
ひまわりコーチング|自身も子育てに悩んだ経験を持つ、メンタルサポーター|お子さんの将来が不安なママ・パパへ、「心の安定」と「具体的な関わり方」のヒントを発信します。
親子支援歴20年×メンタルサポーター
親の心を整え、お子さんの見方を変える実践型サポート
🎁 10の実践ツール+5日間で親子関係が整う無料チャレンジ
📩 LINEから今すぐ無料受け取り
公式ライン
https://lin.ee/NKkcCNv
Posts
Media
Videos
Starter Packs