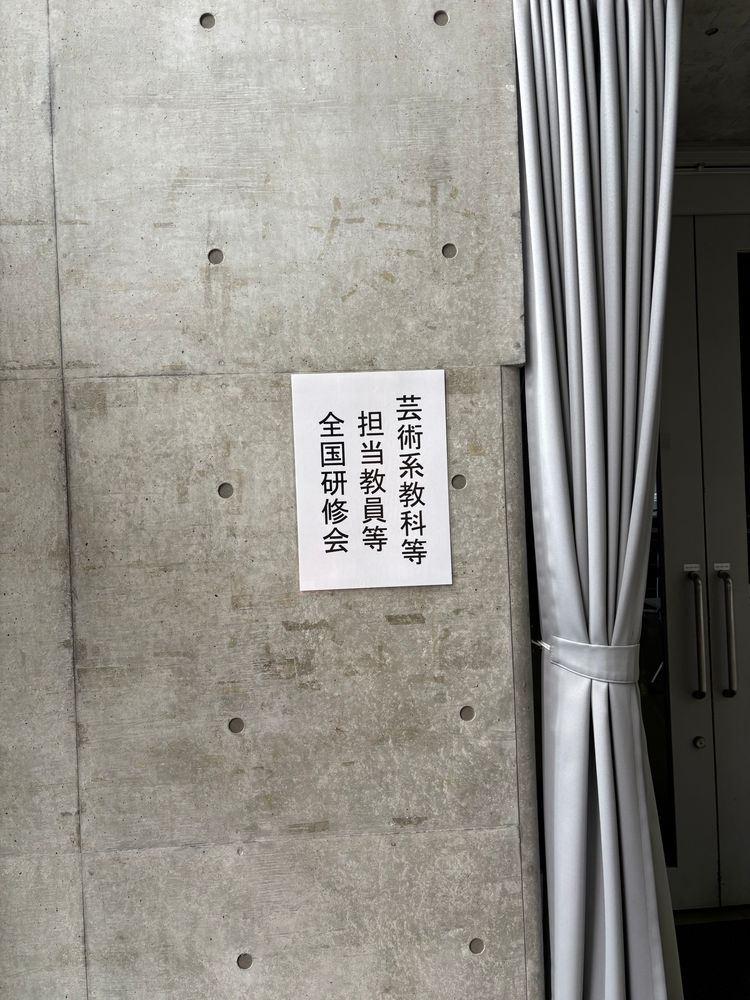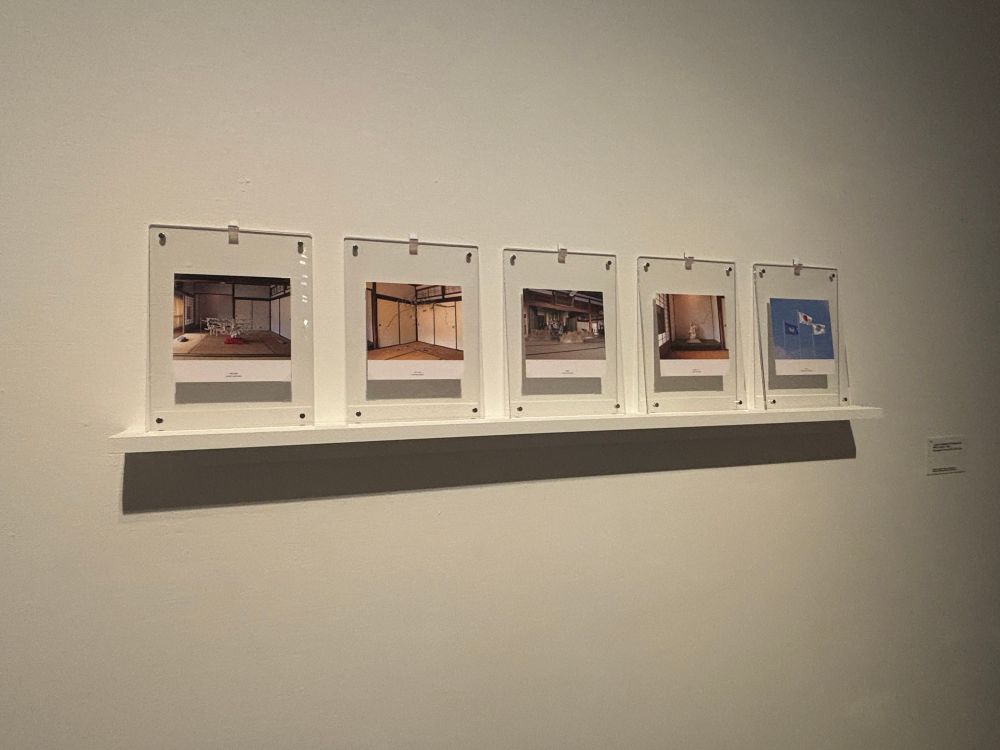末永史尚 / Fuminao SUENAGA
@kachifu.bsky.social
70 followers
71 following
390 posts
美術家、東京在住
http://www.fuminaosuenaga.com
Posts
Media
Videos
Starter Packs