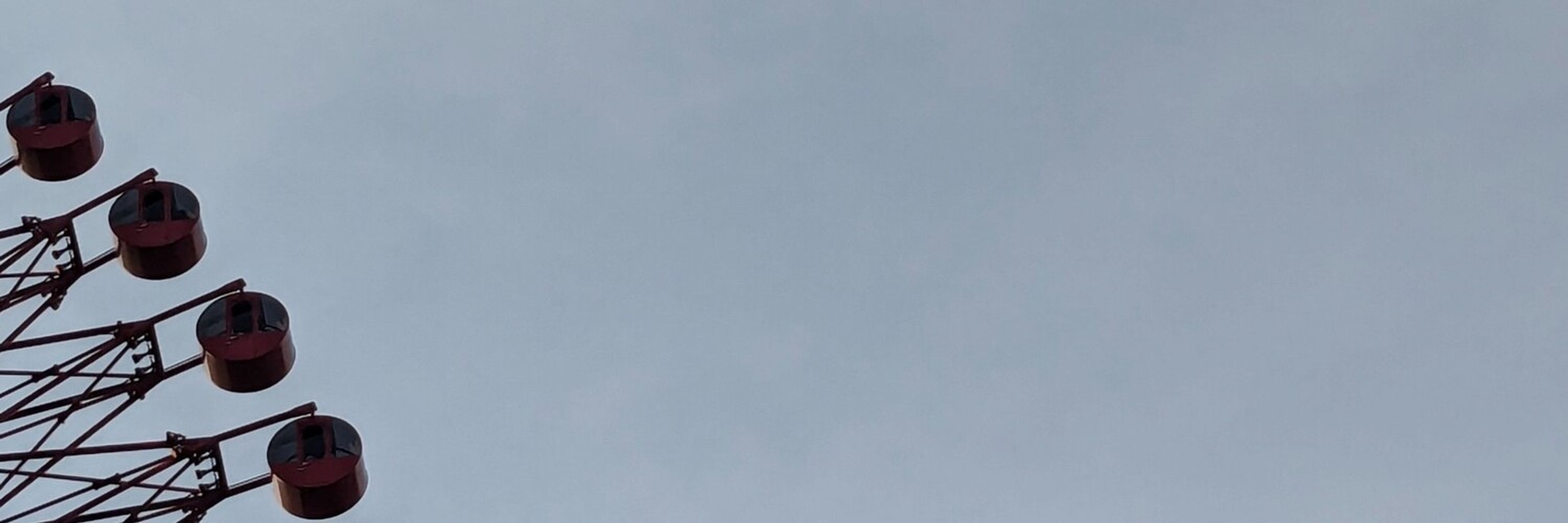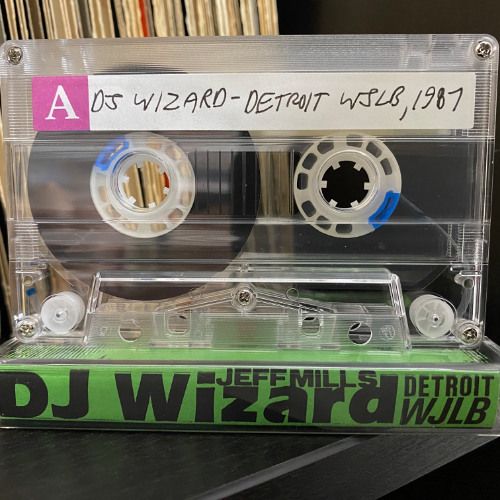kiq / キク
@kiq.fedibird.com.ap.brid.gy
160 followers
0 following
29K posts
Osaka city 大阪市在住の男性。はてなブックマーク連携とShare to Mastodonで雑多に投稿。BlueskyとはBridgy […]
🌉 bridged from https://fedibird.com/@kiq on the fediverse by https://fed.brid.gy/
Posts
Media
Videos
Starter Packs