サウンドスケープの第一人者バーニー・クラウスによる本書は、自然界に響く音を「野生のオーケストラ」として捉え、人間の音楽の起源をそこに見出す壮大な試み。彼は40年以上にわたり世界各地の自然音を録音し、動物たちが生態系の中で互いの音域を分け合って鳴く「音の秩序=バイオフォニー」を発見。森林破壊や都市化によってその調和が失われつつある現実を警告する。音は生物の進化と密接に結びついた情報体系であり、人間の音楽もまた自然界の響きの延長線上にあることを示す一冊。
amzn.to/4qG3mJ7
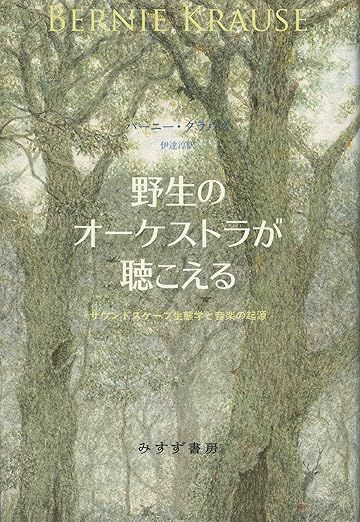
サウンドスケープの第一人者バーニー・クラウスによる本書は、自然界に響く音を「野生のオーケストラ」として捉え、人間の音楽の起源をそこに見出す壮大な試み。彼は40年以上にわたり世界各地の自然音を録音し、動物たちが生態系の中で互いの音域を分け合って鳴く「音の秩序=バイオフォニー」を発見。森林破壊や都市化によってその調和が失われつつある現実を警告する。音は生物の進化と密接に結びついた情報体系であり、人間の音楽もまた自然界の響きの延長線上にあることを示す一冊。
amzn.to/4qG3mJ7
何が言いたいかというと、「日本列島全体」に敷衍できる事実なんて、そんなに多くないのよ。クマの市街地出没は全国で起きているけど、その原因は複合的で、ある地域に当てはまることが、別の地域では全く当てはまらなかったりする。岩手県内ですらそう。
マスコミ的には、全国の現象をまとめて扱いたいだろうけど、それをやると細かいところで不正確な(ウソの)記述が増えるということに注意が必要。
何が言いたいかというと、「日本列島全体」に敷衍できる事実なんて、そんなに多くないのよ。クマの市街地出没は全国で起きているけど、その原因は複合的で、ある地域に当てはまることが、別の地域では全く当てはまらなかったりする。岩手県内ですらそう。
マスコミ的には、全国の現象をまとめて扱いたいだろうけど、それをやると細かいところで不正確な(ウソの)記述が増えるということに注意が必要。

news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE44WU0weks4bHFkcXlzQVZ2bW9wUE1uOVhRMUxJRDJtYlRRS2tmRFBrM0hubUhfb0NIOUhKSzJweFptM0VSWnVZMEdsSEwtM2Zta1ZjazVOLWhhRXhWdF9Ha0ZUMEg2M21FLTAyODNKM3VBMHhZYTZKSENGd29SYjQ?oc=5
news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE44WU0weks4bHFkcXlzQVZ2bW9wUE1uOVhRMUxJRDJtYlRRS2tmRFBrM0hubUhfb0NIOUhKSzJweFptM0VSWnVZMEdsSEwtM2Zta1ZjazVOLWhhRXhWdF9Ha0ZUMEg2M21FLTAyODNKM3VBMHhZYTZKSENGd29SYjQ?oc=5
増田隆一『ヒトとヒグマ──狩猟からクマ送り儀礼まで』岩波新書
amzn.to/42lrWU3
生態系の頂点に立ち、近づきがたい野生動物ヒグマ。ヒトはいつどのような進化をたどってユーラシア大陸でヒグマと出会い、なぜ文化的に共存することになったのか? ヒグマの動物学的・生態学的な特徴から説き起こし、時代と地域を超えた進化上の展開を追い、クマ送り儀礼に見る人間と自然との豊饒な文化の意味にまで迫る。
増田隆一『ヒトとヒグマ──狩猟からクマ送り儀礼まで』岩波新書
amzn.to/42lrWU3
生態系の頂点に立ち、近づきがたい野生動物ヒグマ。ヒトはいつどのような進化をたどってユーラシア大陸でヒグマと出会い、なぜ文化的に共存することになったのか? ヒグマの動物学的・生態学的な特徴から説き起こし、時代と地域を超えた進化上の展開を追い、クマ送り儀礼に見る人間と自然との豊饒な文化の意味にまで迫る。
よしのぶさんはこの話をしたくてゆる生態学ラジオを始められたそうです‼️🦋
蝶、アホすぎる。ピンポン玉に求婚してる。#100
youtu.be/4TtHxJbxu9Y

よしのぶさんはこの話をしたくてゆる生態学ラジオを始められたそうです‼️🦋
蝶、アホすぎる。ピンポン玉に求婚してる。#100
youtu.be/4TtHxJbxu9Y
ただ、朝の一限目から「白鯨」の冒頭を原書で読まされる動物生態学の授業は辛かったです。あれは何だったんだろう…。
ただ、朝の一限目から「白鯨」の冒頭を原書で読まされる動物生態学の授業は辛かったです。あれは何だったんだろう…。
要点1: 動物は空間と社会環境を同時に航海し、空間的選択や仲間関係を含む意思決定が彼らの空間および社会的フェノタイプを構成する。
要点2: 空間-社会的インタフェースはスケール依存性があり、環境とフェノタイプの定義は焦点スケールに依存する。
要点1: 動物は空間と社会環境を同時に航海し、空間的選択や仲間関係を含む意思決定が彼らの空間および社会的フェノタイプを構成する。
要点2: 空間-社会的インタフェースはスケール依存性があり、環境とフェノタイプの定義は焦点スケールに依存する。
新・動物記シリーズ各巻も特価販売中です!
ぜひこの機会にお買い求めください!
新・動物記シリーズ各巻も特価販売中です!
ぜひこの機会にお買い求めください!
https://www.moezine.com/1908948/
動物が絶滅する原因はさまざまだ。地球の気候が変化したせいで、生き抜くことができなくなったケースもある。進化の過程でより優れた新種が誕生し、古くから存在する種が生態学的な地位から蹴落とされてしまう場合もある。 人間のせいで [...]

https://www.moezine.com/1908948/
動物が絶滅する原因はさまざまだ。地球の気候が変化したせいで、生き抜くことができなくなったケースもある。進化の過程でより優れた新種が誕生し、古くから存在する種が生態学的な地位から蹴落とされてしまう場合もある。 人間のせいで [...]
あと動物生態学の授業で、アリの調査法とかを学びましたねー😊
あと動物生態学の授業で、アリの調査法とかを学びましたねー😊
"ネコが野生の祖先からどう進化してイエネコになったのか,ネコは人間や他の動物とどうかかわっているか,ネコの将来はどうなるかをトカゲ研究で有名なロソス博士が興味深く考察.現代のあらゆる技術を駆使してネコの過去・現在・未来を探る"
ジョナサン・B・ロソス/ 的場知之 訳『ネコはどうしてニャアと鳴くの? すべてのネコ好きに贈る魅惑のモフモフ生物学』
www.kagakudojin.co.jp/book/b656568...
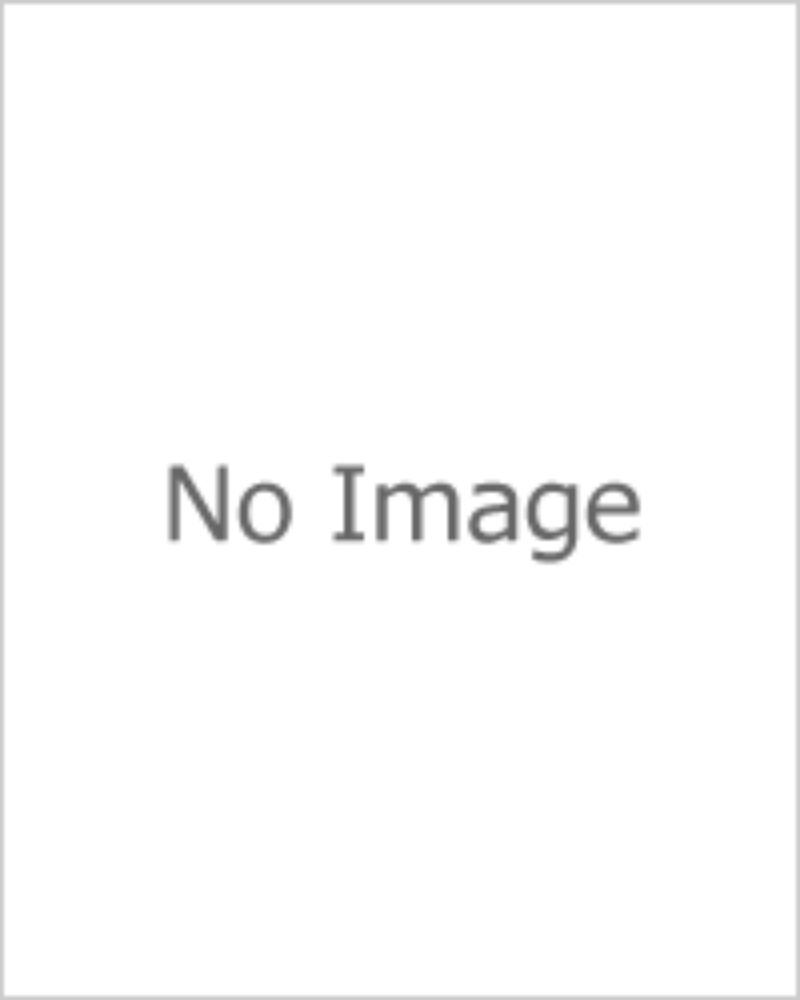
"ネコが野生の祖先からどう進化してイエネコになったのか,ネコは人間や他の動物とどうかかわっているか,ネコの将来はどうなるかをトカゲ研究で有名なロソス博士が興味深く考察.現代のあらゆる技術を駆使してネコの過去・現在・未来を探る"
ジョナサン・B・ロソス/ 的場知之 訳『ネコはどうしてニャアと鳴くの? すべてのネコ好きに贈る魅惑のモフモフ生物学』
www.kagakudojin.co.jp/book/b656568...
www.xknowledge.co.jp/book/9784767...
生き物の不思議な生態や行動を生態学者でイラストライターである著者が分かりやすく解説している。
イラストで動物生態を紹介する書籍の中でも、最新の研究論文の紹介を下敷きにその研究手法や研究の背景なども詳しく紹介しているところが特色。
人と協力してハチミツを得るノドグロミツオシエの研究や、続くコラムでの人と一緒に狩りをする(していた)動物の紹介が印象に残った。

www.xknowledge.co.jp/book/9784767...
生き物の不思議な生態や行動を生態学者でイラストライターである著者が分かりやすく解説している。
イラストで動物生態を紹介する書籍の中でも、最新の研究論文の紹介を下敷きにその研究手法や研究の背景なども詳しく紹介しているところが特色。
人と協力してハチミツを得るノドグロミツオシエの研究や、続くコラムでの人と一緒に狩りをする(していた)動物の紹介が印象に残った。
一般講演も含めてシカ過採食のことはデータとモデリングからいろいろよくわかってきた。僕らが関心のある個々の生き物に着目した生物相保全みたいなところはなかなか難しいので、モニタリングの目標設定は森林構造・植生や生態系機能になるんやけど、そこをもうちょい踏み込めたらいいんだろうなと思った。その点で芦生は先進的。あとは対策が遅れている地域で簡単にできること、今はまだ大丈夫そうな地域でやっておくべきこと、なども出てくるといいのかな?捕獲方法の新技術とか動物側の視点で新しいことがあるのか気になった。
一般講演も含めてシカ過採食のことはデータとモデリングからいろいろよくわかってきた。僕らが関心のある個々の生き物に着目した生物相保全みたいなところはなかなか難しいので、モニタリングの目標設定は森林構造・植生や生態系機能になるんやけど、そこをもうちょい踏み込めたらいいんだろうなと思った。その点で芦生は先進的。あとは対策が遅れている地域で簡単にできること、今はまだ大丈夫そうな地域でやっておくべきこと、なども出てくるといいのかな?捕獲方法の新技術とか動物側の視点で新しいことがあるのか気になった。
要点1: 生息地の破綻や種の喪失が、非人間動物の文化的多様性や複雑性、豊かさの損失につながる可能性がある。
要点2: 現在の知識に焦点を当て、動物文化に影響を及ぼす生態学的要因を明らかにし、環境変化が文化に及ぼす影響を検討。
要点1: 生息地の破綻や種の喪失が、非人間動物の文化的多様性や複雑性、豊かさの損失につながる可能性がある。
要点2: 現在の知識に焦点を当て、動物文化に影響を及ぼす生態学的要因を明らかにし、環境変化が文化に及ぼす影響を検討。
マストドンの絶滅、その影響は今も南米の原生林を脅かす
1982年に提唱された「新熱帯時代アナクロニズム仮説 neotropical anachronisms hypothesis」:大きくて甘く色鮮やかな果実をつける熱帯植物は、マストドンや巨大ナマケモノなどの大型動物による種子散布を前提に共進化した🥑🥭
その実態が分析によって明らかに
種子散布役を失った今、絶滅の危機は特にバクやサルなどにすら事欠くチリ中部で顕著
「生態学的関係が断ち切られた影響は、数千年経っても目に見える形で残るのだ」
www.uab.cat/web/newsroom...

マストドンの絶滅、その影響は今も南米の原生林を脅かす
1982年に提唱された「新熱帯時代アナクロニズム仮説 neotropical anachronisms hypothesis」:大きくて甘く色鮮やかな果実をつける熱帯植物は、マストドンや巨大ナマケモノなどの大型動物による種子散布を前提に共進化した🥑🥭
その実態が分析によって明らかに
種子散布役を失った今、絶滅の危機は特にバクやサルなどにすら事欠くチリ中部で顕著
「生態学的関係が断ち切られた影響は、数千年経っても目に見える形で残るのだ」
www.uab.cat/web/newsroom...
この10年間,夜間の無駄な照明が動物と植物,そして世界を結びつけている生態学的関係を大きく混乱させていることが明らかになった。
別冊日経サイエンス268【猛暑・感染症・野生動物 変わる世界とどう向き合うか】
www.nikkei-science.com/sci_book/bes...

この10年間,夜間の無駄な照明が動物と植物,そして世界を結びつけている生態学的関係を大きく混乱させていることが明らかになった。
別冊日経サイエンス268【猛暑・感染症・野生動物 変わる世界とどう向き合うか】
www.nikkei-science.com/sci_book/bes...
・野生の哺乳類の量は人間や家畜に比べてはるかに少ないのでもはや自然界に対して何も影響をもたらさない
・なので生態学と動物愛護、保全活動は無用である
・さらにこのことからも動物は不合理な存在であるため絶滅されたほうが楽である
・ただ観光資源となるような動物については半ば家畜・ペット化したうえで保護すべきであり、遺伝子の保護については動物園があるのでその動物が自然下にいる必要はない。
・
・野生の哺乳類の量は人間や家畜に比べてはるかに少ないのでもはや自然界に対して何も影響をもたらさない
・なので生態学と動物愛護、保全活動は無用である
・さらにこのことからも動物は不合理な存在であるため絶滅されたほうが楽である
・ただ観光資源となるような動物については半ば家畜・ペット化したうえで保護すべきであり、遺伝子の保護については動物園があるのでその動物が自然下にいる必要はない。
・
7月28日発売の『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』が、クマの生態や歴史をわかりやすく解説。驚きの雑学と命を守る対処法も!

「本当にこの竜の作画が良くて、東京竜学部協会が監修してるだけあってアニメ調にデフォルメされつつも動物学や生態学に基づいた描写がきちんとされていて竜愛好家の間では大注目のアニメなんだ。原作の漫画も大ヒット中。漫画も良い描写なんだがアニメ音にも拘っていて…」
(毎話片思い相手が興奮していてうるさい…)
「本当にこの竜の作画が良くて、東京竜学部協会が監修してるだけあってアニメ調にデフォルメされつつも動物学や生態学に基づいた描写がきちんとされていて竜愛好家の間では大注目のアニメなんだ。原作の漫画も大ヒット中。漫画も良い描写なんだがアニメ音にも拘っていて…」
(毎話片思い相手が興奮していてうるさい…)

