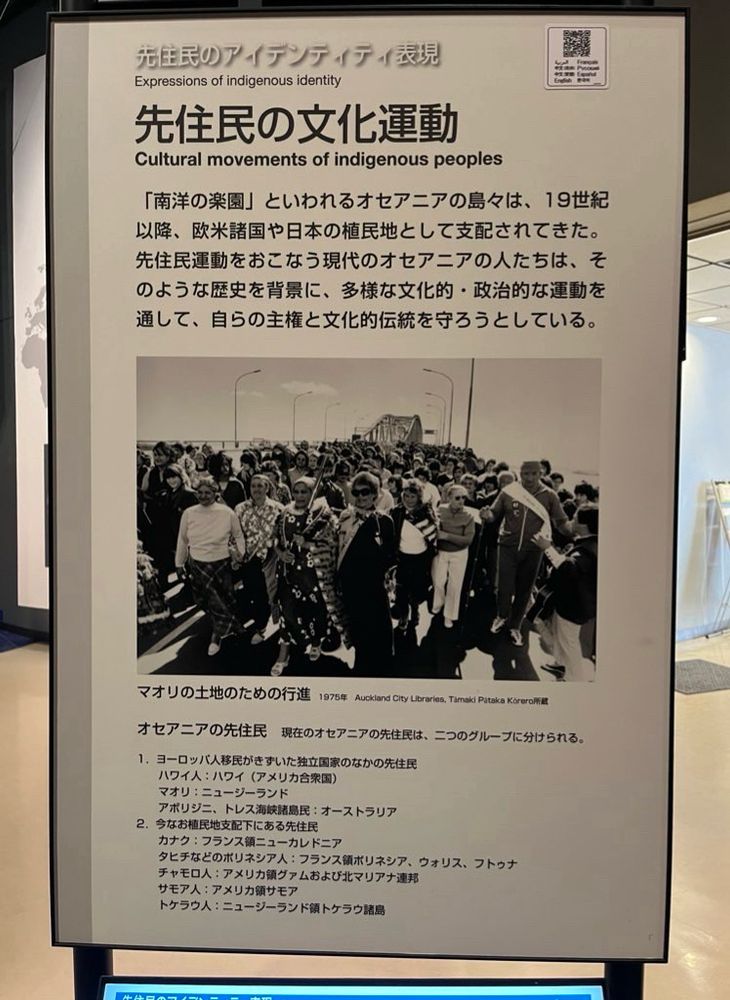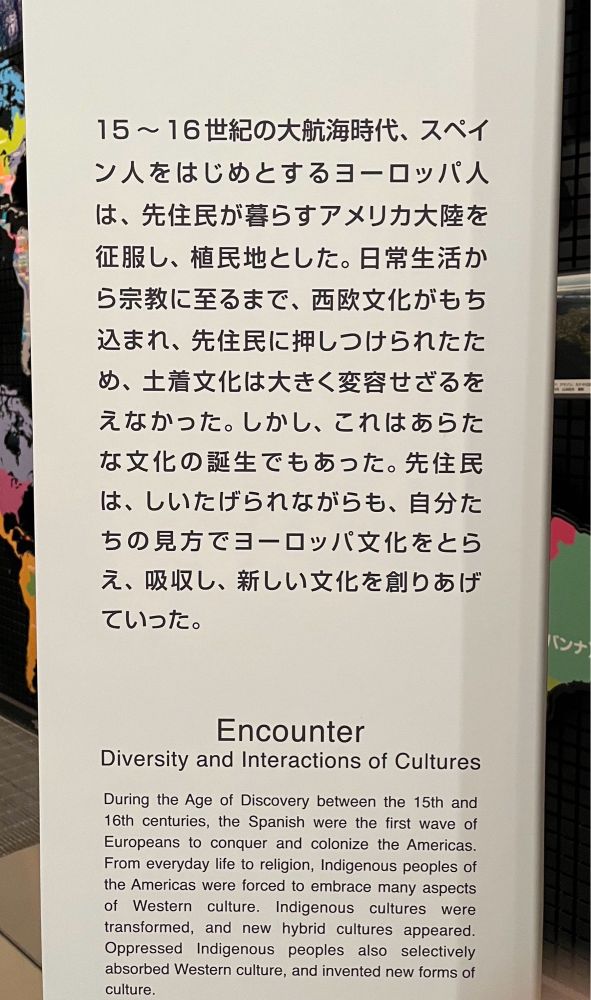垂れ流し3
#stand.fm
#gonzaの秒配信
#〇〇に合わせる必要は有るが✕✕に合わせる必要は無い
#土着の文化宗教
#異教徒の(¦3[▓▓]言
#人語を弄する寄生虫共

•古来日本では、土着信仰の神道と6世紀に伝来した仏教が対立することなく融合し、千年以上にわたり共存の文化が形成された。
•近代化の過程で一時的に分離が進んだが、近年、春日大社と興福寺が150年ぶりに共同祭礼を再開した事例を挙げ、「違いの中に共に生きる文化」の再生を紹介した。
•今日の国際社会には分断があるが、「地上には国境があっても、地下水には国境がない。人の心も同じだ」と述べ、宗教・文化の違いを超える知恵の重要性を訴えた。』
•古来日本では、土着信仰の神道と6世紀に伝来した仏教が対立することなく融合し、千年以上にわたり共存の文化が形成された。
•近代化の過程で一時的に分離が進んだが、近年、春日大社と興福寺が150年ぶりに共同祭礼を再開した事例を挙げ、「違いの中に共に生きる文化」の再生を紹介した。
•今日の国際社会には分断があるが、「地上には国境があっても、地下水には国境がない。人の心も同じだ」と述べ、宗教・文化の違いを超える知恵の重要性を訴えた。』
このお雑煮感が東アジア文化の魅力であって、別にゲームやらアニメやら歌謡曲やらがどこ製でも気にせず楽しくやろうぜっていうのがわれわれ東アジア人の伝統である。宗教性があんまり強くないところはヨーロッパと違う。
令和はアジアの時代を寿ぐにはけっこういい元号と言えるかもしれない。
このお雑煮感が東アジア文化の魅力であって、別にゲームやらアニメやら歌謡曲やらがどこ製でも気にせず楽しくやろうぜっていうのがわれわれ東アジア人の伝統である。宗教性があんまり強くないところはヨーロッパと違う。
令和はアジアの時代を寿ぐにはけっこういい元号と言えるかもしれない。
本当は安易に使うのやめて欲しいかな 文化盗用とか思わんけど
どれだけトキシックなものか知って欲しい
本当は安易に使うのやめて欲しいかな 文化盗用とか思わんけど
どれだけトキシックなものか知って欲しい
大乗仏教より敷居が高い(ような気がする)密教もまた,「みんなの」密教だった.土着の宗教と一体化する「神仏習合」もみんなを救うためのもの.
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1288...

大乗仏教より敷居が高い(ような気がする)密教もまた,「みんなの」密教だった.土着の宗教と一体化する「神仏習合」もみんなを救うためのもの.
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1288...
土着信仰の怪異。独自の宗教文化が根付く集落に巣食う怪異で、価値観が狂っている料理人。自らが持つ力の自覚がない。何でも作れるが得意なのは中華料理。
土着信仰の怪異。独自の宗教文化が根付く集落に巣食う怪異で、価値観が狂っている料理人。自らが持つ力の自覚がない。何でも作れるが得意なのは中華料理。
ってまた風花雪月を流し見しながら思うのである
ってまた風花雪月を流し見しながら思うのである
警部個人宛の匿名の捜索願を受け取り、その警部がスコットランドの島へ捜索に向かうストーリー。
警部は土着の文化風習を嫌悪し、行方不明とされる少女ローワン・モリソンを躍起になって捜索する。
土着の文化風習に対して「部外者」な警官という立場は植民地主義における統治者側の態度そのままってことかな?・・・たぶん。
したしみのない異質なものに対する「恐怖」でもって排除しようと行動するのはほどほどに〜とあらためて思う。
「かわいいカラフルなお花と白い衣で怪しげな宗教」みたいなイメージはこの映画からなんですかね?
boxd.it/97pHJN

警部個人宛の匿名の捜索願を受け取り、その警部がスコットランドの島へ捜索に向かうストーリー。
警部は土着の文化風習を嫌悪し、行方不明とされる少女ローワン・モリソンを躍起になって捜索する。
土着の文化風習に対して「部外者」な警官という立場は植民地主義における統治者側の態度そのままってことかな?・・・たぶん。
したしみのない異質なものに対する「恐怖」でもって排除しようと行動するのはほどほどに〜とあらためて思う。
「かわいいカラフルなお花と白い衣で怪しげな宗教」みたいなイメージはこの映画からなんですかね?
boxd.it/97pHJN
1.遊牧生活をした高句麗の文化影響を受けて新羅の帯の飾りがつける可能性
2.宗教的な意味で飾りをつけた可能性
全部あると思う
1.遊牧生活をした高句麗の文化影響を受けて新羅の帯の飾りがつける可能性
2.宗教的な意味で飾りをつけた可能性
全部あると思う
中世ヨーロッパでは宗教の影響もあり、生活文化を記録した多くの書物にはハロウィーンに関する記載というのがほとんどありません。
本来、その地域に根付いていた土着信仰から宗教ベースにすり変えられた祝祭が多くある中、このハロウィーンに関してはほぼ昔の形を残したまま、伝統行事として今も伝わり続けている地域が少なくありません。古の人々の思いと伝統を守る意識は、それだけ強かったのでしょう。


中世ヨーロッパでは宗教の影響もあり、生活文化を記録した多くの書物にはハロウィーンに関する記載というのがほとんどありません。
本来、その地域に根付いていた土着信仰から宗教ベースにすり変えられた祝祭が多くある中、このハロウィーンに関してはほぼ昔の形を残したまま、伝統行事として今も伝わり続けている地域が少なくありません。古の人々の思いと伝統を守る意識は、それだけ強かったのでしょう。
知っての通り、日本の宗教景色の基本形には、立派な樹や水源、かっこいい岩がある場所などに鳥居がある
長い歴史からみると鳥居は新興宗教なのよ、言い換えれば土着信仰を滅ぼした征服の証といえるね
ぬるい言い方では改宗かな
まつろわぬ民、と称される居なくされた少数民族が居たことは前回の授業でやったな
多文化だったはずなのに、鳥居一色に全国染まってる方が考えれば不自然だとは思わないか?」
キーンコーンカーンコーン
「今日はここまで」
僕は教室を見渡す
半数が寝ていた
僕もつまらない授業の1ページだと思っていた、この時までは
続
知っての通り、日本の宗教景色の基本形には、立派な樹や水源、かっこいい岩がある場所などに鳥居がある
長い歴史からみると鳥居は新興宗教なのよ、言い換えれば土着信仰を滅ぼした征服の証といえるね
ぬるい言い方では改宗かな
まつろわぬ民、と称される居なくされた少数民族が居たことは前回の授業でやったな
多文化だったはずなのに、鳥居一色に全国染まってる方が考えれば不自然だとは思わないか?」
キーンコーンカーンコーン
「今日はここまで」
僕は教室を見渡す
半数が寝ていた
僕もつまらない授業の1ページだと思っていた、この時までは
続
確かにそうですね。
一神教だとどうしても他宗教を排斥する動きになってしまいますし、土着の信仰を名残をとどめて吸収されるのが落とし所となってしまうんでしょうね。
西さんのロシアや中東欧の文化紹介、毎回興味深いことばかりです。また次も楽しみにしております!
確かにそうですね。
一神教だとどうしても他宗教を排斥する動きになってしまいますし、土着の信仰を名残をとどめて吸収されるのが落とし所となってしまうんでしょうね。
西さんのロシアや中東欧の文化紹介、毎回興味深いことばかりです。また次も楽しみにしております!
cinemandrake.com/the-medium
モキュメンタリーにすることで、アジア圏の宗教文化がオリエンタリズムとして消費されがちなことへの皮肉になってるとか、土着の文化の家父長制や女性差別を見つめ直すとか、やっぱそこ露骨に描いてるよね?!という納得があって…

cinemandrake.com/the-medium
モキュメンタリーにすることで、アジア圏の宗教文化がオリエンタリズムとして消費されがちなことへの皮肉になってるとか、土着の文化の家父長制や女性差別を見つめ直すとか、やっぱそこ露骨に描いてるよね?!という納得があって…