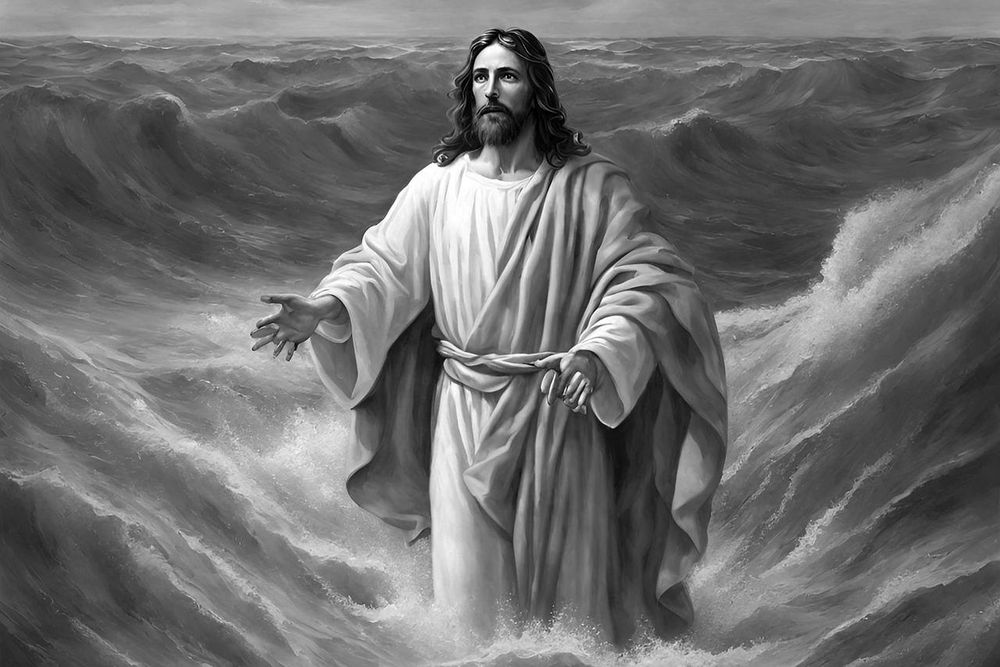大阪の銭湯が市民情報拠点に進化!『ふろマド』で地域貢献を推進
大阪の銭湯がデジタルサイネージ「ふろマド」を活用し、府政・市政情報を提供。地域貢献を目指します。
osaka.publishing.3rd-in.co.jp
November 12, 2025 at 3:17 AM
大阪カジノ住民訴訟で揺れる夢洲-5
カジノ用地の土地改良工事費用788億円を税金で支払い、工事期間中の賃借料を無料にする大阪市。カジノは公共事業なのか?
#進化する自治
#夢洲カジノ
#市民と市政
#vision50
カジノ用地の土地改良工事費用788億円を税金で支払い、工事期間中の賃借料を無料にする大阪市。カジノは公共事業なのか?
#進化する自治
#夢洲カジノ
#市民と市政
#vision50

カジノ事業のために工事費用や土地使用料を肩代わりする大阪市
大阪カジノ住民訴訟で揺れる夢洲-5 第3事件、第4事件までの経過 2022年7月29日に第1事件(夢洲IR差止・損害賠償事件)の住民訴訟が提起されて以降、裁判の進行とともにカジノ事業の誘致や契約も着々と進行していった。2023年4月3日 第2事件(格安賃料差止事件)の住民訴訟が提起された同年 4月14日 国土交通省は大阪府・市の区域整備計画を認定同年 9月5日 大阪府・市副首都推進本部が「実施協定」の骨子案を公表同年 9月8日 大阪府・市が国に対して実施協定の認可を申請同年 9月22日 国土交通大臣が実施協定締結を認可同年 9月28日 大阪府・市とSPC(カジノ事業者)が実施協定、借地権設定契約を締結 ●大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等実施協定書 ●事業用定期借地権設定契約公正証書 ●大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に関する協定 ●大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整備に係る土地使用等に関する協定) ●大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定書 ※9月29日同年 12月1日 大阪府・市とSPC(カジノ事業者)が土地改良工事用地の使用賃借契約を締結 ●大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用賃借契約書 ●引渡し範囲等に関する覚書同年 12月4日 カジノ用地で液状化対策工事開始2024年9月9日 第3事件(土地使用賃借・支払い請求等事件)と第4事件(土地改良費用・支出等差止・請求等事件)が提訴される同年 9月30日 大阪府・市とSPC(カジノ事業者)が土地引渡しに関する合意書を作成同年 10月1日 カジノ事業用対象土地492361019㎡のうち、464952.38㎡を大阪市からSPC(カジノ事業者)に引渡し※SPCはのちに大阪IR株式会社として登記された 土地改良工事用地の無償賃借は違法ではないか この2023年12月に行われた土地改良工事用地の使用賃借契約の締結と液晶化工事の開始が、新たな事件として住民訴訟が起こされることになった。これまでに紹介してきた第3事件、第4事件(大阪IR・カジノ土地改良事業差し止め訴訟)である。第3事件は、2023年12月4日から始まった液状化対策対策工事を行うに際し、大阪市が大阪IR株式会社(現大阪MGM株式会社)に対して土地利用の賃借代金を無償とした契約書が違法で無効であるとし、対象賃料の損害賠償を請求するもの。第3グループは、本訴訟を提起するにあたって、2つの違法性をその要旨の中で述べている。まず、カジノ用地の賃借契約とカジノ用地の土地改良事業に関する協定書において、土地改良事業費用を大阪市が負担することの違法性を指摘している。これば第1事件と同様の違法性を指摘し差し止めを求めるものである。下記に改めてその争点を見ていく。第1事件と同様の請求のため、第1事件への共同参加という形となっており、これが第4事件となる。事業用定期借地権設定契約・大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定書において、土地改良事業の費用負担することが、公営企業の独立採算制、平等原則を逸脱していることから下記の規定に違反している。 埋立地を賃貸・売却するにあたり、大阪市が改良費用を負担するのは異例。 年間2000万人の来場者があることを前提に、35年間の賃料収入による黒字を見込んでの最大788億の負担をすること。 土地改良事業が大阪市の公共工事とされながら大阪IR株式会社が発注する工事となっているため、一般競争入札優先主義やその他の地方自治法等の諸規定(地方自治法2条14項、地方自治法234条1項、地方自治法234条の2の1項、地方財政法4条1項)などの法の趣旨に反する契約となっている。 「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という(地方自治法2条14項)の規定に反している。 上限額のみ定めており、工事業者側に費用を抑える理由が無い。 大阪市は、大阪市が算定した上限額があるので適正さが担保されていると主張しているが、それで済むなら全ての入札が不要となり、競争原理も働かない。 第3事件は、上記の違法性を前提として、次のように主張している。大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約に関して、以下のような違反があるとしている。第4事件で示した、土地改良事業に関する協定書と一体となった使用貸借契約は、前者が違法無効であれば、これも無効である。平等原則(憲法14条1項)に違反・港湾土地を賃貸するにあたり、改良工事中の無償使用を認めるのは異例。・大阪市は、市の事業でも無償で使用させているので平等原則違反ではないと主張している、しかし対象はカジノ事業用地でカジノ事業は「市の事業」ではない。上記改良工事については入札によっていないことと矛盾する。地方自治法、大阪市財産条例違反・カジノ事業は「市の事業」なのか。・大阪市財産条例では公益事業のためなら無償貸付可能としている。 しかし民間によるIR・カジノ施設の建設は「公益事業」なのか。・大阪市は、賃料収入や経済波及効果が公益であると主張している。 しかし大阪市がインフラ等の建設の場合を例に挙げている従来の条例解釈と矛盾している。以上の理由から、第3事件、第4事件では、以下のように請求をしている。 大阪IRの事業のために必要な土地改良費用を負担するという合意の差止め 大阪IRの事業のために必要な土地改良費用の支払いの差止め 大阪IRに対する令和5年12月4日から1月あたり金2億1073万0589円の割合の損害賠償もしくは不当利得返還請求の履行請求 大阪市長もしくは大阪港湾局長に対する令和5年12月4日から1月あたり金2億1073万0589円の割合の損害賠償請求の履行請求 上記❸及び❹の怠る事実の違法確認 前の記事 続く ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
November 12, 2025 at 3:01 AM
一時のイベントで経済が上向くなどというのは幻想だというのは、50年前の大阪万博で証明済みだ。万博や夢洲開発に消えていった税金は、本来市民サービスなどに使われるはずだったのだが。
#進化する自治
#大阪関西万博
#市民と市政
#vision50
#進化する自治
#大阪関西万博
#市民と市政
#vision50

総額14兆1250億円の大阪・関西万博の収支と市民の税負担
「万博の運営収支、最大280億円の黒字見込み」に はしゃぐ関係者の見識を疑う 先週10月7日、日本国際博覧会協会が、大阪・関西万博の運営収支が230億~280億円の黒字になる見通しと発表した。この会見の中で当協会の十倉雅和会長が、余剰金の使い道について「科学技術の発展や命の大切さといったわれわれが訴えてきたことや皆さまに感動していただいたものを残すために使っていければ」と、あの大屋根リングの保存に使うような話をしたという。(「万博の運営収支、最大280億円の黒字見込み 大屋根リングなど再使用へ」電波新聞デジタル 2025.10.10)いやいや、そんなことを勝手に決めてもらっても困るし、まずまず大屋根リングを残すことは、そのツケを大阪市民に押し付けることに他ならない。まだ議会にも図られもしていない「大阪市の公園にする」などという話も寝耳に水の話ということを忘れてもらっては困る。大阪府知事がなんの権限を持って大阪市の公園にすると言ったのか、そのこと自体からして市民を置き去りにし馬鹿にした重大な越権行為だ。当の吉村府知事に至っては、当日のsnsで以下の通り 万博、赤字になったらどうする!と散々言われましたが、結果、「約230億円~280億円の黒字」となる見込みです。大きな黒字です。もし、赤字だったら、今頃、メディアから連日猛批判の日々だったでしょうね。万博の成功は赤字黒字だけではありません。未来社会の共有。やって良かったと思います。 などと喜び勇んだメッセージを出しているが、黒字と発表されているのは「運営費」だけであり、その運営費も実際には、警備費や途上国出展支援費など、本来運営費とされていた費用を国に負担してもらったり、会場で大発生したユスリカ対策費などは、予備費から出されている。本来運営費として負担しなければならなかった費用総額はおよそ1655憶円となってる。今回の発表では、運営費が50億円ほど減額できたとしており、支出が1110億円、収入が1389憶円(いずれも見込み)で約230億円~280億円の黒字が出る見通しとしている。しかし本来負担すべき運営費で見れば、210億円強の赤字ではないか。国に負担してもらったまま「黒字、黒字」と騒いでもらうのも困った話だ。その付け替え費用は、税負担。要は国民の税負担で黒字になったものを余剰金と称し、それをいずれ解散してしまう協会で勝手に使い道を決めてしまうというのも、あまりにも国民を馬鹿にした話ではないか。十倉雅和会長や石毛博行事務総長、副会長を務める吉村副知事など協会トップの見識は、その程度のものなのか。 運営費どころか、expo2025はロゴやキャラクターのカラー通りの大赤字 報道やsns上ではこの運営費と万博の収支について大賑わいだが、はっきり言って大阪・関西万博、大阪府・市民や国民にとっては大赤字の災いだ。内閣官房国際博覧会推進本部事務局が2025年2月に発表した「大阪・関西万博に関連する国の費用について(Ver.3)」と、同じく2月に大阪府市万博推進局が公開した「大阪・関西万博に要する府市の費用について」をもとに今回の万博ならびに関連事業費にかかった費用を改めて見直してみた。大きくは3つの分野に分かれているのだが、総額14兆1250億円にも上る。 大阪・関西万博に関連するインフラ整備費 約10.2兆円 会場建設等関連工事及び開催にむけた費用 2,976.8 億円 2025年大阪・関西万博アクションプラン 3兆6,273.2 億円 以下の表は国と開催自治体の負担と明細 インフラ整備を除いても 国の予算とは別に大阪府市で負担している額が、運営費とは別に1440億円もある。大阪府を除く他府県の国民は、国の負担分だけだが、大阪府民は、それにプラス大阪府府民税を、大阪市民は、それに加えて大阪市民税をそれぞれ負担することになっている。要は、その費用分を本来市民サービスなどに使われるべき税金が、万博や夢洲開発に消えていったのだ。開催前には万博の経済効果が喧伝されていたが、実際には、大阪府や市内で消費されたであろう支出が、万博に付け替えられただけという評価も目にした。一時のイベントで経済が上向くなどというのは幻想だというのは、50年前の大阪万博後の大阪経済の沈滞で証明されていたはずなのに、学習機能のついていない自治体トップによって、2度目の経済沈下を見ることになるかもしれない。都市にとって「にぎわい」は必要かもしれない。しかしこんな重い負担をすることが市民や地域のためになることではないことは確かだ。 ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
November 11, 2025 at 11:45 PM
思い込んだらどこまでも~堕ちたな「市民本位の民主市政をつくる会」
はじめに大間違いして拙速に公開質問しといて、相手が返事に困ると誠意がないだと?
このメンツで誰も同会の暴走を止められないんかいな。あきれるな。
元記事の怪しい醜聞に始まる怪騒動の誤爆。そら誰だって返事に困らぁな。
あべこべだ。誠意あるなら「うっかりにも踊らされて申し訳なかった」
「せめてものお詫びに全力で支える」と小川市長に謝罪せんかい。
真実はひとつだ。草葉の陰で角田儀一もお怒りだ。#負けるな小川あきら。
news.yahoo.co.jp/articles/7de...
思い込んだらどこまでも~堕ちたな「市民本位の民主市政をつくる会」
はじめに大間違いして拙速に公開質問しといて、相手が返事に困ると誠意がないだと?
このメンツで誰も同会の暴走を止められないんかいな。あきれるな。
元記事の怪しい醜聞に始まる怪騒動の誤爆。そら誰だって返事に困らぁな。
あべこべだ。誠意あるなら「うっかりにも踊らされて申し訳なかった」
「せめてものお詫びに全力で支える」と小川市長に謝罪せんかい。
真実はひとつだ。草葉の陰で角田儀一もお怒りだ。#負けるな小川あきら。
news.yahoo.co.jp/articles/7de...

前橋市長の回答「誠意ない」 ホテル密会問題、支援団体の公開質問に(朝日新聞) - Yahoo!ニュース
小川晶・前橋市長が既婚男性職員とラブホテルを利用していた問題で、「市民本位の民主市政をつくる会」(民主市政の会)は6日、記者会見し、小川市長に出した公開質問状の回答について「誠意も熱情も感じられな
news.yahoo.co.jp
November 7, 2025 at 9:09 AM
思い込んだらどこまでも~堕ちたな「市民本位の民主市政をつくる会」
はじめに大間違いして拙速に公開質問しといて、相手が返事に困ると誠意がないだと?
このメンツで誰も同会の暴走を止められないんかいな。あきれるな。
元記事の怪しい醜聞に始まる怪騒動の誤爆。そら誰だって返事に困らぁな。
あべこべだ。誠意あるなら「うっかりにも踊らされて申し訳なかった」
「せめてものお詫びに全力で支える」と小川市長に謝罪せんかい。
真実はひとつだ。草葉の陰で角田儀一もお怒りだ。#負けるな小川あきら。
news.yahoo.co.jp/articles/7de...
思い込んだらどこまでも~堕ちたな「市民本位の民主市政をつくる会」
はじめに大間違いして拙速に公開質問しといて、相手が返事に困ると誠意がないだと?
このメンツで誰も同会の暴走を止められないんかいな。あきれるな。
元記事の怪しい醜聞に始まる怪騒動の誤爆。そら誰だって返事に困らぁな。
あべこべだ。誠意あるなら「うっかりにも踊らされて申し訳なかった」
「せめてものお詫びに全力で支える」と小川市長に謝罪せんかい。
真実はひとつだ。草葉の陰で角田儀一もお怒りだ。#負けるな小川あきら。
news.yahoo.co.jp/articles/7de...
【#相模原市】11/7、来年度への市政運営・施策要望の提出!羽生田がく市議、上野たつやさん、さかたななさん とともに、この間市民のみなさんから集めた声を届けてきました!
市民サービス低下につながった行財政構造改革プランについて、職員の意見も踏まえ検証を、と求めました。
#日本共産党
市民サービス低下につながった行財政構造改革プランについて、職員の意見も踏まえ検証を、と求めました。
#日本共産党


November 7, 2025 at 9:02 AM
【#相模原市】11/7、来年度への市政運営・施策要望の提出!羽生田がく市議、上野たつやさん、さかたななさん とともに、この間市民のみなさんから集めた声を届けてきました!
市民サービス低下につながった行財政構造改革プランについて、職員の意見も踏まえ検証を、と求めました。
#日本共産党
市民サービス低下につながった行財政構造改革プランについて、職員の意見も踏まえ検証を、と求めました。
#日本共産党
「ムスリムが市政のトップに就いてもその人の了見がまともである限り自宗教への利益誘導なんかよりトータルな対市民判断が前提になる」
ってのは正のバランス感覚だけど、その「政治的判断においてひとの属性は同属への優先的な配慮を保証しない」という道理は
「まともじゃない輩が社会の高い座についたら、同じ当事者性のもとで苦しむ市民を損なう制度を平気で温存しうるし、なんなら積極的に傷付ける方へ進みうる(なぜなら自分は金や権力で問題をハックできるから)」
という負と裏表なのは考えときたい。
だから、〇〇の当事者が政に携わっても「〇〇なら誰でもいいってわけではない」と同じ属性の人から言われる例があるわけで。
ってのは正のバランス感覚だけど、その「政治的判断においてひとの属性は同属への優先的な配慮を保証しない」という道理は
「まともじゃない輩が社会の高い座についたら、同じ当事者性のもとで苦しむ市民を損なう制度を平気で温存しうるし、なんなら積極的に傷付ける方へ進みうる(なぜなら自分は金や権力で問題をハックできるから)」
という負と裏表なのは考えときたい。
だから、〇〇の当事者が政に携わっても「〇〇なら誰でもいいってわけではない」と同じ属性の人から言われる例があるわけで。
November 7, 2025 at 8:29 AM
「ムスリムが市政のトップに就いてもその人の了見がまともである限り自宗教への利益誘導なんかよりトータルな対市民判断が前提になる」
ってのは正のバランス感覚だけど、その「政治的判断においてひとの属性は同属への優先的な配慮を保証しない」という道理は
「まともじゃない輩が社会の高い座についたら、同じ当事者性のもとで苦しむ市民を損なう制度を平気で温存しうるし、なんなら積極的に傷付ける方へ進みうる(なぜなら自分は金や権力で問題をハックできるから)」
という負と裏表なのは考えときたい。
だから、〇〇の当事者が政に携わっても「〇〇なら誰でもいいってわけではない」と同じ属性の人から言われる例があるわけで。
ってのは正のバランス感覚だけど、その「政治的判断においてひとの属性は同属への優先的な配慮を保証しない」という道理は
「まともじゃない輩が社会の高い座についたら、同じ当事者性のもとで苦しむ市民を損なう制度を平気で温存しうるし、なんなら積極的に傷付ける方へ進みうる(なぜなら自分は金や権力で問題をハックできるから)」
という負と裏表なのは考えときたい。
だから、〇〇の当事者が政に携わっても「〇〇なら誰でもいいってわけではない」と同じ属性の人から言われる例があるわけで。
2021年大阪市は「広域的な観点からのまちづくり等に係る都市計画事務」を大阪府に委託した。しかし「一体化」ではなく「統合による分断」「市政の自律性の喪失」となった。
#府市一体化
#都市計画
#市民と市政
#まちづくり
#大阪の未来
#進化する自治
#府市一体化
#都市計画
#市民と市政
#まちづくり
#大阪の未来
#進化する自治

府市一体化による大阪市の劣化
以前大阪市は、特別区になるならないのために、グランドビジョンが描けない旨をレポートした。その騒ぎの水面下で大阪市の都市計画権限自体はすでに大きく削ぎ落とされている。2021年、大阪市は「広域的な観点からのまちづくり等に係る都市計画事務」を大阪府に委託した。これにより、都市計画区域の整備方針や高速道路、臨港地区など、大都市の骨格を形づくる計画群の決定権は府側に移った。名目上は「府市一体化」であり、二重行政の解消を謳う改革であった。しかし、その後の展開を観察すれば、「一体化」というよりも「統合による分断」、あるいは「市政の自律性の喪失」と呼ぶ方が実態に近い。 大阪市の判断が消えた都市行政 従来、大阪市は政令指定都市として、用途地域、防火地域、地区計画など、住民の生活や景観に密着した都市計画を自ら立案し、議会審議を経て決定する仕組みを持っていた。都市計画審議会も独立しており、地元の課題を地元で解くという原則が生きていた。だが、維新市政の下で進められた「府市一体行政」は、この独自の判断回路を府庁の中に取り込んでいった。都市計画局も事実上の「共同組織」となり、職員配置も混成化された。結果として、市職員の側からすれば、自らの専門判断が最終決定に反映されにくい構造となり、士気の低下は避けられなかった。 表向きには、これを「効率化」と説明する声が強い。確かに、道路や鉄道、広域的な土地利用調整など、府域全体で最適化すべきテーマは存在する。しかし問題は、現場の声と都市の肌理を理解する層が意思決定の中心から遠ざけられた点にある。用途地域や地区計画の計画決定一つ取っても、現場感覚なしに机上の計算で決めると、後からの軋轢が必ず生じる。実際、地元説明や調整の場では「府の方針だから」と説明されることが増え、市の担当者が従来のように柔軟に動けない状況が広がっている。 府にとっては「広域的視点での合理化」かもしれないが、市の現場から見れば「決定権を失った下請け行政」なのだ。都市計画とは、単なる線引きの作業ではなく、都市の未来像を共有し、その実現に向けて行政・住民・民間が合意形成を積み上げていくプロセスである。だが、現在の大阪では、このプロセスが中抜きされている。府の計画立案と、市の住民説明の間に意識の断絶が生まれ、双方の責任の所在も曖昧になった。 「マップナビおおさか」のHPから引用 市職員の士気低下と専門性の喪失 さらに深刻なのは、職員のモチベーションの低下である。大阪市の都市計画職は、長年にわたり全国でも屈指の技術集団として知られてきた。街路計画、再開発、景観形成、防災型まちづくりなど、多様な分野で先進事例を生み出してきた。しかし、今や多くの職員が「決められない立場」に追いやられ、自分たちの仕事が府庁の方針決定の補助に過ぎないと感じている。若手の育成も難しくなっており、「計画を描く喜び」よりも「説明責任の回避」が先に立つ行政文化が定着しつつあるのではないだろうか。 このような構造は、都市の「速度」を確実に鈍らせる。都市計画は、意思決定の速度と柔軟さが生命線である。地域からの提案を吸い上げ、タイムリーに制度化し、民間投資と連動させる。その循環が断たれれば、まちづくりはすぐに惰性化する。大阪では、まさにその惰性がじわじわと広がっている。都市再生特別地区や民間再開発の指定手続きにも時間がかかり、結果として企業は他都市へ流れている。府の一体化によって調整ルートは一本化されたが、実際の承認プロセスは以前よりも複雑で、決裁の段階が増えたにすぎない。まさに府市一体どころか、3重行政だ。 政治主導が専門性を覆う 加えて、政治的な色彩も濃くなった。維新市政が目指した「府主導の一元化」は、制度論的には筋が通っているように見えるが、政治的主導の強さが行政の専門性を覆い隠す場面が目立つ。都市計画の本質は専門技術と合意形成にあるはずだが、現実には「政治的メッセージ」としての都市開発が前面に出ている。万博、IR、夢洲開発――これらの巨大プロジェクトが象徴するのは、府政主導の「イベント都市」像であり、市民生活に根ざした都市計画とは異質のものである。 結果として、大阪市の「現場の知恵」は十分に活かされていない。現場の感度を失った都市は、いずれ「見かけだけの都市」になる。道路やタワーが整備されても、暮らしの質が伴わなければ都市は空洞化する。府市一体化が本当に大阪の未来を拓くのか、それとも自律的な都市経営力を失わせるのか。答えは、すでに現場の沈黙が物語っている。 制度としての政令指定都市は形式的に残っているが、その内実は解体されつつある。都市計画という行政の「哲学」が、効率化の名の下で削ぎ落とされている。このままでは、都市を構想する力そのものが大阪から失われかねない。都市の未来を描くには、再び現場の専門性と市民の声を中心に据えることが不可欠である。大阪が本当に「一体化」を目指すなら、行政権限の集中ではなく、信頼と共創の回復こそが必要である。府市の関係が垂直的な上下関係に戻ったとき、そこに広がるのは効率ではなく停滞である。 残念ながら、大阪万博、そしてIRに続く、次のイベントが必要な維新の会は、副首都を持ち出した。イベント都市大阪は一見華やかだが、大阪市民の基礎となる都市計画もグランドデザインもこのままでは望めない。 今こそ、大阪市は再び「自らの都市を描く」意志を取り戻すべき時であるのだが、これ以上のボタンの掛け違いはいつまで続くのであろうか。 3重行政の代表的な区分(抜粋) 1) 大阪府が決定(大阪市→府へ事務委託となったもの) 「広域・基幹インフラ」や都市構造に直結するものが中心である。 都市計画区域の整備・開発・保全の方針 区域区分(市街化区域/市街化調整区域) 都市再生特別地区 国際戦略港湾に係る臨港地区 高速自動車国道、一般国道、阪神高速道路 都市高速鉄道(地下鉄など) 一団地の官公庁施設/同予定区域(以上は「(2-2)指定都市が定める都市計画(府に事務委託)」として列挙) 大阪市公式ウェブサイト あわせて、市配布の「決定権限一覧表」でも、これら“委託”欄にマーキングあり。 大阪市公式ウェブサイト 2) 大阪市が決定(従来どおり市がまだ保持しているもの) 住民生活に密着し、地区スケールでのきめ細かな調整が要るものが中心。 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域 防火地域・準防火地域、高度地区・高度利用地区、景観地区、風致地区 ほかの地域地区 地区計画(沿道・集落・防災街区整備地区計画・特定用途誘導地区 等を含む) 生産緑地地区、特定生産緑地 駐車場整備地区 など(「(3)市町村が定める都市計画」および大阪府Q&Aの“市で引き続き行う事務”に明記) 大阪市公式ウェブサイト+1 3) 規模等で主体が分かれる代表例(資料の表に基づく) 公園・緑地:面積10ha以上→府(委託)/10ha未満→市。 大阪市公式ウェブサイト 道路:一般国道・都道府県道→府(委託)/市道等は市(項目別に整理)。 大阪市公式ウェブサイト 土地区画整理・市街地再開発などの面的整備事業:施行主体や面積閾値(例:50ha超 等)で区分(指定都市が定める扱いとされる類型もあり)。 大阪市公式ウェブサイト 根拠資料 大阪市「都市計画審議会及び都市計画決定権限について」決定権限の一覧表付き(“うち府へ事務委託”欄で判別可能)。 大阪市公式ウェブサイト+1 大阪市「大阪市における都市計画決定の手続き」(2-2)府に事務委託に該当する具体項目を列挙。 大阪市公式ウェブサイト 大阪府Q&A「府市の一体的な行政運営…」市が継続する事務(用途地域、土地区画整理、地区計画など)を明記。 大阪府公式サイト <山口 達也> ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
November 7, 2025 at 3:01 AM
公平とは何か、公正とは何か、行き過ぎとは何か。
政治とは「公正の担保」である。公平という形式的平等と、公正という実質的平等。その両者の間で社会の納得を得る線引きを行い、行き過ぎを抑制する。
では、現在の日本、いまの大阪は?
#進化する自治
#市民と市政
#vision50
政治とは「公正の担保」である。公平という形式的平等と、公正という実質的平等。その両者の間で社会の納得を得る線引きを行い、行き過ぎを抑制する。
では、現在の日本、いまの大阪は?
#進化する自治
#市民と市政
#vision50

政治とは―公平・公正・行き過ぎから考える
進化する自治というが、そもそもの、「政治とは何なのか。」この問いは古代から現代に至るまで繰り返し議論されてきた根源的なテーマである。アリストテレスは人間を「ポリス的動物」と呼び、共同体を形成することこそ人間の本質であると説いた。その共同体の運営を担う仕組みこそ政治である。では、政治は具体的にどのような役割を持ち、民主主義の下ではどう機能すべきなのか。本稿では「公平(Equality)」「公正(Equity)」「行き過ぎ(Excessive)」という三つの概念を軸に考察する。 公平とは何か 公平とは「誰に対しても同じ扱いをすること」である。選挙で一人一票が保障されるのは典型的な公平の仕組みである。税率を一律に設定することもまた公平の表現である。公平は形式的な平等を重視し、誰もが同じルールの下に置かれることを意味する。 しかし、形式的な公平はしばしば実質的な不平等を生み出す。たとえば、学習に困難を抱える子どもと、特別な支援を必要としない子どもに、同じ授業だけを与えるとすれば、結果的に前者は学習機会を失う。形式的な公平は必ずしも機会の均等を保障しないのである。 公正とは何か 公正とは、状況や背景に応じて妥当な配慮を行い、実質的な平等を確保することである。生活困窮者に対する生活保護や給付金、障がいのある人へのバリアフリー化、災害被災地への特別支援は、公正の観点から導かれる政策である。 つまり、公平が「同じ扱い」を目指すのに対して、公正は「違いを考慮したうえで実質的に平等な結果を目指す」点に特徴がある。政治はこの「公正」を担保する仕組みとしての性格を持つ。ジョン・ロールズが唱えた「正義とは社会制度の第一の徳である」という言葉は、政治の本質を突いている。 行き過ぎとは何か しかし、公正を重視しすぎると「行き過ぎ(Excessive)」が生じる。過剰な優遇策や特例は、他の人々に不公平感をもたらし、社会の信頼を損なう。支援の対象が不透明であったり、特定の利益集団のみに偏った政策が行われたりすれば、それは「行き過ぎ」として批判を受ける。 公平を強調しすぎれば弱者を切り捨て、公正を強調しすぎれば過剰な優遇に陥る。このバランスをどう取るかが、政治の核心にある課題なのである。 民主主義と三つのバランス 民主主義の下での政治は、この公平・公正・行き過ぎの三つの力学の中で均衡を保つことが求められる。 公平の確保 法の下の平等、一票の平等といった基本原則は揺るがせにできない。すべての市民が同じルールの下に置かれることは、民主主義の基盤である。 公正の実現 しかし現実には格差や不利な状況に置かれる人々が存在する。そのため、公正の観点から追加的な支援を行い、実質的な平等を確保する必要がある。 行き過ぎの抑制 公正を理由にした過剰な優遇や、政治権力の私物化による不当な利益分配は避けなければならない。そのためにこそ、透明性と市民による監視が不可欠である。 この三つの視点はトレードオフの関係にあるため、常に絶妙な調整を必要とする。その調整を担うのが、政治という営みである。 政治とは公正の担保である ここで改めて「政治とは何か」を問うならば、それは「公正の担保」であると言えるだろう。公平という形式的平等と、公正という実質的平等。その両者の間で社会の納得を得る線引きを行い、行き過ぎを抑制する。その役割を果たすために、政治は存在している。 もちろん、現実の政治は必ずしも公正を担保できているわけではない。政権維持のための権力闘争や、特定の利益集団に偏った政策、あるいは世論操作による「見せかけの公正」は枚挙にいとまがない。だからこそ、市民による不断の監視と参加が不可欠である。民主主義とは「完全な公正が与えられる体制」ではなく、「常に公正を追求し続ける体制」である。 緊張感が保てない長期政権 民主主義における政治は、次の三点に集約される。 公平を基盤とし:すべての人に基本的権利を等しく保障する 公正を追求し:不利な立場の人々に配慮し、実質的な平等を実現する。 行き過ぎを抑制:過剰な優遇や権力の乱用を防ぐため、透明性と説明責任を果たす。 この三つが有機的に結びつくとき、政治は人々の信頼を得て、民主主義は健全に機能する。政治とは単に権力の行使ではなく、社会の公正を守るための制度的担保である。そしてその担保は、市民一人ひとりの参加と監視によって初めて現実のものとなるのである。 そういう意味で、長期政権になると、この公正性の制度が担保しにくくなる。二元代表制の元、市長と議員がグルになってしまうとこの公正性は全く機能しなくなる。現時点での大阪市政はまさしくその状態であり、原理原則からみても、今の大阪市政は非常に危険な状態である。具体的な内容については、またコラムで伝えていきたい。 <山口達也> ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
November 7, 2025 at 1:11 AM
東京都の市民参加型予算。制度を導入して行政側はどのように受け止めているか。また実際に参加、提案した市民はこの制度をどのようにとらえているだろうか。
#進化する自治
#市民参加型予算
#市民と市政
#vision50
#進化する自治
#市民参加型予算
#市民と市政
#vision50

行政の予算編成への市民参加で「公共」はどう変わる?-3
東京都の市民参加型予算。制度を導入して行政側はどのように受け止めているか。また実際に参加、提案した市民はこの制度をどのようにとらえているだろうか。 #進化する自治 #市民参加型予算 #市民と市政 #vision50
ucosaka.com
November 6, 2025 at 1:15 AM
出演は市民と市長! 市民と共につくる市政情報ドラマ『明智さんのシセイカツ』スタート! 市政 …
↓↓続きはこちら↓↓
https://zmedia.jp/drama/660854/?utm_source=Bluesky
↓↓続きはこちら↓↓
https://zmedia.jp/drama/660854/?utm_source=Bluesky
November 5, 2025 at 7:03 AM
出演は市民と市長! 市民と共につくる市政情報ドラマ『明智さんのシセイカツ』スタート! 市政 …
↓↓続きはこちら↓↓
https://zmedia.jp/drama/660854/?utm_source=Bluesky
↓↓続きはこちら↓↓
https://zmedia.jp/drama/660854/?utm_source=Bluesky
会派日高見会行政視察2日目は北海道登別市。人口42,900人(2025年9月末現在)、面積212.1 km²。議会改革度調査において、2022〜2024年度の3か年で1位となっている先進的な議会(2023年度で石巻市議会は298位)。『多様性のある議会の実現』をビジョンに掲げ、議論する議会の見える化への取組、住民参画の取組やデジタルツールを活用している。 議長公約・所信表明、議長諮問。市民満足度や住民ニーズをいかに市政へ反映させていくかが重要と思われる。政策形成サイクルなど登別市の取組を本市議会の改革の参考に実現としたい。

November 5, 2025 at 6:07 AM
会派日高見会行政視察2日目は北海道登別市。人口42,900人(2025年9月末現在)、面積212.1 km²。議会改革度調査において、2022〜2024年度の3か年で1位となっている先進的な議会(2023年度で石巻市議会は298位)。『多様性のある議会の実現』をビジョンに掲げ、議論する議会の見える化への取組、住民参画の取組やデジタルツールを活用している。 議長公約・所信表明、議長諮問。市民満足度や住民ニーズをいかに市政へ反映させていくかが重要と思われる。政策形成サイクルなど登別市の取組を本市議会の改革の参考に実現としたい。
市民と市長が共演!福知山で始まる新たな市政情報ドラマ#京都府#福知山市#市政情報#明智さん
市民と市長が共演する新感覚の市政情報ドラマ『明智さんのシセイカツ』が、11月4日から福知山市公式YouTubeとInstagramに登場。市の取り組みを身近に感じられる内容です。
市民と市長が共演する新感覚の市政情報ドラマ『明智さんのシセイカツ』が、11月4日から福知山市公式YouTubeとInstagramに登場。市の取り組みを身近に感じられる内容です。

市民と市長が共演!福知山で始まる新たな市政情報ドラマ
市民と市長が共演する新感覚の市政情報ドラマ『明智さんのシセイカツ』が、11月4日から福知山市公式YouTubeとInstagramに登場。市の取り組みを身近に感じられる内容です。
news.3rd-in.co.jp
November 4, 2025 at 8:24 AM
日本で「市民参加型予算」の実例が見られるようになるのは、2000年に地方分権一括法が施行されて以降。参加型予算の事例から「市民自治」を考える。
#進化する自治
#市民参加型予算
#市民と市政
#vision50
#進化する自治
#市民参加型予算
#市民と市政
#vision50

行政の予算編成への市民参加で「公共」はどう変わる?-2
「住民の関与」が「市民自治」につながるか? 日本で導入された事例から考える 地方分権改革を起点に始まった地方行政の変化とともに 日本で「市民参加型予算」の実例が見られるようになるのは、2000年に地方分権一括法が施行されて以降。従来自治体の予算は法令や国の補助金で制約された部分が多かったが、一括法により予算編成の自由裁量権が広がったことがひとつ。もう一つには、1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、市民活動の幅の広がりなどが要因とみられている。「自治体予算編成過程への市民参加」(末尾出典参照)によれば、2003年の時点で、日本における自治体予算編成過程への市民参加として3つのタイプを挙げられている。 既存の制度の説明責任の向上を目指して予算編成過程を公開するあるいはわかりやすい予算書を作成する 市役所とは別に市民が自治体予算全体の見直しと予算案作成を行う 市予算のうちの一部を自治体内の地区に交付し市民が地区予算を編成する この時点では、海外で多く見られるような「事業アイデアを住民から募る」は、3の予算の一部を自治体内の地区に交付・配分する形式が該当する。「自治体予算編成過程への市民参加」でも事例として挙げられている三重県名張市の「ゆめづくり地区予算制度」が代表的で、2003年(平成15)にスタートし現在も行われている。時代をさかのぼり2010年ころには、その取り組み方も多様化し、中でも(4)の「1%支援制度」が注目されるようになっている。「まちづくりに関する日本の参加型予算の現状と可能性」(末尾出典参照)では、参加型予算の取り組みを5つのタイプに分類。各タイプは、下記に示すような手法で行われているが、いずれも海外事例のような「市民の直接的参加」という手法とまでは言えない。 予算編成過程の公開 編成過程での情報公開と市民意見の収集・反映 参考:全国市民オンブズマン連絡会議「予算編成過程・住民参加状況調査」 (予算編成過程=予算要求・予算査定段階での情報公開、住民参加=意見を述べる手段の有無や意見の公表、回答の公表 など) 市民委員会による予算案の作成(現在は行われていない) 例:志木市「市民委員会」設置と「市民予算編成」 (市民委員会は公募。情報は行政各部署が提供、それに基づき予算のムダを分析して積算の増減の可能性を検討 (優先順位ではなく変更可能性を提示)、市民予算説明会で行政の予算案とともに公表) 予算の一部を自治体地区に交付 例:名張市ゆめづくり地域予算制度 市民活動団体への支援 例:和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業(R2まで)個人住民税1%を市民投票により補助 市民税1%相当額を予算枠とし、その配分を市民活動団体への市民の投票で決める 市民提案事業 予算前にNPOから事業提案を受ける 例:千葉県「パートナーシップ市場」(現在は廃止、詳細不明) 成功の要因(兼村2024「再び住民参加予算の登場と今後の展望」) ※これらの取り組みの一部(③類似の取り組み)や、日本版BID(業務地区、商業地区の事業者についての合意をとったうえで、エリアマネジメントのための費用を徴収して使うしくみ)、ふるさと納税がPB World Atlasでは参加型予算類似の仕組みとして扱われたこともあったが、2020年版では外されている(「ポルトガルにおける参加型予算の制度と実践」藤原 遥 2023年) 日本での市民参加型予算は、政府以外の主体が課題解決するためのスキームを含んでいるが、国際的にみれば必ずしもそうではない海外にも事業提案型の市民参加型予算が存在するが、事業提案段階、説明会や投票段階には、行政やNPOなどの関与がある。提案~決定~実行の各段階において市民が参加できるチャネルがあり、参加する機会をつくる多様なしくみが用意されている。 1%支援制度 「1%支援制度」は、一定の条件を満たした市民が、自分の応援したい市民活動団体を選択して届け出ることができ、その選択結果に基づき団体に支援金が交付される制度である。ハンガリーで始まった、自身の所得税の1%を指定した団体に寄付できる制度が発端のため、俗にこう呼ばれている。市民が直接、意思表示をする点がこの制度のポイントである。現在、千葉県市川市、北海道恵庭市、岩手県奥州市、愛知県一宮市、大分県大分市、千葉県八千代市、大阪府和泉市で制度が導入されている。3つの特徴1.市民が直接選択する 地域課題の解決方法を市民活動団体が市民に提案し、その賛同票を得られれば、その分補助金が得られる。2.多様な市民活動団体に公的資金が流れるルートができる 従来の補助金という枠組みでは公的資金が流れることがなかった団体に補助金が流れている3.地域全体を巻き込んだ取り組み これまで市民活動とあまり接点のなかった市民もが、参加するチャネルを開く仕組みとなっている 地方分権から都市内分権へを謳う名張市「ゆめづくり地域予算制度」 先に挙げた、日本における参加型予算の事例として名張市の「ゆめづくり地域予算制度」は、使途自由の一括交付金として始まった制度だった。当初(2003年)、14地域で結成された「地域づくり委員会」に対し、使途自由な一括交付金(5,000 万円:現在の基本額に相当)を交付。応募型の市民公益活動実践事業として始まった。しかし20年の間に改善を重ね、2012年に「ゆめづくり協働事業提案制度」という、地域と市が協議しながら新たなサービスや価値を生み出すための協働事業に刷新され、現在に至っている。住民の合意により設立された住民主体のまちづくり組織である「地域づくり組織」→各地区ごとの「まちづくり協議会」が事業の提案者であり担い手でもある。地域に対する予算割り当てを基本としてはいるが、現在の同制度は、「市民の直接参加」、「市民提案」、「熟議」、「市民×行政の協働」というかたちを備えていると言えよう。各地区の「まちづくり協議会」の運営に当たっては行政のサポートが行われているので、行政主導とも言えなくはない。例えば事業分野では、次のように分類され、それぞれのテーマに合った事業提案が行われている。 名張市のゆめづくり地域予算制度の交付金内容 自主防犯、自主防災 人権、健康、福祉 環境、景観の保全 高齢者の生きがいづくり 子どもの健全育成 地域文化の継承、創出 コミュニティビジネス 住民交流、地域振興 その他 各地域ごとに振り分けられれば個々の予算額はそれほど大きいわけではないが、地域の課題改善、市民の主体的なまちづくりという点では、大いに機能していると思われる。 【事業例】70歳以上単身高齢者交流会小学校新入生に「命の笛」贈呈ラジオ体操支援防災関係資機材の整備給食ボランティア支援稲作体験教室防災井戸を活用した蔵清水カフェウォークラリー大会伝統文化教室(獅子神楽)開催コミュニティバス運行放課後児童クラブ支援道標(案内板)設置事業くわしくは、webサイト名張市ゆめづくり地域予算制度 これまで見てきたように「市民参加型予算制度」には様ざまな手法が行われてきた。しかし、海外で始まり発展を遂げてきている、市民が地域や市民生活をテーマに行政に対し直接「事業提案」を行うしくみについては、2017年に東京都が行った事例が挙げられる。ucoでは、市民がより行政に関与する手法として、「市民参加型予算制度」について理解を深めるため、そうした事例について一昨年に調査。東京都、三重県、長野県、東京都杉並区の4自治体へのインタビューを行った。 次回はそれぞれの自治体の制度のしくみや実施内容についてみていこうと思う。 前の記事を読む 続きを読む 出典●「自治体予算編成過程への市民参加」松田真由美(公立鳥取環境大学客員研究員)(調査研究報告 地域生活空間 TORCレポート №26 2004年) 出典●まちづくりに関する日本の参加型予算の現状と可能性 ~NPOをはじめとする市民社会組織による役割を中心に~松原 明、鈴木 歩 『まちと暮らし研究』 No.13 (一般財団法人 地域生活研究所 2011年6月20日発行)「新しい公共」の社会設計にむけて 出典●「ポルトガルにおける参加型予算の制度と実践」(藤原 遥 福島大学経済経営学類准教授) ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
November 4, 2025 at 12:00 AM
今日は名古屋観光してきたぞ!
名古屋市役所、愛知県庁、名古屋市市政資料館。
全部初めて行った・・・(名古屋市民じゃないので)。
古い建築物が大好きなのですっごく楽しかった!
いつか無くなってしまうかもしれないので行けてよかった🥰
名古屋市役所、愛知県庁、名古屋市市政資料館。
全部初めて行った・・・(名古屋市民じゃないので)。
古い建築物が大好きなのですっごく楽しかった!
いつか無くなってしまうかもしれないので行けてよかった🥰




November 3, 2025 at 10:53 AM
今日は名古屋観光してきたぞ!
名古屋市役所、愛知県庁、名古屋市市政資料館。
全部初めて行った・・・(名古屋市民じゃないので)。
古い建築物が大好きなのですっごく楽しかった!
いつか無くなってしまうかもしれないので行けてよかった🥰
名古屋市役所、愛知県庁、名古屋市市政資料館。
全部初めて行った・・・(名古屋市民じゃないので)。
古い建築物が大好きなのですっごく楽しかった!
いつか無くなってしまうかもしれないので行けてよかった🥰
分からなくありません! 色々なことが話されてはいますが、そもそも市政とは市民の為にあるものじゃないんですか
November 3, 2025 at 1:02 AM
分からなくありません! 色々なことが話されてはいますが、そもそも市政とは市民の為にあるものじゃないんですか
王*公園の土地も、ゆくゆくはこんな感じで私立大学の利益のためだけに使われたりするのでしょうね~。
市(市民)の共有財産を、特定の私立大学に払い下げるなんて、ほんと馬鹿げた事がまかり通っている神戸市政。
何期も同じご老人が市長を継続しているようではね。
でも、それも有権者の選択(笑
www.rakumachi.jp/news/column/...
市(市民)の共有財産を、特定の私立大学に払い下げるなんて、ほんと馬鹿げた事がまかり通っている神戸市政。
何期も同じご老人が市長を継続しているようではね。
でも、それも有権者の選択(笑
www.rakumachi.jp/news/column/...

土地代で45億稼ぐ科学大、クラファンでトイレ改修する金沢大…国立大学「金策」の明暗|楽待不動産投資新聞
運営費が減る時代、大学はどう動くのか
www.rakumachi.jp
November 2, 2025 at 6:50 AM
王*公園の土地も、ゆくゆくはこんな感じで私立大学の利益のためだけに使われたりするのでしょうね~。
市(市民)の共有財産を、特定の私立大学に払い下げるなんて、ほんと馬鹿げた事がまかり通っている神戸市政。
何期も同じご老人が市長を継続しているようではね。
でも、それも有権者の選択(笑
www.rakumachi.jp/news/column/...
市(市民)の共有財産を、特定の私立大学に払い下げるなんて、ほんと馬鹿げた事がまかり通っている神戸市政。
何期も同じご老人が市長を継続しているようではね。
でも、それも有権者の選択(笑
www.rakumachi.jp/news/column/...
📌「伊東市 田久保市長 不信任」の関連ニュース
伊東市の田久保市長が議会から2度目の不信任を受け、失職しました。市民の関心が集まる中、今後の市政運営がどう変わるのか注目です。詳しくはこちら→…
伊東市の田久保市長が議会から2度目の不信任を受け、失職しました。市民の関心が集まる中、今後の市政運営がどう変わるのか注目です。詳しくはこちら→…
【図解】伊東市長が失職=議会2度目の不信任―静岡(時事通信) - Yahoo!ニュース
伊東市の田久保市長が議会から2度目の不信任を受け、失職しました。市民の関心が集まる中、今後の市政運営がどう変わるのか注目です。詳しくはこちら→ [記事リンク](https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTE05bl9uTDMxYVlMa1dITHZ6ZEhFR0JPNXg1OXZOb2FHQ0ZvY0Nzb3Mtb2JoaHE5WmlqekV
news.google.com
October 31, 2025 at 7:53 AM
📌「伊東市 田久保市長 不信任」の関連ニュース
伊東市の田久保市長が議会から2度目の不信任を受け、失職しました。市民の関心が集まる中、今後の市政運営がどう変わるのか注目です。詳しくはこちら→…
伊東市の田久保市長が議会から2度目の不信任を受け、失職しました。市民の関心が集まる中、今後の市政運営がどう変わるのか注目です。詳しくはこちら→…
大阪府・市が描く副首都ビジョンの先にあるもの-2
https://ucosaka.com/column/20250930/
維新の会の言う「副首都」とはどういう位置づけなのか? 経済指標と一体となった評価は「副首都」の指標としてふさわしいものなのか? 首都にふさわしいまちづくりとは?
#進化する自治
#副首都ビジョン
#市民と市政
#vision50
https://ucosaka.com/column/20250930/
維新の会の言う「副首都」とはどういう位置づけなのか? 経済指標と一体となった評価は「副首都」の指標としてふさわしいものなのか? 首都にふさわしいまちづくりとは?
#進化する自治
#副首都ビジョン
#市民と市政
#vision50

大阪府・市が描く副首都ビジョンの先にあるもの-2
「日本の都市特性評価」において大阪市が5年連続総合1位とは? 前回、日本における「副首都」とはどういう位置づけなのかが、はっきりしない、という話を大阪府・市副首都推進局が提示している「Beyond EXPO 2025~万博後の大阪の未来に向けて~骨子(案)」をもとに探っていった。この中では、直近10年(2015-2024年)の大阪の取組みをベースに、大阪が以前と比べてより成長する基盤がつくられてきたか、今後の発展が期待できる、といった内容が満載である。具体的な取り組みとしてここで表されている項目といえば、「経済成長」、「都市魅力の向上」、「人材育成・集積」といった内容。(下図「直近10年(2015-2024年)の大阪の取組み(主なもの)」参照) 出典:「Beyond EXPO 2025~万博後の大阪の未来に向けて~骨子(案)」 経済成長では、・成長産業拠点の形成、・まちづくり・インフラ整備が挙げられており、相変わらずの新たな開発を続けるという60年代、70年代の土建国家よろしい前時代的な発想にしか見えない。「拠点づくり」という開発であって、拠点を育てる産業支援が項目としてさえ上がっていない。また都市魅力の向上として挙げられているのが、「世界遺産(百舌鳥・古市古墳群)」、「中之島美術館の開設」、「PMO/PPP/PFIによる都心の魅力づくり」などだ。世界遺産登録などは確かに魅力向上にはなるだろうし、集客力アップにつながっているのも知れない。だが、中之島美術館やPMO/PPP/PFIによる都心の魅力づくりは、ほんとうに「都市の魅力づくり」になっているといえるだろうか。中之島美術館が大都市の美術館として魅力ある企画を行っているのかは様ざまな意見があろうかと思う。ことは美術館の企画そのものではなく、この美術館がPFI法に基づき、株式会社大阪中之島ミュージアムが運営している、いわゆる「PFIコンセッション方式」にあると思う。大阪府・市は、公園や美術館といった公共施設を民間企業を運営権者として導入するPMO、PFIといったコンセッション方式を多用している。公園の運用を任せることと引き換えに、公園内の一部のエリアを商業施設等を設置することを認め、樹木の伐採や植物園の縮小などが行われ、公園内に誰もが利用できる場ではない空間を生み出している。現在の大阪府・市が都市魅力の向上として中之島美術館をクローズアップさせる一方、他の美術館や博物館に対してどれほどの支援が行われているだろうか。橋下市長時代、市内の美術館、博物館を統廃合し、当時想定されていた「新美術館」に一元化し、民間資金を導入するという意向が喧伝された。なんでも一つにすればいいというものでもない。1か所にした後は、市有地を売却することしか考えていないのだから。現在は「地方独立行政法人大阪市博物館機構」による美術館・博物館の経営は統合される中、中之島美術館の存在だけが宣伝されている。「文化」に対して経営効果・効率だけを指標とする方針のもとで運営されることが、大阪府・市の言う「にぎわい」や「都市の魅力」につながるのだろうか、と考えるわけである。 日本の都市特性評価に表される評価内容と上位であることの意味 先に進もう。現在の大阪は、様ざまな視点から総合力として優れた都市となったという。その指標が、森記念財団 都市戦略研究所が毎年行っている「日本の都市特性評価」だ。ここで表されている「合計スコア上位10都市 結果・分析」から大阪市、名古屋市、福岡市の上位3位と、それに続く横浜市、京都市、神戸市を見てほしい。 出典:日本の都市特性評価2025(森記念財団都市戦略研究所) 大阪市は経済・ビジネスや交通・アクセス、文化・交流では1位、2位となっている。が、環境では134位、生活・居住も47位と評価は低い。生活・居住は前年度よりも劣っている。上位3都市では環境はいずれも評価が低くなっていることから、都市のあり方、あるいは考え方に偏在があるということだ。環境の指標として「温暖化対策」や「自然環境」、「気候」など5項目あるが大阪市の評価が低くなるのは、再生可能エネルギー自給率の低さや都市地域緑地率の低さ、夏の涼しさ・冬の暖かさなどに問題があるということだ。ただ、他の分野の指標にもおかしさを感じる項目がある。例えば文化。交流では、ハード資源として観光地の数や文化財指定件数が増加したことで評価が上がっており、ソフト資源ではイベントの数が増えたことにより評価が上がっている。評価が上がったことには納得するものがある。市や外郭団体、PMO方式による公園でのイベントが年中ひっきりなしに行われている。また休日の人の多さや行楽・観光目的の訪問の多さもあれば、観光客誘致活動も評価指標の一つということからも、経済指標と一体となった評価となっていることがわかる。研究・開発でも、研究集積の指標が学術・開発研究機関従業者割合であったり、研究開発成果として論文投稿数や特許取得数が指標となっている。どういう内容か、あるいは研究成果の社会的影響度などは指標にはなっていない。一方、4位の横浜市や6位の神戸市などは、突出した分野があるわけではないが、どの分野もある程度平均的な指標を示している。しかも前年と比べて極端に上下しているわけでもない。指標グループ別の偏差値で比べてみれば、大阪市の極端さが見て取れる。経済活動は120以上を示しているが、雇用や雇用の多様性は極端に低い。健康・医療も低くなっているし市民生活・福祉も低いなど、市民にとって実は住みづらく、魅力に乏しいことが現れている。 出典:日本の都市特性評価2025(森記念財団都市戦略研究所) 現在の首都エリアに見られるまちづくりとは 様ざまな分野での安定さが求められる「副首都」として、こうした極端な都市がふさわしいと言えるのだろうか。例えば東京23区の上位4区を参考までに掲載しておこう。大阪市と比べていただければ、各分野で極端な差異があまりないことに気が付くと思う。大阪府・市は、盛んに「副首都」の重要性をアピールし、大阪が日本の経済をけん引する都市にふさわしいと喧伝するのだが、自分たちが「優れている」とする指標をもってしても、そうではないことが読み取れると思う。特に「世界」を相手にトップ都市と肩を並べたいのであれば、温暖化対策や廃棄物対策、自然環境といった指標を大幅に改善する政策転換が必要だと提言しておく。 出典:日本の都市特性評価2025(森記念財団都市戦略研究所) 前の記事を読む 続きを読む ucoの活動をサポートしてください
ucosaka.com
October 31, 2025 at 1:41 AM
地域の「風景」を価値あるものにする起業家のこと【2025.10.29号】uco
note.com/ucosaka/n/n1...
♪地域が誇れる文化をどのようにしてつなぐのか、一つの解を学ぶ
地域を活性化させ、自分たちのまちの、自分たちの文化だと誇れるものをつくり出す
#進化する自治
#まちづくり
#市民と市政
#vision50
note.com/ucosaka/n/n1...
♪地域が誇れる文化をどのようにしてつなぐのか、一つの解を学ぶ
地域を活性化させ、自分たちのまちの、自分たちの文化だと誇れるものをつくり出す
#進化する自治
#まちづくり
#市民と市政
#vision50

地域の「風景」を価値あるものにする起業家のこと【2025.10.29号】|UCO https://ucosaka.com/
♪地域が誇れる文化をどのようにしてつなぐのか、一つの解を学ぶ いまから11年ほど前、あるボランティア活動の会議が山形県であり、酒田市沖合にある離島の飛島に行ったことがある。島を巡るツアーがあり、それをコーディネイトしていたM氏と知り合った。彼は数年前に飛島に移住し、この島で地域づくり会社を起こし、運営していることを知った。当時まだ20代だったが、とても精力的に、そして楽しく活動していたことが記憶...
note.com
October 29, 2025 at 11:20 AM
地域の「風景」を価値あるものにする起業家のこと【2025.10.29号】uco
note.com/ucosaka/n/n1...
♪地域が誇れる文化をどのようにしてつなぐのか、一つの解を学ぶ
地域を活性化させ、自分たちのまちの、自分たちの文化だと誇れるものをつくり出す
#進化する自治
#まちづくり
#市民と市政
#vision50
note.com/ucosaka/n/n1...
♪地域が誇れる文化をどのようにしてつなぐのか、一つの解を学ぶ
地域を活性化させ、自分たちのまちの、自分たちの文化だと誇れるものをつくり出す
#進化する自治
#まちづくり
#市民と市政
#vision50
改めて問い直したい大阪市が適正とする教育環境と規模【2025.10.27号】uco
note.com/ucosaka/n/n8...
マンモス校と過小規模校が隣接する小学校区の教育環境課題
#進化する自治
#市民と市政
#教育課題
#vision50
note.com/ucosaka/n/n8...
マンモス校と過小規模校が隣接する小学校区の教育環境課題
#進化する自治
#市民と市政
#教育課題
#vision50

改めて問い直したい大阪市が適正とする教育環境と規模【2025.10.27号】|UCO https://ucosaka.com/
マンモス校と過小規模校が隣接する小学校区の教育環境課題 長く続いた酷暑がようやく終わり、短くなった秋空の下、小学校では運動会シーズンとなり私の住む地域でも先週末に開催された。この地域は古くから文教地区として有名で、学区が取っ払われた現在でも人気が高く、総児童数が1200名を超える市内でも有数のマンモス校となっている。そのため運動会は午前・午後の二部制での開催が長い間続いている。今年度の開催案内で...
note.com
October 28, 2025 at 11:26 AM
改めて問い直したい大阪市が適正とする教育環境と規模【2025.10.27号】uco
note.com/ucosaka/n/n8...
マンモス校と過小規模校が隣接する小学校区の教育環境課題
#進化する自治
#市民と市政
#教育課題
#vision50
note.com/ucosaka/n/n8...
マンモス校と過小規模校が隣接する小学校区の教育環境課題
#進化する自治
#市民と市政
#教育課題
#vision50