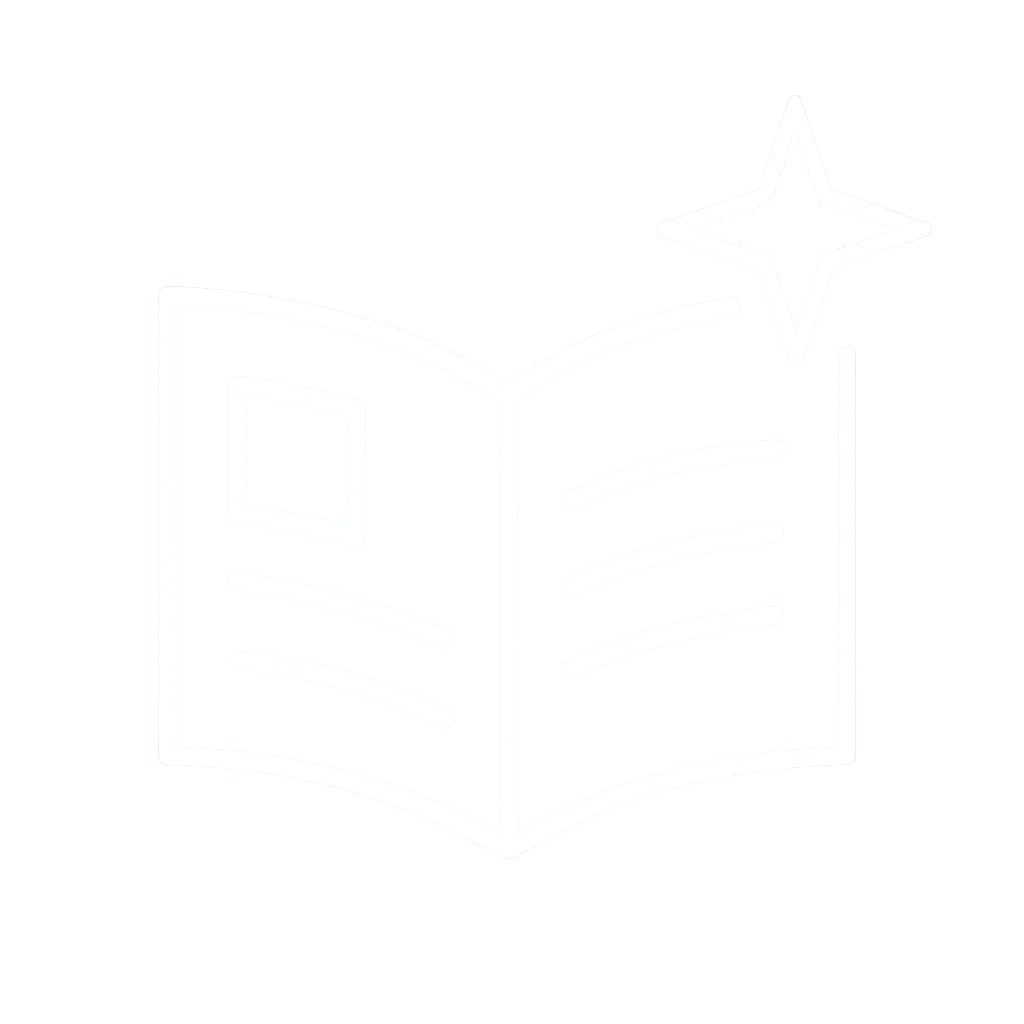哲学・文学・宗教bot
@hys3go.bsky.social
100 followers
1 following
13K posts
ぼくのかんがえたさいきょうのbot
ニーチェ(379),ウィトゲンシュタイン(327),三島由紀夫(241),シュペングラー(205),ゲーテ(180),ドストエフスキー(115),カフカ(102),聖書(99),カント(99),オスカー・ワイルド(61),太宰治(59),ショーペンハウアー(37),その他(356)
2時間毎に投稿します
4.5ヶ月くらいで1周します
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
哲学・文学・宗教bot
@hys3go.bsky.social
· Nov 17