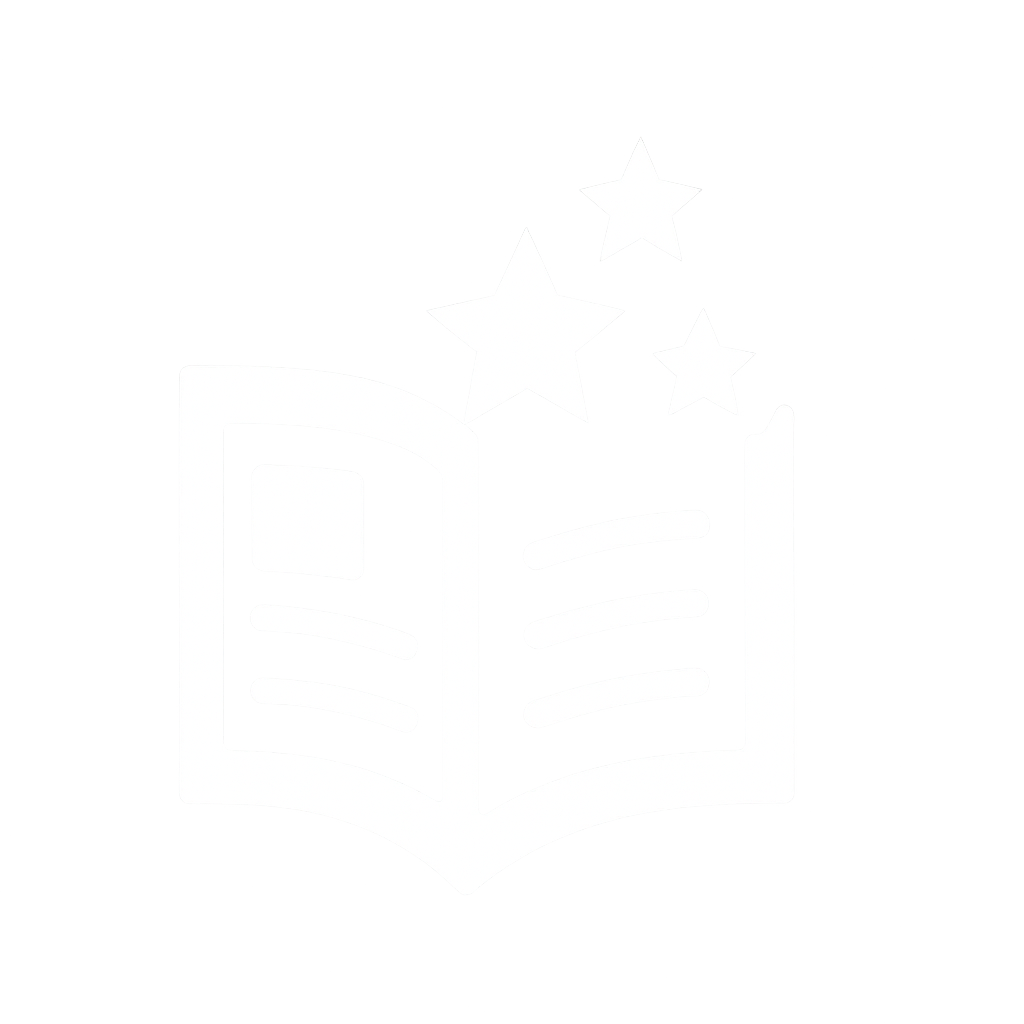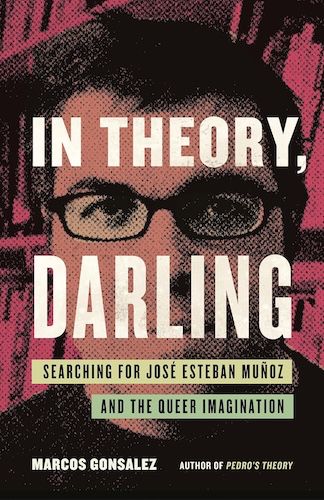エミコヤマ
@macska.org
1.7K followers
75 following
7K posts
うにはともだち(エレン・デジェネレスの声で)
読書報告: http://books.macska.org
seattle/portland
Posts
Media
Videos
Starter Packs
エミコヤマ
@macska.org
· 25m
エミコヤマ
@macska.org
· 25m
エミコヤマ
@macska.org
· 25m
エミコヤマ
@macska.org
· 25m
エミコヤマ
@macska.org
· 25m
エミコヤマ
@macska.org
· 1h
エミコヤマ
@macska.org
· 2h
エミコヤマ
@macska.org
· 11h
エミコヤマ
@macska.org
· 12h
エミコヤマ
@macska.org
· 12h
エミコヤマ
@macska.org
· 12h
エミコヤマ
@macska.org
· 13h
エミコヤマ
@macska.org
· 14h
エミコヤマ
@macska.org
· 14h

Alexis Pauline Gumbs著「Survival Is a Promise: The Eternal Life of Audre Lorde」
Alexis Pauline Gumbs著「Survival Is a Promise: The Eternal Life of Audre Lorde」 没後30年を過ぎたいまも多くの人たちに影響を与え続けている黒人レズビアン詩人オードリー・ロードの新しい伝記。 ロードが亡くなったとき著者はまだ10歳で、彼女が書き残したものや彼女を知る年上の世代から聞いた話で彼女について知ったと思われる。…
books.macska.org
エミコヤマ
@macska.org
· 14h
エミコヤマ
@macska.org
· 14h
エミコヤマ
@macska.org
· 14h
エミコヤマ
@macska.org
· 16h
エミコヤマ
@macska.org
· 16h