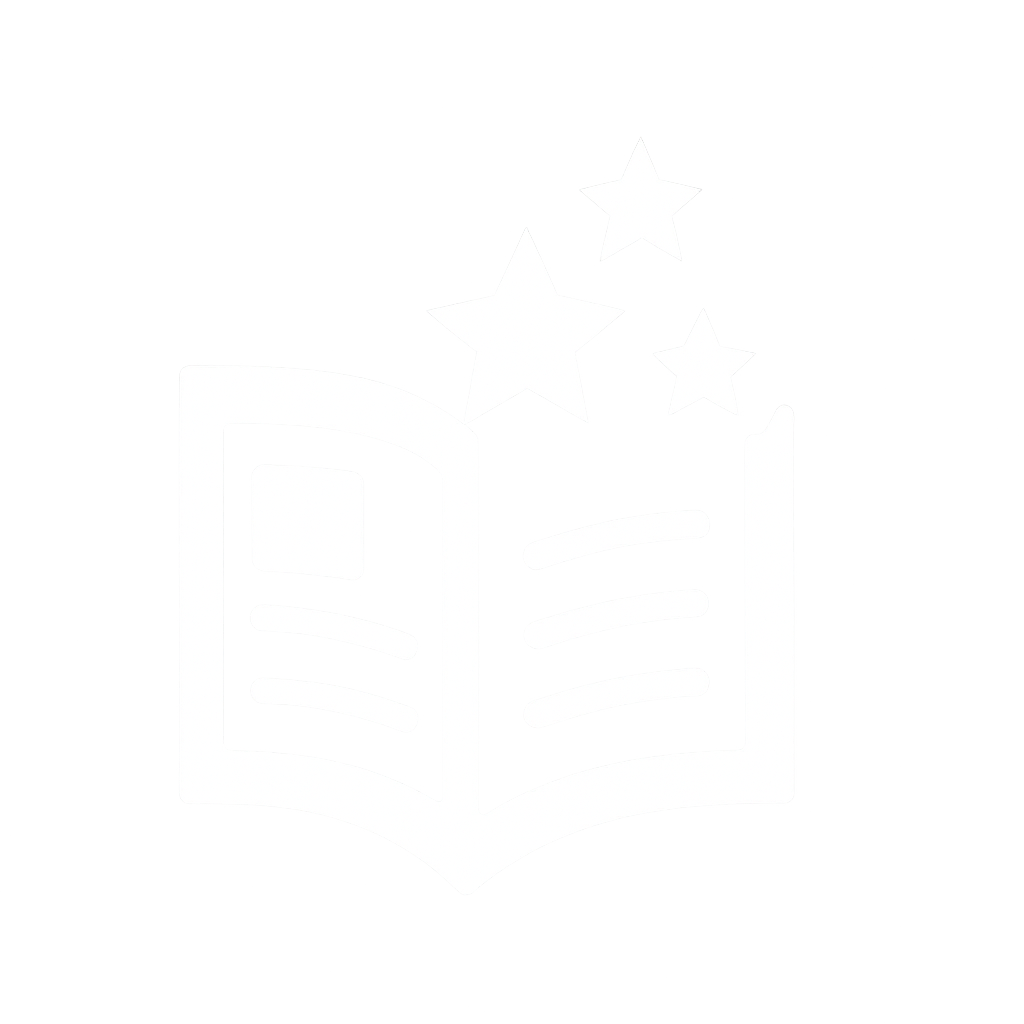増田聡
@smasuda.bsky.social
1.2K followers
73 following
510 posts
その辺によくいるタイプの量産型の人文系周縁学者。右翼です。酒と凧揚げと温泉とうどんと競馬とスケボーが好き。Twitter: @smasuda
Posts
Media
Videos
Starter Packs
増田聡
@smasuda.bsky.social
· 2d
増田聡
@smasuda.bsky.social
· 5d
増田聡
@smasuda.bsky.social
· 20d
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Sep 11
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Sep 11
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Sep 11
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Aug 25
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Aug 7
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Aug 7
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 29
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 26
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 22
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 20
Reposted by 増田聡
Shotaro Tsuda
@brighthelmer.bsky.social
· Jul 19
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 18
増田聡
@smasuda.bsky.social
· Jul 18