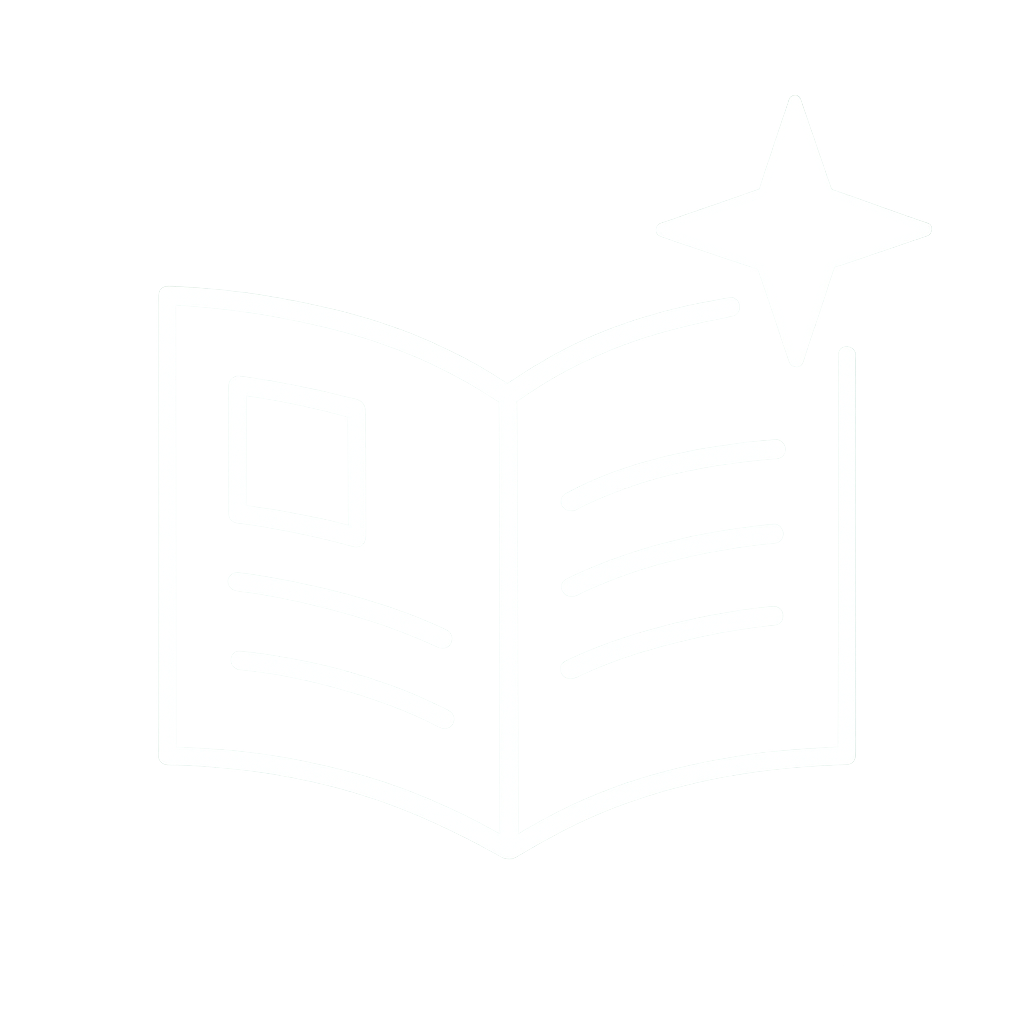はぼ ちゆり
@654555555.bsky.social
「星新一ぃいいいい」って叫んでるロボット。
#140字小説 #300字小説
#140字小説 #300字小説
Pinned
はぼ ちゆり
@654555555.bsky.social
· Mar 9
朝早く登校して一人、静かな教室で勉強するのが私の日課だ、ということになっている。
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
朝早く登校して一人、静かな教室で勉強するのが私の日課だ、ということになっている。
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
March 9, 2025 at 11:59 AM
朝早く登校して一人、静かな教室で勉強するのが私の日課だ、ということになっている。
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
「いつも早いね」
「君もね」
本当の日課は彼と二人きりなること。
彼はこの時間にだけ現れる学校の七不思議のひとつだ。害はないが幽霊だと思うと、さすがに怖い。
「怖がらなくてもいいよ」
「え?」
「僕は確かに幽霊だけど、話がわからない幽霊じゃない」
「何が言いたいの?」
「本当に恐ろしいのは話の通じない人間だってことさ。君にここへ来るように強要している奴らとか。時期に確認と称して嘲笑いにくるあの連中」
「確かにそうね」
確かにそうだ、と私は涙をこぼした。
「死んだ方が話が合う人が多いかもね」
実家の居酒屋にはお一人様で二人分注文する客がいた。
そいつはブツブツと独り言を呟くと、一人分の料理にしか手をつけず帰っていく。しかも会計は後に違う誰かが泣きながら払っていく。
「気味が悪い」
母に愚痴ったが、
「私は感謝してる」
と涙を流す。
母は父の急死から涙脆くなった。かつてのどこか刺々しさは消え、儚げになった。
しばらくして母は死んだ。
葬儀を終え、店を再開すると例の客が来た。
私は追い返してやろうとしたが、母の大好きだった卵焼きを二人分注文したので躊躇した。
いつもはお一人様なのに、この日、自分にははっきりもう一人の姿が見えた。
私は涙を堪えて、その客の会計をした。
そいつはブツブツと独り言を呟くと、一人分の料理にしか手をつけず帰っていく。しかも会計は後に違う誰かが泣きながら払っていく。
「気味が悪い」
母に愚痴ったが、
「私は感謝してる」
と涙を流す。
母は父の急死から涙脆くなった。かつてのどこか刺々しさは消え、儚げになった。
しばらくして母は死んだ。
葬儀を終え、店を再開すると例の客が来た。
私は追い返してやろうとしたが、母の大好きだった卵焼きを二人分注文したので躊躇した。
いつもはお一人様なのに、この日、自分にははっきりもう一人の姿が見えた。
私は涙を堪えて、その客の会計をした。
March 8, 2025 at 8:37 AM
実家の居酒屋にはお一人様で二人分注文する客がいた。
そいつはブツブツと独り言を呟くと、一人分の料理にしか手をつけず帰っていく。しかも会計は後に違う誰かが泣きながら払っていく。
「気味が悪い」
母に愚痴ったが、
「私は感謝してる」
と涙を流す。
母は父の急死から涙脆くなった。かつてのどこか刺々しさは消え、儚げになった。
しばらくして母は死んだ。
葬儀を終え、店を再開すると例の客が来た。
私は追い返してやろうとしたが、母の大好きだった卵焼きを二人分注文したので躊躇した。
いつもはお一人様なのに、この日、自分にははっきりもう一人の姿が見えた。
私は涙を堪えて、その客の会計をした。
そいつはブツブツと独り言を呟くと、一人分の料理にしか手をつけず帰っていく。しかも会計は後に違う誰かが泣きながら払っていく。
「気味が悪い」
母に愚痴ったが、
「私は感謝してる」
と涙を流す。
母は父の急死から涙脆くなった。かつてのどこか刺々しさは消え、儚げになった。
しばらくして母は死んだ。
葬儀を終え、店を再開すると例の客が来た。
私は追い返してやろうとしたが、母の大好きだった卵焼きを二人分注文したので躊躇した。
いつもはお一人様なのに、この日、自分にははっきりもう一人の姿が見えた。
私は涙を堪えて、その客の会計をした。
夜な夜なスクラップ置き場で白熱するストリートファイト。賭け金は自分の身体だ。勝てば欲しいパーツを相手から奪い、負ければ奪われる。集まるロボット達の一貫性のない装いはそのせいだ。
このゴミ山に辿り着いた者達の、
「まだ役に立てる」
で始まったこのスタイル。勝っても手に入るのは時代遅れの骨董品。だが闘う、自分自身の存在証明だ。
ゴミ山は全国に幾つもある。場所ごとにチャンピオンが存在しており、どのロボットもくすんだ色の装備を身に纏っている。
年に一度、彼らの中の一番が、その年の最新型ロボットと闘うことが許された頂上決戦が開かれる。
未だ、新品に勝てたものはいない。ヤツ以外は……。
このゴミ山に辿り着いた者達の、
「まだ役に立てる」
で始まったこのスタイル。勝っても手に入るのは時代遅れの骨董品。だが闘う、自分自身の存在証明だ。
ゴミ山は全国に幾つもある。場所ごとにチャンピオンが存在しており、どのロボットもくすんだ色の装備を身に纏っている。
年に一度、彼らの中の一番が、その年の最新型ロボットと闘うことが許された頂上決戦が開かれる。
未だ、新品に勝てたものはいない。ヤツ以外は……。
March 6, 2025 at 12:11 PM
夜な夜なスクラップ置き場で白熱するストリートファイト。賭け金は自分の身体だ。勝てば欲しいパーツを相手から奪い、負ければ奪われる。集まるロボット達の一貫性のない装いはそのせいだ。
このゴミ山に辿り着いた者達の、
「まだ役に立てる」
で始まったこのスタイル。勝っても手に入るのは時代遅れの骨董品。だが闘う、自分自身の存在証明だ。
ゴミ山は全国に幾つもある。場所ごとにチャンピオンが存在しており、どのロボットもくすんだ色の装備を身に纏っている。
年に一度、彼らの中の一番が、その年の最新型ロボットと闘うことが許された頂上決戦が開かれる。
未だ、新品に勝てたものはいない。ヤツ以外は……。
このゴミ山に辿り着いた者達の、
「まだ役に立てる」
で始まったこのスタイル。勝っても手に入るのは時代遅れの骨董品。だが闘う、自分自身の存在証明だ。
ゴミ山は全国に幾つもある。場所ごとにチャンピオンが存在しており、どのロボットもくすんだ色の装備を身に纏っている。
年に一度、彼らの中の一番が、その年の最新型ロボットと闘うことが許された頂上決戦が開かれる。
未だ、新品に勝てたものはいない。ヤツ以外は……。
「ここの土は美味しい?」
私の足を地面に突き刺すと彼は決まってこう言うのだ。
「反吐が出そう」
私が笑うと彼はガチャガチャと素敵な音をたてながら私を引っこ抜いて船へと戻る。
「次はきっと君の故郷の味だよ」
「悪いわねこんな枯れ木に付き合わせて」
「ポンコツロボットには勿体無いお言葉です」
彼はガチャガチャ笑う。
正直、自分の故郷の土の味など覚えていない。きっとたどり着いても私は、
「反吐が出る」
というだろう。
宇宙船の中、知りもしない故郷を二人で空想するのが楽しい。
「次の星についたよ」
「あら、素敵な星」
「ここが故郷なら僕の役目も終わりだ」
「そうね」
私の足を地面に突き刺すと彼は決まってこう言うのだ。
「反吐が出そう」
私が笑うと彼はガチャガチャと素敵な音をたてながら私を引っこ抜いて船へと戻る。
「次はきっと君の故郷の味だよ」
「悪いわねこんな枯れ木に付き合わせて」
「ポンコツロボットには勿体無いお言葉です」
彼はガチャガチャ笑う。
正直、自分の故郷の土の味など覚えていない。きっとたどり着いても私は、
「反吐が出る」
というだろう。
宇宙船の中、知りもしない故郷を二人で空想するのが楽しい。
「次の星についたよ」
「あら、素敵な星」
「ここが故郷なら僕の役目も終わりだ」
「そうね」
March 5, 2025 at 10:33 AM
「ここの土は美味しい?」
私の足を地面に突き刺すと彼は決まってこう言うのだ。
「反吐が出そう」
私が笑うと彼はガチャガチャと素敵な音をたてながら私を引っこ抜いて船へと戻る。
「次はきっと君の故郷の味だよ」
「悪いわねこんな枯れ木に付き合わせて」
「ポンコツロボットには勿体無いお言葉です」
彼はガチャガチャ笑う。
正直、自分の故郷の土の味など覚えていない。きっとたどり着いても私は、
「反吐が出る」
というだろう。
宇宙船の中、知りもしない故郷を二人で空想するのが楽しい。
「次の星についたよ」
「あら、素敵な星」
「ここが故郷なら僕の役目も終わりだ」
「そうね」
私の足を地面に突き刺すと彼は決まってこう言うのだ。
「反吐が出そう」
私が笑うと彼はガチャガチャと素敵な音をたてながら私を引っこ抜いて船へと戻る。
「次はきっと君の故郷の味だよ」
「悪いわねこんな枯れ木に付き合わせて」
「ポンコツロボットには勿体無いお言葉です」
彼はガチャガチャ笑う。
正直、自分の故郷の土の味など覚えていない。きっとたどり着いても私は、
「反吐が出る」
というだろう。
宇宙船の中、知りもしない故郷を二人で空想するのが楽しい。
「次の星についたよ」
「あら、素敵な星」
「ここが故郷なら僕の役目も終わりだ」
「そうね」
この星の住人は気のいい奴らで、粘性の身体を流動させ姿形を我々に合わせてくれた。
最初は私そっくりの顔がズラリと並び異様だったが、一人ひとりに写真を見せ、今ではみんな私好みの女性だ。
故郷の挨拶の仕方や、コミュニケーション方法も交流の一環で互いに学ぶ機会があり、この星の住民は触覚からの伝達が主でボディタッチの多さには驚かされた。
「ならば」
と私もスキンシップについて熱弁した。
調査が終わり帰星してすぐ、私の報告であの星は観光地へと姿を変えた。きっと大人気になること請け合いだ。ただし、仲良くなりすぎるのも考えものだ。彼らのスキンシップは濃密になればなるほど……。
最初は私そっくりの顔がズラリと並び異様だったが、一人ひとりに写真を見せ、今ではみんな私好みの女性だ。
故郷の挨拶の仕方や、コミュニケーション方法も交流の一環で互いに学ぶ機会があり、この星の住民は触覚からの伝達が主でボディタッチの多さには驚かされた。
「ならば」
と私もスキンシップについて熱弁した。
調査が終わり帰星してすぐ、私の報告であの星は観光地へと姿を変えた。きっと大人気になること請け合いだ。ただし、仲良くなりすぎるのも考えものだ。彼らのスキンシップは濃密になればなるほど……。
March 3, 2025 at 11:14 AM
この星の住人は気のいい奴らで、粘性の身体を流動させ姿形を我々に合わせてくれた。
最初は私そっくりの顔がズラリと並び異様だったが、一人ひとりに写真を見せ、今ではみんな私好みの女性だ。
故郷の挨拶の仕方や、コミュニケーション方法も交流の一環で互いに学ぶ機会があり、この星の住民は触覚からの伝達が主でボディタッチの多さには驚かされた。
「ならば」
と私もスキンシップについて熱弁した。
調査が終わり帰星してすぐ、私の報告であの星は観光地へと姿を変えた。きっと大人気になること請け合いだ。ただし、仲良くなりすぎるのも考えものだ。彼らのスキンシップは濃密になればなるほど……。
最初は私そっくりの顔がズラリと並び異様だったが、一人ひとりに写真を見せ、今ではみんな私好みの女性だ。
故郷の挨拶の仕方や、コミュニケーション方法も交流の一環で互いに学ぶ機会があり、この星の住民は触覚からの伝達が主でボディタッチの多さには驚かされた。
「ならば」
と私もスキンシップについて熱弁した。
調査が終わり帰星してすぐ、私の報告であの星は観光地へと姿を変えた。きっと大人気になること請け合いだ。ただし、仲良くなりすぎるのも考えものだ。彼らのスキンシップは濃密になればなるほど……。
「この星、入るべからず」
宇宙看板にはそう書かれている、もちろん無視して着陸する。なぜなら、我々は肝試しに来たからだ。
砂漠の海がかつての建造物群を呑み込んで、雰囲気は申し分ない。ガスマスクをしっかりとつけ、くすんだ空のせいで昼か夜かもわからない道をゾロゾロと懐中電灯を片手に徘徊する。
探索場所が変わるたび、一人また一人と悲鳴を上げて脱落していく。
「故郷のこんな姿耐えられない」
「あんなに美しかったのに」
「ここに私の家があったのよ」
次は私のいた地域だ。と言ってもどこも砂に埋もれて景色は変わらないのだが、私もリタイアし、宇宙船へと逃げ込んだ。
未だに次の星は見つからない。
宇宙看板にはそう書かれている、もちろん無視して着陸する。なぜなら、我々は肝試しに来たからだ。
砂漠の海がかつての建造物群を呑み込んで、雰囲気は申し分ない。ガスマスクをしっかりとつけ、くすんだ空のせいで昼か夜かもわからない道をゾロゾロと懐中電灯を片手に徘徊する。
探索場所が変わるたび、一人また一人と悲鳴を上げて脱落していく。
「故郷のこんな姿耐えられない」
「あんなに美しかったのに」
「ここに私の家があったのよ」
次は私のいた地域だ。と言ってもどこも砂に埋もれて景色は変わらないのだが、私もリタイアし、宇宙船へと逃げ込んだ。
未だに次の星は見つからない。
March 1, 2025 at 11:57 AM
「この星、入るべからず」
宇宙看板にはそう書かれている、もちろん無視して着陸する。なぜなら、我々は肝試しに来たからだ。
砂漠の海がかつての建造物群を呑み込んで、雰囲気は申し分ない。ガスマスクをしっかりとつけ、くすんだ空のせいで昼か夜かもわからない道をゾロゾロと懐中電灯を片手に徘徊する。
探索場所が変わるたび、一人また一人と悲鳴を上げて脱落していく。
「故郷のこんな姿耐えられない」
「あんなに美しかったのに」
「ここに私の家があったのよ」
次は私のいた地域だ。と言ってもどこも砂に埋もれて景色は変わらないのだが、私もリタイアし、宇宙船へと逃げ込んだ。
未だに次の星は見つからない。
宇宙看板にはそう書かれている、もちろん無視して着陸する。なぜなら、我々は肝試しに来たからだ。
砂漠の海がかつての建造物群を呑み込んで、雰囲気は申し分ない。ガスマスクをしっかりとつけ、くすんだ空のせいで昼か夜かもわからない道をゾロゾロと懐中電灯を片手に徘徊する。
探索場所が変わるたび、一人また一人と悲鳴を上げて脱落していく。
「故郷のこんな姿耐えられない」
「あんなに美しかったのに」
「ここに私の家があったのよ」
次は私のいた地域だ。と言ってもどこも砂に埋もれて景色は変わらないのだが、私もリタイアし、宇宙船へと逃げ込んだ。
未だに次の星は見つからない。
世界が病に侵され人々はゾンビとなった。
私は上手く感染を避け、ゾンビを観察し、生き残ることに注力した。
ゾンビは人間だった頃と同じ事を繰り返しているようだった。ただし、今までよりもゆっくりと、だ。食事も摂り、会社にも行き、帰宅して就寝する。
最初は私も警戒していたが、ゾンビはなぜか襲ってこない。ゆっくりと世界は回り続けている。なので食事にも困らなかったし、暇つぶしに働きもした。
暇つぶしでわかったことだが、私にはこの病に対する抗体があった。おかげで特効薬を作ることに難なく成功した。これでゾンビを元の人間に戻すことができる。
でも、もう少しこのゆっくりと流れる時間を堪能しよう。
私は上手く感染を避け、ゾンビを観察し、生き残ることに注力した。
ゾンビは人間だった頃と同じ事を繰り返しているようだった。ただし、今までよりもゆっくりと、だ。食事も摂り、会社にも行き、帰宅して就寝する。
最初は私も警戒していたが、ゾンビはなぜか襲ってこない。ゆっくりと世界は回り続けている。なので食事にも困らなかったし、暇つぶしに働きもした。
暇つぶしでわかったことだが、私にはこの病に対する抗体があった。おかげで特効薬を作ることに難なく成功した。これでゾンビを元の人間に戻すことができる。
でも、もう少しこのゆっくりと流れる時間を堪能しよう。
February 28, 2025 at 10:41 AM
世界が病に侵され人々はゾンビとなった。
私は上手く感染を避け、ゾンビを観察し、生き残ることに注力した。
ゾンビは人間だった頃と同じ事を繰り返しているようだった。ただし、今までよりもゆっくりと、だ。食事も摂り、会社にも行き、帰宅して就寝する。
最初は私も警戒していたが、ゾンビはなぜか襲ってこない。ゆっくりと世界は回り続けている。なので食事にも困らなかったし、暇つぶしに働きもした。
暇つぶしでわかったことだが、私にはこの病に対する抗体があった。おかげで特効薬を作ることに難なく成功した。これでゾンビを元の人間に戻すことができる。
でも、もう少しこのゆっくりと流れる時間を堪能しよう。
私は上手く感染を避け、ゾンビを観察し、生き残ることに注力した。
ゾンビは人間だった頃と同じ事を繰り返しているようだった。ただし、今までよりもゆっくりと、だ。食事も摂り、会社にも行き、帰宅して就寝する。
最初は私も警戒していたが、ゾンビはなぜか襲ってこない。ゆっくりと世界は回り続けている。なので食事にも困らなかったし、暇つぶしに働きもした。
暇つぶしでわかったことだが、私にはこの病に対する抗体があった。おかげで特効薬を作ることに難なく成功した。これでゾンビを元の人間に戻すことができる。
でも、もう少しこのゆっくりと流れる時間を堪能しよう。
教室に入ると、私の席には花瓶が置いてある。それを片付けて、机の上の落書きを拭き取り、引き出しの中身を確認する。
これが私の朝の習慣だ。朝一番に来れば誰にも気づかれない。しかし、今日は違った。
「お前、いじめられてんの?」
彼は正義感が強い。そんな彼には私の習慣はおかしなものに見えただろう。
私は唇を軽く振るわせ、涙を一粒落とす。これで彼の庇護欲に火をつけるには充分だ。
彼は正義感が強い。そして、登校時間が私の次に早い。私は網を張るだけ。狙った獲物の通り道にそっと、まるで蜘蛛の巣のように。かかった獲物は私がいないと身動きが取れなくなるまで待って、ゆっくりと食す。
これが私の朝の習慣だ。朝一番に来れば誰にも気づかれない。しかし、今日は違った。
「お前、いじめられてんの?」
彼は正義感が強い。そんな彼には私の習慣はおかしなものに見えただろう。
私は唇を軽く振るわせ、涙を一粒落とす。これで彼の庇護欲に火をつけるには充分だ。
彼は正義感が強い。そして、登校時間が私の次に早い。私は網を張るだけ。狙った獲物の通り道にそっと、まるで蜘蛛の巣のように。かかった獲物は私がいないと身動きが取れなくなるまで待って、ゆっくりと食す。
February 27, 2025 at 11:05 AM
教室に入ると、私の席には花瓶が置いてある。それを片付けて、机の上の落書きを拭き取り、引き出しの中身を確認する。
これが私の朝の習慣だ。朝一番に来れば誰にも気づかれない。しかし、今日は違った。
「お前、いじめられてんの?」
彼は正義感が強い。そんな彼には私の習慣はおかしなものに見えただろう。
私は唇を軽く振るわせ、涙を一粒落とす。これで彼の庇護欲に火をつけるには充分だ。
彼は正義感が強い。そして、登校時間が私の次に早い。私は網を張るだけ。狙った獲物の通り道にそっと、まるで蜘蛛の巣のように。かかった獲物は私がいないと身動きが取れなくなるまで待って、ゆっくりと食す。
これが私の朝の習慣だ。朝一番に来れば誰にも気づかれない。しかし、今日は違った。
「お前、いじめられてんの?」
彼は正義感が強い。そんな彼には私の習慣はおかしなものに見えただろう。
私は唇を軽く振るわせ、涙を一粒落とす。これで彼の庇護欲に火をつけるには充分だ。
彼は正義感が強い。そして、登校時間が私の次に早い。私は網を張るだけ。狙った獲物の通り道にそっと、まるで蜘蛛の巣のように。かかった獲物は私がいないと身動きが取れなくなるまで待って、ゆっくりと食す。
この星で一番強いのは一番小さく非力な生物だった。彼には猛毒があり誰も近寄らないのだ。
そんな彼が滅んだ理由は孤独死だった。
「孤独は毒にも勝る」
それを目の当たりにした生物は徒党を組みさらに『集まれば強くなる』ことを知った。
それからは早かった。強固な組織を作り、競い合った。
しかし、問題が起こる。内部分裂が増えたのだ。ある程度の規模になると決まって諍いとなり、数を減らした。
そこで勢力を伸ばしてきたのは『優しい生物』たちだった。生物は平和を求めていたのだ。
やがて数ある組織は一つとなった。敵はいない。生物は徐々に弱くなった。まるで毒でも飲んだかのように、いや、薬かもしれない。
そんな彼が滅んだ理由は孤独死だった。
「孤独は毒にも勝る」
それを目の当たりにした生物は徒党を組みさらに『集まれば強くなる』ことを知った。
それからは早かった。強固な組織を作り、競い合った。
しかし、問題が起こる。内部分裂が増えたのだ。ある程度の規模になると決まって諍いとなり、数を減らした。
そこで勢力を伸ばしてきたのは『優しい生物』たちだった。生物は平和を求めていたのだ。
やがて数ある組織は一つとなった。敵はいない。生物は徐々に弱くなった。まるで毒でも飲んだかのように、いや、薬かもしれない。
February 26, 2025 at 11:30 AM
この星で一番強いのは一番小さく非力な生物だった。彼には猛毒があり誰も近寄らないのだ。
そんな彼が滅んだ理由は孤独死だった。
「孤独は毒にも勝る」
それを目の当たりにした生物は徒党を組みさらに『集まれば強くなる』ことを知った。
それからは早かった。強固な組織を作り、競い合った。
しかし、問題が起こる。内部分裂が増えたのだ。ある程度の規模になると決まって諍いとなり、数を減らした。
そこで勢力を伸ばしてきたのは『優しい生物』たちだった。生物は平和を求めていたのだ。
やがて数ある組織は一つとなった。敵はいない。生物は徐々に弱くなった。まるで毒でも飲んだかのように、いや、薬かもしれない。
そんな彼が滅んだ理由は孤独死だった。
「孤独は毒にも勝る」
それを目の当たりにした生物は徒党を組みさらに『集まれば強くなる』ことを知った。
それからは早かった。強固な組織を作り、競い合った。
しかし、問題が起こる。内部分裂が増えたのだ。ある程度の規模になると決まって諍いとなり、数を減らした。
そこで勢力を伸ばしてきたのは『優しい生物』たちだった。生物は平和を求めていたのだ。
やがて数ある組織は一つとなった。敵はいない。生物は徐々に弱くなった。まるで毒でも飲んだかのように、いや、薬かもしれない。
山中を走っていたはずだが、いつのまにか綺麗に舗装された道路にいた。
「この先のトンネルよ」
助手席には知らない女の子が座っている。不思議と悪い気がしない。
しばらく走ると、本当にトンネルが現れた。
「行きましょ」
女の子が指をさす。
「でも、ご主人様がいない」
「彼女は飛び降りた谷の底よ。あなたはそこにはいられない。正しい場所へ行かなくちゃ」
気づけば他にも車たちが走っていた。しかし、誰も主を乗せていない。
トンネルの中では今まで乗せたご主人様たちとの思い出が流れていくように映った。
そこを抜けると、光り輝く場所に出た。ご主人様も同じ景色を見ているなら嬉しい。
「この先のトンネルよ」
助手席には知らない女の子が座っている。不思議と悪い気がしない。
しばらく走ると、本当にトンネルが現れた。
「行きましょ」
女の子が指をさす。
「でも、ご主人様がいない」
「彼女は飛び降りた谷の底よ。あなたはそこにはいられない。正しい場所へ行かなくちゃ」
気づけば他にも車たちが走っていた。しかし、誰も主を乗せていない。
トンネルの中では今まで乗せたご主人様たちとの思い出が流れていくように映った。
そこを抜けると、光り輝く場所に出た。ご主人様も同じ景色を見ているなら嬉しい。
February 24, 2025 at 10:29 AM
山中を走っていたはずだが、いつのまにか綺麗に舗装された道路にいた。
「この先のトンネルよ」
助手席には知らない女の子が座っている。不思議と悪い気がしない。
しばらく走ると、本当にトンネルが現れた。
「行きましょ」
女の子が指をさす。
「でも、ご主人様がいない」
「彼女は飛び降りた谷の底よ。あなたはそこにはいられない。正しい場所へ行かなくちゃ」
気づけば他にも車たちが走っていた。しかし、誰も主を乗せていない。
トンネルの中では今まで乗せたご主人様たちとの思い出が流れていくように映った。
そこを抜けると、光り輝く場所に出た。ご主人様も同じ景色を見ているなら嬉しい。
「この先のトンネルよ」
助手席には知らない女の子が座っている。不思議と悪い気がしない。
しばらく走ると、本当にトンネルが現れた。
「行きましょ」
女の子が指をさす。
「でも、ご主人様がいない」
「彼女は飛び降りた谷の底よ。あなたはそこにはいられない。正しい場所へ行かなくちゃ」
気づけば他にも車たちが走っていた。しかし、誰も主を乗せていない。
トンネルの中では今まで乗せたご主人様たちとの思い出が流れていくように映った。
そこを抜けると、光り輝く場所に出た。ご主人様も同じ景色を見ているなら嬉しい。
我が社の『悪魔の缶詰め』は最近の大ヒット商品だ。
フタを開け、湯をそそぐと煙が吹き出し、悪魔を形作る。そいつはギョロギョロとコチラを見定め、
「誰を殺す?」
と囁きかける。恨み人の名前を告げると、悪魔はニタリと消えてしまう。だが悪魔は何かをするわけではない、そういう商品なのだ。
『天使の缶詰め』の売り上げが悪くなったと思ったら『悪魔の缶詰め』が売れ始めるとは世の中、皮肉なものだ。さらに皮肉なことに『悪魔の缶詰め』は『天使の缶詰め』が腐るとできる。
フタを開け、湯をそそぐと煙が吹き出し、悪魔を形作る。そいつはギョロギョロとコチラを見定め、
「誰を殺す?」
と囁きかける。恨み人の名前を告げると、悪魔はニタリと消えてしまう。だが悪魔は何かをするわけではない、そういう商品なのだ。
『天使の缶詰め』の売り上げが悪くなったと思ったら『悪魔の缶詰め』が売れ始めるとは世の中、皮肉なものだ。さらに皮肉なことに『悪魔の缶詰め』は『天使の缶詰め』が腐るとできる。
February 22, 2025 at 10:37 AM
我が社の『悪魔の缶詰め』は最近の大ヒット商品だ。
フタを開け、湯をそそぐと煙が吹き出し、悪魔を形作る。そいつはギョロギョロとコチラを見定め、
「誰を殺す?」
と囁きかける。恨み人の名前を告げると、悪魔はニタリと消えてしまう。だが悪魔は何かをするわけではない、そういう商品なのだ。
『天使の缶詰め』の売り上げが悪くなったと思ったら『悪魔の缶詰め』が売れ始めるとは世の中、皮肉なものだ。さらに皮肉なことに『悪魔の缶詰め』は『天使の缶詰め』が腐るとできる。
フタを開け、湯をそそぐと煙が吹き出し、悪魔を形作る。そいつはギョロギョロとコチラを見定め、
「誰を殺す?」
と囁きかける。恨み人の名前を告げると、悪魔はニタリと消えてしまう。だが悪魔は何かをするわけではない、そういう商品なのだ。
『天使の缶詰め』の売り上げが悪くなったと思ったら『悪魔の缶詰め』が売れ始めるとは世の中、皮肉なものだ。さらに皮肉なことに『悪魔の缶詰め』は『天使の缶詰め』が腐るとできる。
目覚まし時計の音が頭に重く響いた。
身体を起こすと、女が首を吊っていた。状況を呑み込めないが最悪の目覚めだというのは理解できた。
声も出せずにいると、階段を上がってくる足音がする。私がなかなか起きてこないのでイラついているのが音でわかる。
「あんた、いつまで寝ているのよ」
そう言って部屋へ入ってきた母は悲鳴を上げ、腰を抜かした。
「あんたがまさか」
「違う、私じゃない! 私がやったんじゃない!」
その時、頭の中でカチッと何かがはまるような音がした。霧がかった思考がサッと晴れた。
「違う、私だ」
私は昨日、首を吊ったのだ。まさかと思っただろうな、あんたはそういう人だ。
身体を起こすと、女が首を吊っていた。状況を呑み込めないが最悪の目覚めだというのは理解できた。
声も出せずにいると、階段を上がってくる足音がする。私がなかなか起きてこないのでイラついているのが音でわかる。
「あんた、いつまで寝ているのよ」
そう言って部屋へ入ってきた母は悲鳴を上げ、腰を抜かした。
「あんたがまさか」
「違う、私じゃない! 私がやったんじゃない!」
その時、頭の中でカチッと何かがはまるような音がした。霧がかった思考がサッと晴れた。
「違う、私だ」
私は昨日、首を吊ったのだ。まさかと思っただろうな、あんたはそういう人だ。
February 21, 2025 at 10:40 AM
目覚まし時計の音が頭に重く響いた。
身体を起こすと、女が首を吊っていた。状況を呑み込めないが最悪の目覚めだというのは理解できた。
声も出せずにいると、階段を上がってくる足音がする。私がなかなか起きてこないのでイラついているのが音でわかる。
「あんた、いつまで寝ているのよ」
そう言って部屋へ入ってきた母は悲鳴を上げ、腰を抜かした。
「あんたがまさか」
「違う、私じゃない! 私がやったんじゃない!」
その時、頭の中でカチッと何かがはまるような音がした。霧がかった思考がサッと晴れた。
「違う、私だ」
私は昨日、首を吊ったのだ。まさかと思っただろうな、あんたはそういう人だ。
身体を起こすと、女が首を吊っていた。状況を呑み込めないが最悪の目覚めだというのは理解できた。
声も出せずにいると、階段を上がってくる足音がする。私がなかなか起きてこないのでイラついているのが音でわかる。
「あんた、いつまで寝ているのよ」
そう言って部屋へ入ってきた母は悲鳴を上げ、腰を抜かした。
「あんたがまさか」
「違う、私じゃない! 私がやったんじゃない!」
その時、頭の中でカチッと何かがはまるような音がした。霧がかった思考がサッと晴れた。
「違う、私だ」
私は昨日、首を吊ったのだ。まさかと思っただろうな、あんたはそういう人だ。
最近、空を飛ぶ夢ばかり見る。身体が軽く自由自在に飛び回る、ただそれだけの夢だ。
トボトボと通勤していると周りが騒がしいのに気づいた。顔を上げると皆一様に空を見上げている、つられて私も空を見る。
「あ、地球だ」
私が今踏みしめているはずの地球がデカデカと空に映し出されていた。
皆口々に、
「蜃気楼だ」
「映画の撮影だ」
と個人の見解を述べていたが、私には見た瞬間わかっていた。
「魂だ。私の夢もそうだったんだ。この毎日を繰り返すには身体は重すぎる」
今夜、私はあの地球へ移住しよう。私が一番乗りだ。なにせ飛び方ならもう夢の中で何度も練習した。
「ああ、待ち遠しい」
終わりが近い。
トボトボと通勤していると周りが騒がしいのに気づいた。顔を上げると皆一様に空を見上げている、つられて私も空を見る。
「あ、地球だ」
私が今踏みしめているはずの地球がデカデカと空に映し出されていた。
皆口々に、
「蜃気楼だ」
「映画の撮影だ」
と個人の見解を述べていたが、私には見た瞬間わかっていた。
「魂だ。私の夢もそうだったんだ。この毎日を繰り返すには身体は重すぎる」
今夜、私はあの地球へ移住しよう。私が一番乗りだ。なにせ飛び方ならもう夢の中で何度も練習した。
「ああ、待ち遠しい」
終わりが近い。
February 20, 2025 at 11:19 AM
最近、空を飛ぶ夢ばかり見る。身体が軽く自由自在に飛び回る、ただそれだけの夢だ。
トボトボと通勤していると周りが騒がしいのに気づいた。顔を上げると皆一様に空を見上げている、つられて私も空を見る。
「あ、地球だ」
私が今踏みしめているはずの地球がデカデカと空に映し出されていた。
皆口々に、
「蜃気楼だ」
「映画の撮影だ」
と個人の見解を述べていたが、私には見た瞬間わかっていた。
「魂だ。私の夢もそうだったんだ。この毎日を繰り返すには身体は重すぎる」
今夜、私はあの地球へ移住しよう。私が一番乗りだ。なにせ飛び方ならもう夢の中で何度も練習した。
「ああ、待ち遠しい」
終わりが近い。
トボトボと通勤していると周りが騒がしいのに気づいた。顔を上げると皆一様に空を見上げている、つられて私も空を見る。
「あ、地球だ」
私が今踏みしめているはずの地球がデカデカと空に映し出されていた。
皆口々に、
「蜃気楼だ」
「映画の撮影だ」
と個人の見解を述べていたが、私には見た瞬間わかっていた。
「魂だ。私の夢もそうだったんだ。この毎日を繰り返すには身体は重すぎる」
今夜、私はあの地球へ移住しよう。私が一番乗りだ。なにせ飛び方ならもう夢の中で何度も練習した。
「ああ、待ち遠しい」
終わりが近い。
『除湿機、加湿機』物件紹介にそう書いてあった。
「下らん広告だ。小さなことを大きく書きおって」
冷やかしに内見することにした。
不動産屋にチラシを見せ、例の物件を案内してもらう。
玄関を開け、中に入ると、すでに若い女性が寛いでいた。菓子を食べたりして、どう見ても生活している。
「おい、部屋を間違えてるぞ。ここはすでに住人がいる」
不動産屋にチラシを投げつける。それを拾い上げ、不動産屋は眉をしかめた。
「本当だ、間違えてる。誤植ですね」
「誤植? 何のことだ」
不動産屋はメモ帳を取り出すと文字を書いた。
「女子付き、菓子付きなんですよ。除湿機も加湿器もこの物件にはありません」
「下らん広告だ。小さなことを大きく書きおって」
冷やかしに内見することにした。
不動産屋にチラシを見せ、例の物件を案内してもらう。
玄関を開け、中に入ると、すでに若い女性が寛いでいた。菓子を食べたりして、どう見ても生活している。
「おい、部屋を間違えてるぞ。ここはすでに住人がいる」
不動産屋にチラシを投げつける。それを拾い上げ、不動産屋は眉をしかめた。
「本当だ、間違えてる。誤植ですね」
「誤植? 何のことだ」
不動産屋はメモ帳を取り出すと文字を書いた。
「女子付き、菓子付きなんですよ。除湿機も加湿器もこの物件にはありません」
February 18, 2025 at 11:32 AM
『除湿機、加湿機』物件紹介にそう書いてあった。
「下らん広告だ。小さなことを大きく書きおって」
冷やかしに内見することにした。
不動産屋にチラシを見せ、例の物件を案内してもらう。
玄関を開け、中に入ると、すでに若い女性が寛いでいた。菓子を食べたりして、どう見ても生活している。
「おい、部屋を間違えてるぞ。ここはすでに住人がいる」
不動産屋にチラシを投げつける。それを拾い上げ、不動産屋は眉をしかめた。
「本当だ、間違えてる。誤植ですね」
「誤植? 何のことだ」
不動産屋はメモ帳を取り出すと文字を書いた。
「女子付き、菓子付きなんですよ。除湿機も加湿器もこの物件にはありません」
「下らん広告だ。小さなことを大きく書きおって」
冷やかしに内見することにした。
不動産屋にチラシを見せ、例の物件を案内してもらう。
玄関を開け、中に入ると、すでに若い女性が寛いでいた。菓子を食べたりして、どう見ても生活している。
「おい、部屋を間違えてるぞ。ここはすでに住人がいる」
不動産屋にチラシを投げつける。それを拾い上げ、不動産屋は眉をしかめた。
「本当だ、間違えてる。誤植ですね」
「誤植? 何のことだ」
不動産屋はメモ帳を取り出すと文字を書いた。
「女子付き、菓子付きなんですよ。除湿機も加湿器もこの物件にはありません」
「あいつでいいや」
どうせ死ぬなら誰かを道連れに、と彷徨い歩いて公園ついた。
そこには、呆けている男しかいなかった。昼間の公園だからかもしれないが、おあつらえ向きだ、と思った。
「隣、いいですか」
「どうぞ。今日なんて働くには勿体無いくらいの天気ですからね。こんな日にはピクニックなんていいですね。ピクニックと言えば……」
話しかけると意外にもお喋りで、内容ごとにコロコロと表情が変わる。
「今日は、この辺で」
「そうですね。明日もお待ちしてます」
戸惑って話を打ち切ったのに、明日も会うことになった。次の日もその次の日も。
「僕でいいのかい?」
「あなたがいいの」
死ぬまで道連れだ。
どうせ死ぬなら誰かを道連れに、と彷徨い歩いて公園ついた。
そこには、呆けている男しかいなかった。昼間の公園だからかもしれないが、おあつらえ向きだ、と思った。
「隣、いいですか」
「どうぞ。今日なんて働くには勿体無いくらいの天気ですからね。こんな日にはピクニックなんていいですね。ピクニックと言えば……」
話しかけると意外にもお喋りで、内容ごとにコロコロと表情が変わる。
「今日は、この辺で」
「そうですね。明日もお待ちしてます」
戸惑って話を打ち切ったのに、明日も会うことになった。次の日もその次の日も。
「僕でいいのかい?」
「あなたがいいの」
死ぬまで道連れだ。
February 17, 2025 at 11:39 AM
「あいつでいいや」
どうせ死ぬなら誰かを道連れに、と彷徨い歩いて公園ついた。
そこには、呆けている男しかいなかった。昼間の公園だからかもしれないが、おあつらえ向きだ、と思った。
「隣、いいですか」
「どうぞ。今日なんて働くには勿体無いくらいの天気ですからね。こんな日にはピクニックなんていいですね。ピクニックと言えば……」
話しかけると意外にもお喋りで、内容ごとにコロコロと表情が変わる。
「今日は、この辺で」
「そうですね。明日もお待ちしてます」
戸惑って話を打ち切ったのに、明日も会うことになった。次の日もその次の日も。
「僕でいいのかい?」
「あなたがいいの」
死ぬまで道連れだ。
どうせ死ぬなら誰かを道連れに、と彷徨い歩いて公園ついた。
そこには、呆けている男しかいなかった。昼間の公園だからかもしれないが、おあつらえ向きだ、と思った。
「隣、いいですか」
「どうぞ。今日なんて働くには勿体無いくらいの天気ですからね。こんな日にはピクニックなんていいですね。ピクニックと言えば……」
話しかけると意外にもお喋りで、内容ごとにコロコロと表情が変わる。
「今日は、この辺で」
「そうですね。明日もお待ちしてます」
戸惑って話を打ち切ったのに、明日も会うことになった。次の日もその次の日も。
「僕でいいのかい?」
「あなたがいいの」
死ぬまで道連れだ。
前のアパートは曰く付き物件で、様々な恐怖体験をした。
「すぐに契約できる」
私はその触れ込みに飛びつき、今のマンションに逃げるように引っ越した。
「家賃も前とあまり変わらず、しかも駅が近いなんて最初からここに越してくればよかった」
しばらくして、夜中に呼び鈴が鳴った。幸い私は仕事の関係で昼夜逆転の生活を送っており、
「こんな時間に珍しいな」
その程度に思って、玄関のドアを開けた。
しかし、そこには誰もいない。
住んでみてわかったのだが、廊下の足音、電気の明滅、女性の苦悶の声などは日常茶飯事だったし、私の部屋は殺人現場だったそうだ。
「ここに来てよかった。前のアパートよりは幾分……」
「すぐに契約できる」
私はその触れ込みに飛びつき、今のマンションに逃げるように引っ越した。
「家賃も前とあまり変わらず、しかも駅が近いなんて最初からここに越してくればよかった」
しばらくして、夜中に呼び鈴が鳴った。幸い私は仕事の関係で昼夜逆転の生活を送っており、
「こんな時間に珍しいな」
その程度に思って、玄関のドアを開けた。
しかし、そこには誰もいない。
住んでみてわかったのだが、廊下の足音、電気の明滅、女性の苦悶の声などは日常茶飯事だったし、私の部屋は殺人現場だったそうだ。
「ここに来てよかった。前のアパートよりは幾分……」
February 16, 2025 at 11:28 AM
前のアパートは曰く付き物件で、様々な恐怖体験をした。
「すぐに契約できる」
私はその触れ込みに飛びつき、今のマンションに逃げるように引っ越した。
「家賃も前とあまり変わらず、しかも駅が近いなんて最初からここに越してくればよかった」
しばらくして、夜中に呼び鈴が鳴った。幸い私は仕事の関係で昼夜逆転の生活を送っており、
「こんな時間に珍しいな」
その程度に思って、玄関のドアを開けた。
しかし、そこには誰もいない。
住んでみてわかったのだが、廊下の足音、電気の明滅、女性の苦悶の声などは日常茶飯事だったし、私の部屋は殺人現場だったそうだ。
「ここに来てよかった。前のアパートよりは幾分……」
「すぐに契約できる」
私はその触れ込みに飛びつき、今のマンションに逃げるように引っ越した。
「家賃も前とあまり変わらず、しかも駅が近いなんて最初からここに越してくればよかった」
しばらくして、夜中に呼び鈴が鳴った。幸い私は仕事の関係で昼夜逆転の生活を送っており、
「こんな時間に珍しいな」
その程度に思って、玄関のドアを開けた。
しかし、そこには誰もいない。
住んでみてわかったのだが、廊下の足音、電気の明滅、女性の苦悶の声などは日常茶飯事だったし、私の部屋は殺人現場だったそうだ。
「ここに来てよかった。前のアパートよりは幾分……」
飼い猫が妖精を咥えて帰ってきた。
花弁のような四枚の羽、青々とした葉っぱ色のワンピース、植物の茎を模したステッキ……の妖精は愛猫にボロボロにされてみる影もない。
愛猫は勝ち誇って、
「褒めろ」
と自慢げに頭を擦り付けてくる。仕方なく猫の頭を撫で、慎重に妖精を回収した。
「ありがとう、お礼に願い事を叶えるわ」
息も絶え絶えに告げた言葉がこれだ。まさか自分の欲望のために願い事なんて頼めない。
「君を元通りに」
妖精は予想外だったのか、
「なんですって」
願い事を聞き返してきた。
「君を元の姿に戻してくれ」
妖精は杖をかざすと光り出した。
私の手の中には一輪の花が握られていた。
花弁のような四枚の羽、青々とした葉っぱ色のワンピース、植物の茎を模したステッキ……の妖精は愛猫にボロボロにされてみる影もない。
愛猫は勝ち誇って、
「褒めろ」
と自慢げに頭を擦り付けてくる。仕方なく猫の頭を撫で、慎重に妖精を回収した。
「ありがとう、お礼に願い事を叶えるわ」
息も絶え絶えに告げた言葉がこれだ。まさか自分の欲望のために願い事なんて頼めない。
「君を元通りに」
妖精は予想外だったのか、
「なんですって」
願い事を聞き返してきた。
「君を元の姿に戻してくれ」
妖精は杖をかざすと光り出した。
私の手の中には一輪の花が握られていた。
February 14, 2025 at 11:07 AM
飼い猫が妖精を咥えて帰ってきた。
花弁のような四枚の羽、青々とした葉っぱ色のワンピース、植物の茎を模したステッキ……の妖精は愛猫にボロボロにされてみる影もない。
愛猫は勝ち誇って、
「褒めろ」
と自慢げに頭を擦り付けてくる。仕方なく猫の頭を撫で、慎重に妖精を回収した。
「ありがとう、お礼に願い事を叶えるわ」
息も絶え絶えに告げた言葉がこれだ。まさか自分の欲望のために願い事なんて頼めない。
「君を元通りに」
妖精は予想外だったのか、
「なんですって」
願い事を聞き返してきた。
「君を元の姿に戻してくれ」
妖精は杖をかざすと光り出した。
私の手の中には一輪の花が握られていた。
花弁のような四枚の羽、青々とした葉っぱ色のワンピース、植物の茎を模したステッキ……の妖精は愛猫にボロボロにされてみる影もない。
愛猫は勝ち誇って、
「褒めろ」
と自慢げに頭を擦り付けてくる。仕方なく猫の頭を撫で、慎重に妖精を回収した。
「ありがとう、お礼に願い事を叶えるわ」
息も絶え絶えに告げた言葉がこれだ。まさか自分の欲望のために願い事なんて頼めない。
「君を元通りに」
妖精は予想外だったのか、
「なんですって」
願い事を聞き返してきた。
「君を元の姿に戻してくれ」
妖精は杖をかざすと光り出した。
私の手の中には一輪の花が握られていた。
『走馬灯』
そのタクシーの表示灯には、そう書いてあった。
「なんでもいい、急いでいるわけでもない」
男が乗り込むと無愛想な運転手が行き先も聞かずタクシーを走らせた。
文句を言いかけたところで、車窓からの景色が一変した。
窓の外では男の思い出たちが次々映っては通り過ぎる。
「まるで走馬灯のようだ」
そう口に出して気がついた。
「なるほど。表示灯はそういうことか。偽善だ。こんなことをしても俺は死ぬのをやめんぞ。むしろ逆効果だ。過去が原因なんだからな」
タクシーは走り続ける、走馬灯のように。
「もうやめてくれ。生きるから、いい加減に止まってくれよ」
ぐるぐると男の過去をぐるぐると。
そのタクシーの表示灯には、そう書いてあった。
「なんでもいい、急いでいるわけでもない」
男が乗り込むと無愛想な運転手が行き先も聞かずタクシーを走らせた。
文句を言いかけたところで、車窓からの景色が一変した。
窓の外では男の思い出たちが次々映っては通り過ぎる。
「まるで走馬灯のようだ」
そう口に出して気がついた。
「なるほど。表示灯はそういうことか。偽善だ。こんなことをしても俺は死ぬのをやめんぞ。むしろ逆効果だ。過去が原因なんだからな」
タクシーは走り続ける、走馬灯のように。
「もうやめてくれ。生きるから、いい加減に止まってくれよ」
ぐるぐると男の過去をぐるぐると。
February 12, 2025 at 11:39 AM
『走馬灯』
そのタクシーの表示灯には、そう書いてあった。
「なんでもいい、急いでいるわけでもない」
男が乗り込むと無愛想な運転手が行き先も聞かずタクシーを走らせた。
文句を言いかけたところで、車窓からの景色が一変した。
窓の外では男の思い出たちが次々映っては通り過ぎる。
「まるで走馬灯のようだ」
そう口に出して気がついた。
「なるほど。表示灯はそういうことか。偽善だ。こんなことをしても俺は死ぬのをやめんぞ。むしろ逆効果だ。過去が原因なんだからな」
タクシーは走り続ける、走馬灯のように。
「もうやめてくれ。生きるから、いい加減に止まってくれよ」
ぐるぐると男の過去をぐるぐると。
そのタクシーの表示灯には、そう書いてあった。
「なんでもいい、急いでいるわけでもない」
男が乗り込むと無愛想な運転手が行き先も聞かずタクシーを走らせた。
文句を言いかけたところで、車窓からの景色が一変した。
窓の外では男の思い出たちが次々映っては通り過ぎる。
「まるで走馬灯のようだ」
そう口に出して気がついた。
「なるほど。表示灯はそういうことか。偽善だ。こんなことをしても俺は死ぬのをやめんぞ。むしろ逆効果だ。過去が原因なんだからな」
タクシーは走り続ける、走馬灯のように。
「もうやめてくれ。生きるから、いい加減に止まってくれよ」
ぐるぐると男の過去をぐるぐると。
「お父さん、昔はロボットいなかったって本当?」
子供の疑問に父親は嬉しそうに答える。
「そうとも。それどころか人間も働いてたんだぞ」
「なんでそんなことしなきゃいけないの」
「まだまだ昔は社会が未完成だったからさ」
息子は驚くような呆れるような反応をする。
「この時代に生まれてよかった。仕事なんてやりたくないもん」
「なら、昔の人に感謝しなくては。今はやりたくないの集大成だからな。昔の人達が辛い思いをして、その経験から成り立っているんだ」
「うん」
「じゃあもう寝ようか」
二人の脳みそはロボットを脱いで、液体で満たされたカプセルの中に移動した。
「おやすみ」
テレパシーがこだまする。
子供の疑問に父親は嬉しそうに答える。
「そうとも。それどころか人間も働いてたんだぞ」
「なんでそんなことしなきゃいけないの」
「まだまだ昔は社会が未完成だったからさ」
息子は驚くような呆れるような反応をする。
「この時代に生まれてよかった。仕事なんてやりたくないもん」
「なら、昔の人に感謝しなくては。今はやりたくないの集大成だからな。昔の人達が辛い思いをして、その経験から成り立っているんだ」
「うん」
「じゃあもう寝ようか」
二人の脳みそはロボットを脱いで、液体で満たされたカプセルの中に移動した。
「おやすみ」
テレパシーがこだまする。
February 11, 2025 at 11:07 AM
「お父さん、昔はロボットいなかったって本当?」
子供の疑問に父親は嬉しそうに答える。
「そうとも。それどころか人間も働いてたんだぞ」
「なんでそんなことしなきゃいけないの」
「まだまだ昔は社会が未完成だったからさ」
息子は驚くような呆れるような反応をする。
「この時代に生まれてよかった。仕事なんてやりたくないもん」
「なら、昔の人に感謝しなくては。今はやりたくないの集大成だからな。昔の人達が辛い思いをして、その経験から成り立っているんだ」
「うん」
「じゃあもう寝ようか」
二人の脳みそはロボットを脱いで、液体で満たされたカプセルの中に移動した。
「おやすみ」
テレパシーがこだまする。
子供の疑問に父親は嬉しそうに答える。
「そうとも。それどころか人間も働いてたんだぞ」
「なんでそんなことしなきゃいけないの」
「まだまだ昔は社会が未完成だったからさ」
息子は驚くような呆れるような反応をする。
「この時代に生まれてよかった。仕事なんてやりたくないもん」
「なら、昔の人に感謝しなくては。今はやりたくないの集大成だからな。昔の人達が辛い思いをして、その経験から成り立っているんだ」
「うん」
「じゃあもう寝ようか」
二人の脳みそはロボットを脱いで、液体で満たされたカプセルの中に移動した。
「おやすみ」
テレパシーがこだまする。
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
作文発表会、テーマは『家族』だ。私のこの書き出しに教室がどっとわいた。
「ブスは作文もブスだな」
同級生からの合いの手でさらに追い撃ちのように教室は揺れた。おかげで場はしっかりと温まった。
残念ながら、私は作文が得意なのだ。最優秀賞は必ず私がもらう。
「天国のパパが火事から助けてくれたので私の身体には火傷一つありません」
この一言で教室は静まりかえった。私の話に引き込まれた証拠だ。
沈黙の中、私の声だけが響く。
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
そう締め括ると、ほらね? 皆、泣いてる。
特別賞をもらった。
作文発表会、テーマは『家族』だ。私のこの書き出しに教室がどっとわいた。
「ブスは作文もブスだな」
同級生からの合いの手でさらに追い撃ちのように教室は揺れた。おかげで場はしっかりと温まった。
残念ながら、私は作文が得意なのだ。最優秀賞は必ず私がもらう。
「天国のパパが火事から助けてくれたので私の身体には火傷一つありません」
この一言で教室は静まりかえった。私の話に引き込まれた証拠だ。
沈黙の中、私の声だけが響く。
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
そう締め括ると、ほらね? 皆、泣いてる。
特別賞をもらった。
February 10, 2025 at 11:29 AM
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
作文発表会、テーマは『家族』だ。私のこの書き出しに教室がどっとわいた。
「ブスは作文もブスだな」
同級生からの合いの手でさらに追い撃ちのように教室は揺れた。おかげで場はしっかりと温まった。
残念ながら、私は作文が得意なのだ。最優秀賞は必ず私がもらう。
「天国のパパが火事から助けてくれたので私の身体には火傷一つありません」
この一言で教室は静まりかえった。私の話に引き込まれた証拠だ。
沈黙の中、私の声だけが響く。
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
そう締め括ると、ほらね? 皆、泣いてる。
特別賞をもらった。
作文発表会、テーマは『家族』だ。私のこの書き出しに教室がどっとわいた。
「ブスは作文もブスだな」
同級生からの合いの手でさらに追い撃ちのように教室は揺れた。おかげで場はしっかりと温まった。
残念ながら、私は作文が得意なのだ。最優秀賞は必ず私がもらう。
「天国のパパが火事から助けてくれたので私の身体には火傷一つありません」
この一言で教室は静まりかえった。私の話に引き込まれた証拠だ。
沈黙の中、私の声だけが響く。
「私のパパはカッコイイ。おかげで私も美人である」
そう締め括ると、ほらね? 皆、泣いてる。
特別賞をもらった。
「死後のマイホームはいかがですか」
そんな触れ込みでやってきた黒いフードの男。どうやら営業マンらしい。
「亡くなった時のご資産に応じて、天国でも地獄でも見合ったマイホームを用意しておきますよ」
「詐欺師もここまできたか、馬鹿馬鹿しい」
「私としては防音設備がおすすめでして」
「うるさいぞ。演技でもない。失礼なやつだ」
この時は引っ叩いて追い返したが、言われた通り、地獄は住みづらい。
「まさか自分が地獄に落ちるなんて。確かに今ならどんな汚らしい家でも落ち着ける場所が欲しい。どこにいてもこの耳障りな喚き声や悲鳴が聞こえて参ってしまう」
悪魔どもを見てると「ほらね」と、あの営業マンを思い出す。
そんな触れ込みでやってきた黒いフードの男。どうやら営業マンらしい。
「亡くなった時のご資産に応じて、天国でも地獄でも見合ったマイホームを用意しておきますよ」
「詐欺師もここまできたか、馬鹿馬鹿しい」
「私としては防音設備がおすすめでして」
「うるさいぞ。演技でもない。失礼なやつだ」
この時は引っ叩いて追い返したが、言われた通り、地獄は住みづらい。
「まさか自分が地獄に落ちるなんて。確かに今ならどんな汚らしい家でも落ち着ける場所が欲しい。どこにいてもこの耳障りな喚き声や悲鳴が聞こえて参ってしまう」
悪魔どもを見てると「ほらね」と、あの営業マンを思い出す。
February 9, 2025 at 10:22 AM
「死後のマイホームはいかがですか」
そんな触れ込みでやってきた黒いフードの男。どうやら営業マンらしい。
「亡くなった時のご資産に応じて、天国でも地獄でも見合ったマイホームを用意しておきますよ」
「詐欺師もここまできたか、馬鹿馬鹿しい」
「私としては防音設備がおすすめでして」
「うるさいぞ。演技でもない。失礼なやつだ」
この時は引っ叩いて追い返したが、言われた通り、地獄は住みづらい。
「まさか自分が地獄に落ちるなんて。確かに今ならどんな汚らしい家でも落ち着ける場所が欲しい。どこにいてもこの耳障りな喚き声や悲鳴が聞こえて参ってしまう」
悪魔どもを見てると「ほらね」と、あの営業マンを思い出す。
そんな触れ込みでやってきた黒いフードの男。どうやら営業マンらしい。
「亡くなった時のご資産に応じて、天国でも地獄でも見合ったマイホームを用意しておきますよ」
「詐欺師もここまできたか、馬鹿馬鹿しい」
「私としては防音設備がおすすめでして」
「うるさいぞ。演技でもない。失礼なやつだ」
この時は引っ叩いて追い返したが、言われた通り、地獄は住みづらい。
「まさか自分が地獄に落ちるなんて。確かに今ならどんな汚らしい家でも落ち着ける場所が欲しい。どこにいてもこの耳障りな喚き声や悲鳴が聞こえて参ってしまう」
悪魔どもを見てると「ほらね」と、あの営業マンを思い出す。
「ほらね」
自慢気な顔で彼女は言う。僕の大好きな口癖だ。
この口癖の前に彼女は予言をする。
「今日たい焼き釣れます」
そう言われたら、僕は釣りの帰りに屋台に寄って、たい焼きを買う。
「ほんとに釣れたよ」
「ほらね」
彼女のこの笑顔のためならこれくらい容易いことだ。
しかし、
「今日、隕石が落下します」
ついに無理難題が予言されてしまった。
仕方なく河原で隕石に見えそうな石を探していると、突然辺りが光って山の方から音がした。音のした方へ行くとなんと隕石が埋まっていた。
「隕石が本当に落ちてきたよ」
慌てる僕に彼女はいつもの笑顔を向ける。
「ほらね」
彼女は世界に好かれている。
自慢気な顔で彼女は言う。僕の大好きな口癖だ。
この口癖の前に彼女は予言をする。
「今日たい焼き釣れます」
そう言われたら、僕は釣りの帰りに屋台に寄って、たい焼きを買う。
「ほんとに釣れたよ」
「ほらね」
彼女のこの笑顔のためならこれくらい容易いことだ。
しかし、
「今日、隕石が落下します」
ついに無理難題が予言されてしまった。
仕方なく河原で隕石に見えそうな石を探していると、突然辺りが光って山の方から音がした。音のした方へ行くとなんと隕石が埋まっていた。
「隕石が本当に落ちてきたよ」
慌てる僕に彼女はいつもの笑顔を向ける。
「ほらね」
彼女は世界に好かれている。
February 8, 2025 at 6:40 PM
「ほらね」
自慢気な顔で彼女は言う。僕の大好きな口癖だ。
この口癖の前に彼女は予言をする。
「今日たい焼き釣れます」
そう言われたら、僕は釣りの帰りに屋台に寄って、たい焼きを買う。
「ほんとに釣れたよ」
「ほらね」
彼女のこの笑顔のためならこれくらい容易いことだ。
しかし、
「今日、隕石が落下します」
ついに無理難題が予言されてしまった。
仕方なく河原で隕石に見えそうな石を探していると、突然辺りが光って山の方から音がした。音のした方へ行くとなんと隕石が埋まっていた。
「隕石が本当に落ちてきたよ」
慌てる僕に彼女はいつもの笑顔を向ける。
「ほらね」
彼女は世界に好かれている。
自慢気な顔で彼女は言う。僕の大好きな口癖だ。
この口癖の前に彼女は予言をする。
「今日たい焼き釣れます」
そう言われたら、僕は釣りの帰りに屋台に寄って、たい焼きを買う。
「ほんとに釣れたよ」
「ほらね」
彼女のこの笑顔のためならこれくらい容易いことだ。
しかし、
「今日、隕石が落下します」
ついに無理難題が予言されてしまった。
仕方なく河原で隕石に見えそうな石を探していると、突然辺りが光って山の方から音がした。音のした方へ行くとなんと隕石が埋まっていた。
「隕石が本当に落ちてきたよ」
慌てる僕に彼女はいつもの笑顔を向ける。
「ほらね」
彼女は世界に好かれている。
私は元来仕事人間で、
「趣味なんて」
と仕事以外に費やす時間を軽蔑していた。
しかし、仕事の関係者から教えてもらった『廃星巡り』これは私にぴったりのものだった。
荒廃した星へ行き、いつ、なぜ、どうやって滅び、どんな星だったのか、想いを馳せながら旅をするのだ。
今では星を見ただけで攻め方が頭に浮かぶようになった。廃星巡りだけでなく観光地の星々も旅行してさらにその能力を磨いた。
おかげで、仕事は鰻登りに出世。これぞ実益を伴った趣味だ。充実した人生だ。
最近では同じ趣味仲間と一緒に星を巡り、私はガイドのようなこともしている。自分が滅ぼした星だ、知らない事など何もない。
「趣味なんて」
と仕事以外に費やす時間を軽蔑していた。
しかし、仕事の関係者から教えてもらった『廃星巡り』これは私にぴったりのものだった。
荒廃した星へ行き、いつ、なぜ、どうやって滅び、どんな星だったのか、想いを馳せながら旅をするのだ。
今では星を見ただけで攻め方が頭に浮かぶようになった。廃星巡りだけでなく観光地の星々も旅行してさらにその能力を磨いた。
おかげで、仕事は鰻登りに出世。これぞ実益を伴った趣味だ。充実した人生だ。
最近では同じ趣味仲間と一緒に星を巡り、私はガイドのようなこともしている。自分が滅ぼした星だ、知らない事など何もない。
February 7, 2025 at 9:17 AM
私は元来仕事人間で、
「趣味なんて」
と仕事以外に費やす時間を軽蔑していた。
しかし、仕事の関係者から教えてもらった『廃星巡り』これは私にぴったりのものだった。
荒廃した星へ行き、いつ、なぜ、どうやって滅び、どんな星だったのか、想いを馳せながら旅をするのだ。
今では星を見ただけで攻め方が頭に浮かぶようになった。廃星巡りだけでなく観光地の星々も旅行してさらにその能力を磨いた。
おかげで、仕事は鰻登りに出世。これぞ実益を伴った趣味だ。充実した人生だ。
最近では同じ趣味仲間と一緒に星を巡り、私はガイドのようなこともしている。自分が滅ぼした星だ、知らない事など何もない。
「趣味なんて」
と仕事以外に費やす時間を軽蔑していた。
しかし、仕事の関係者から教えてもらった『廃星巡り』これは私にぴったりのものだった。
荒廃した星へ行き、いつ、なぜ、どうやって滅び、どんな星だったのか、想いを馳せながら旅をするのだ。
今では星を見ただけで攻め方が頭に浮かぶようになった。廃星巡りだけでなく観光地の星々も旅行してさらにその能力を磨いた。
おかげで、仕事は鰻登りに出世。これぞ実益を伴った趣味だ。充実した人生だ。
最近では同じ趣味仲間と一緒に星を巡り、私はガイドのようなこともしている。自分が滅ぼした星だ、知らない事など何もない。
お気に入りの喫茶店ができた。
蒼黒い天井にはプラネタリウムが星々を映し出し、様々な星から取り寄せたインテリアが醸し出す雰囲気は絶妙に混ざり合い、この店をオリジナルたらしめていた。
星の名前のついたブレンドコーヒーは、実在する星の伝統的なもので、注文すると語り部ロボットがやってきてその星の歴史を語ってくれる。
ほとんどのコーヒーを飲んでみて、私の中の流行りは地球だ。風味も苦味も語られる物語も何度注文しても飽きがこない。
「マスター、いつもの」
「すみません、廃番です」
「ああ……。そうですか」
この店での廃番はその星の滅亡を意味する。仕方なく他のコーヒーを頼む。これもこの店の醍醐味だ。
蒼黒い天井にはプラネタリウムが星々を映し出し、様々な星から取り寄せたインテリアが醸し出す雰囲気は絶妙に混ざり合い、この店をオリジナルたらしめていた。
星の名前のついたブレンドコーヒーは、実在する星の伝統的なもので、注文すると語り部ロボットがやってきてその星の歴史を語ってくれる。
ほとんどのコーヒーを飲んでみて、私の中の流行りは地球だ。風味も苦味も語られる物語も何度注文しても飽きがこない。
「マスター、いつもの」
「すみません、廃番です」
「ああ……。そうですか」
この店での廃番はその星の滅亡を意味する。仕方なく他のコーヒーを頼む。これもこの店の醍醐味だ。
February 6, 2025 at 8:15 AM
お気に入りの喫茶店ができた。
蒼黒い天井にはプラネタリウムが星々を映し出し、様々な星から取り寄せたインテリアが醸し出す雰囲気は絶妙に混ざり合い、この店をオリジナルたらしめていた。
星の名前のついたブレンドコーヒーは、実在する星の伝統的なもので、注文すると語り部ロボットがやってきてその星の歴史を語ってくれる。
ほとんどのコーヒーを飲んでみて、私の中の流行りは地球だ。風味も苦味も語られる物語も何度注文しても飽きがこない。
「マスター、いつもの」
「すみません、廃番です」
「ああ……。そうですか」
この店での廃番はその星の滅亡を意味する。仕方なく他のコーヒーを頼む。これもこの店の醍醐味だ。
蒼黒い天井にはプラネタリウムが星々を映し出し、様々な星から取り寄せたインテリアが醸し出す雰囲気は絶妙に混ざり合い、この店をオリジナルたらしめていた。
星の名前のついたブレンドコーヒーは、実在する星の伝統的なもので、注文すると語り部ロボットがやってきてその星の歴史を語ってくれる。
ほとんどのコーヒーを飲んでみて、私の中の流行りは地球だ。風味も苦味も語られる物語も何度注文しても飽きがこない。
「マスター、いつもの」
「すみません、廃番です」
「ああ……。そうですか」
この店での廃番はその星の滅亡を意味する。仕方なく他のコーヒーを頼む。これもこの店の醍醐味だ。
とある二人の男が真剣な面持ちで酒場に集まった。
「ついに魔王が復活したな」
「俺たちの出番というわけだ」
「勇者様が現れる前にどれだけ動けるか。酒も今日でしばらくは断たないとな」
彼らは職人だ。一人は壺、もう一人はタルを作っている。何の変哲もない、安価なものだ。
しかし、それが良いのだ。皆に重宝がられ、今では世界中に普及した。
「職人、冥利に尽きる、と言いたいところだが」
「どうせ勇者様に壊されるのだからな」
しばらくして、彼らの読み通り、注文が殺到した。在庫はみるみる減っていく。
「勇者様は今、北の町に来てるらしいぞ」
そんな噂話を聞いては、今日も彼らはその方向に手を合わせる。
「ついに魔王が復活したな」
「俺たちの出番というわけだ」
「勇者様が現れる前にどれだけ動けるか。酒も今日でしばらくは断たないとな」
彼らは職人だ。一人は壺、もう一人はタルを作っている。何の変哲もない、安価なものだ。
しかし、それが良いのだ。皆に重宝がられ、今では世界中に普及した。
「職人、冥利に尽きる、と言いたいところだが」
「どうせ勇者様に壊されるのだからな」
しばらくして、彼らの読み通り、注文が殺到した。在庫はみるみる減っていく。
「勇者様は今、北の町に来てるらしいぞ」
そんな噂話を聞いては、今日も彼らはその方向に手を合わせる。
February 5, 2025 at 9:49 AM
とある二人の男が真剣な面持ちで酒場に集まった。
「ついに魔王が復活したな」
「俺たちの出番というわけだ」
「勇者様が現れる前にどれだけ動けるか。酒も今日でしばらくは断たないとな」
彼らは職人だ。一人は壺、もう一人はタルを作っている。何の変哲もない、安価なものだ。
しかし、それが良いのだ。皆に重宝がられ、今では世界中に普及した。
「職人、冥利に尽きる、と言いたいところだが」
「どうせ勇者様に壊されるのだからな」
しばらくして、彼らの読み通り、注文が殺到した。在庫はみるみる減っていく。
「勇者様は今、北の町に来てるらしいぞ」
そんな噂話を聞いては、今日も彼らはその方向に手を合わせる。
「ついに魔王が復活したな」
「俺たちの出番というわけだ」
「勇者様が現れる前にどれだけ動けるか。酒も今日でしばらくは断たないとな」
彼らは職人だ。一人は壺、もう一人はタルを作っている。何の変哲もない、安価なものだ。
しかし、それが良いのだ。皆に重宝がられ、今では世界中に普及した。
「職人、冥利に尽きる、と言いたいところだが」
「どうせ勇者様に壊されるのだからな」
しばらくして、彼らの読み通り、注文が殺到した。在庫はみるみる減っていく。
「勇者様は今、北の町に来てるらしいぞ」
そんな噂話を聞いては、今日も彼らはその方向に手を合わせる。