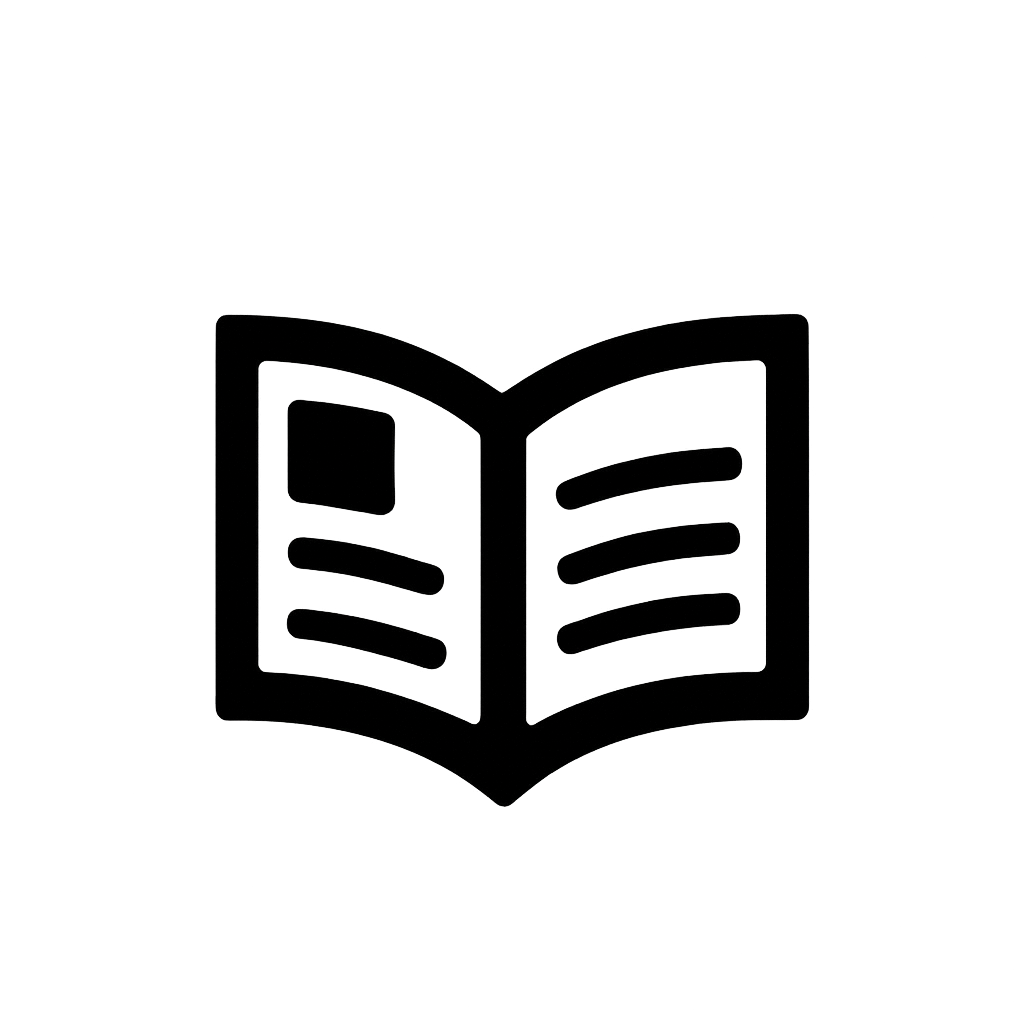えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
35 followers
53 following
390 posts
洋画沼に潜むもの。常に何かを編んでいる。責任能力のある成人が、自ら愚かさに足を踏み入れていく表現が好き。
Posts
Media
Videos
Starter Packs
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· 13d
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· 13d
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· 13d
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· 13d
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 12
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 12
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 12
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 12
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 10
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 4
えむぐりあ
@emgrie1.bsky.social
· Sep 1