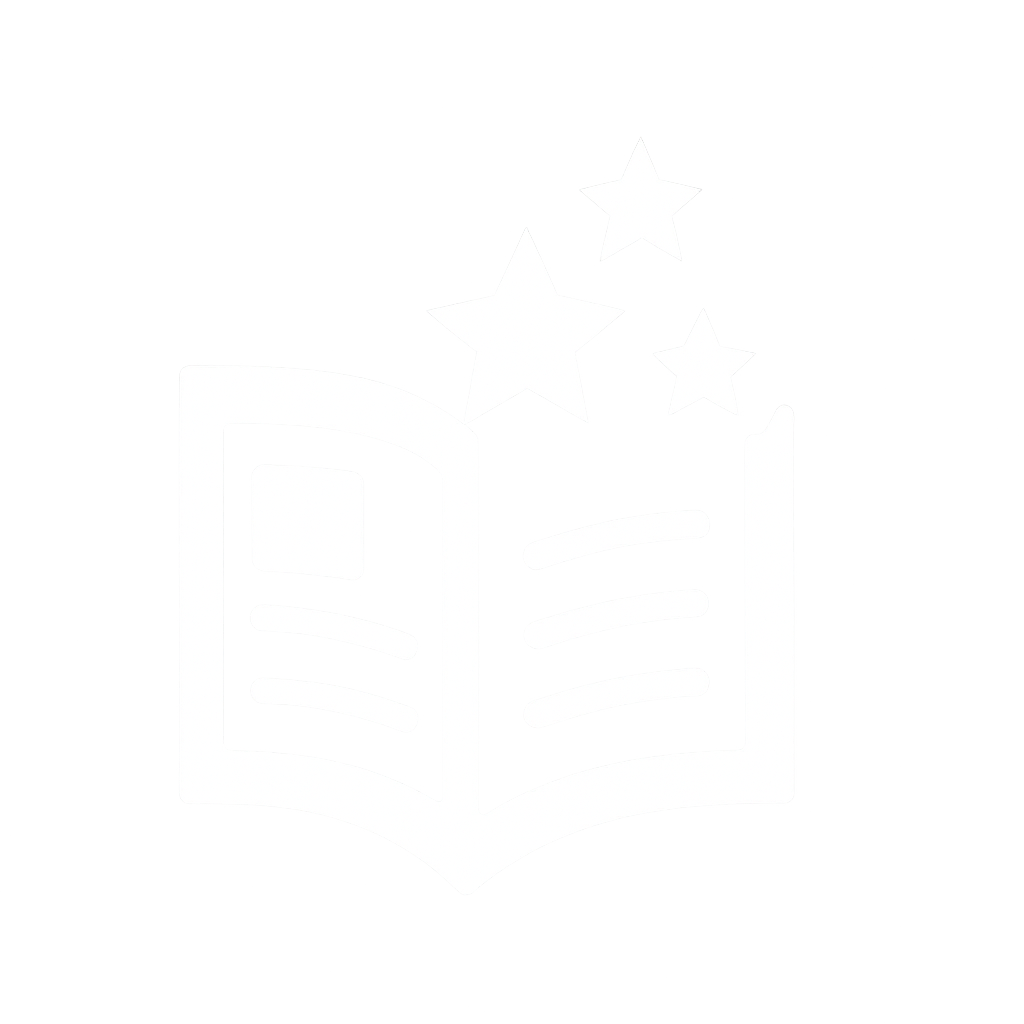明日 雨
@hinemosunotako720.bsky.social
100 followers
28 following
2.5K posts
燗酒好き。ドラマ好き。アイコンは神田まつやの鍋焼きうどんです。ここのアカウントには、主に朝ドラと読んだ本のことについて投稿してます。フォローもフォロー解除もお気軽に、です。
Posts
Media
Videos
Starter Packs