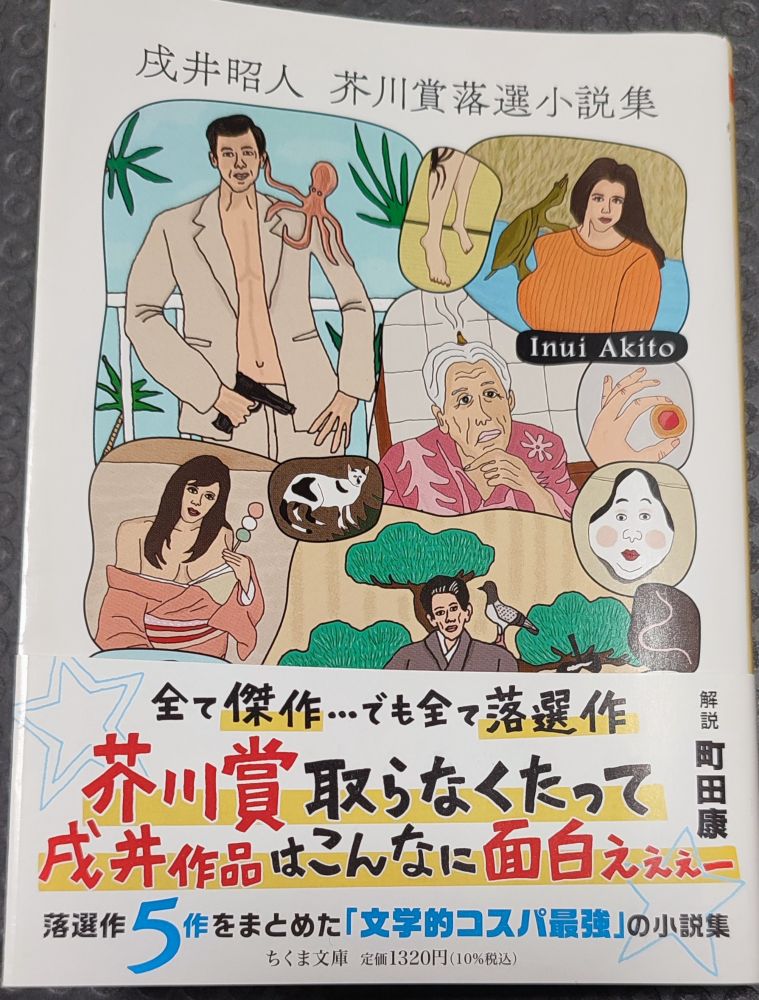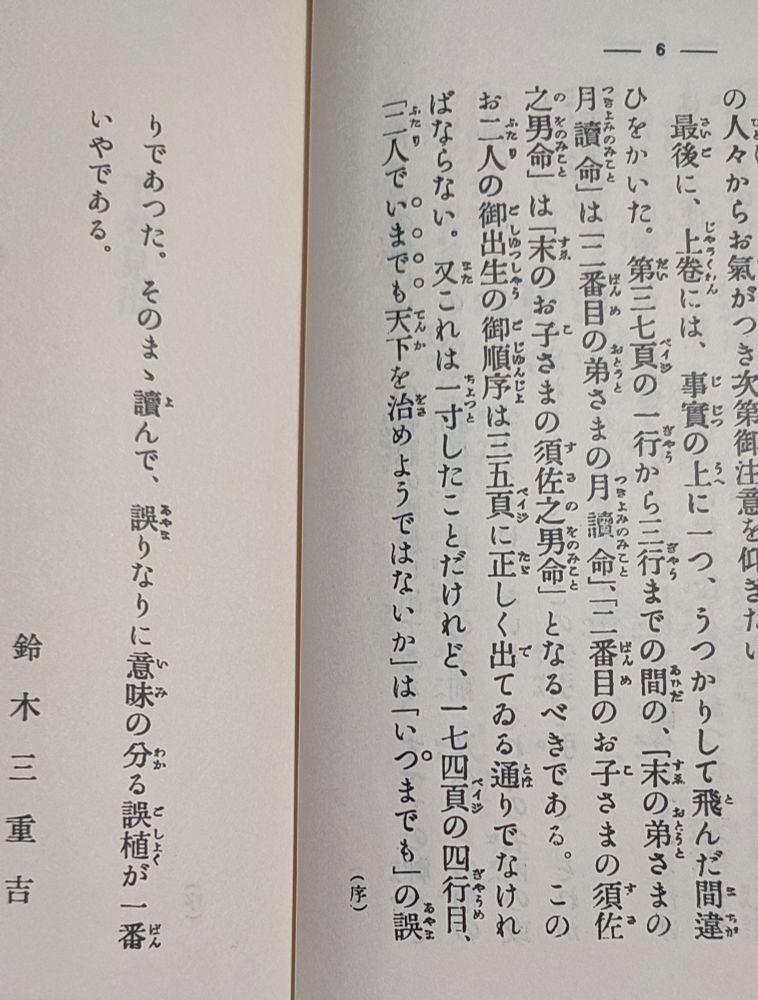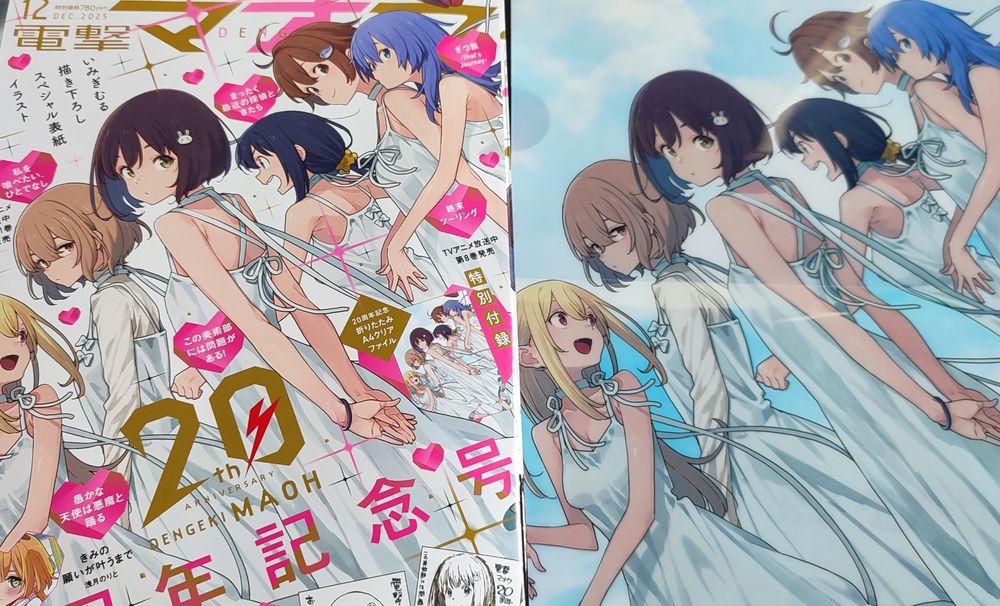hisadan
@hisadan.bsky.social
46 followers
19 following
570 posts
日々雑感。読んだ本とかその他諸々。自分用のライフログ。
Processing関連のことはXで。https://twitter.com/hisadan
Processingで作ったもの:https://scrapbox.io/hisadan/
Posts
Media
Videos
Starter Packs
hisadan
@hisadan.bsky.social
· 10d
hisadan
@hisadan.bsky.social
· 24d
hisadan
@hisadan.bsky.social
· Oct 5