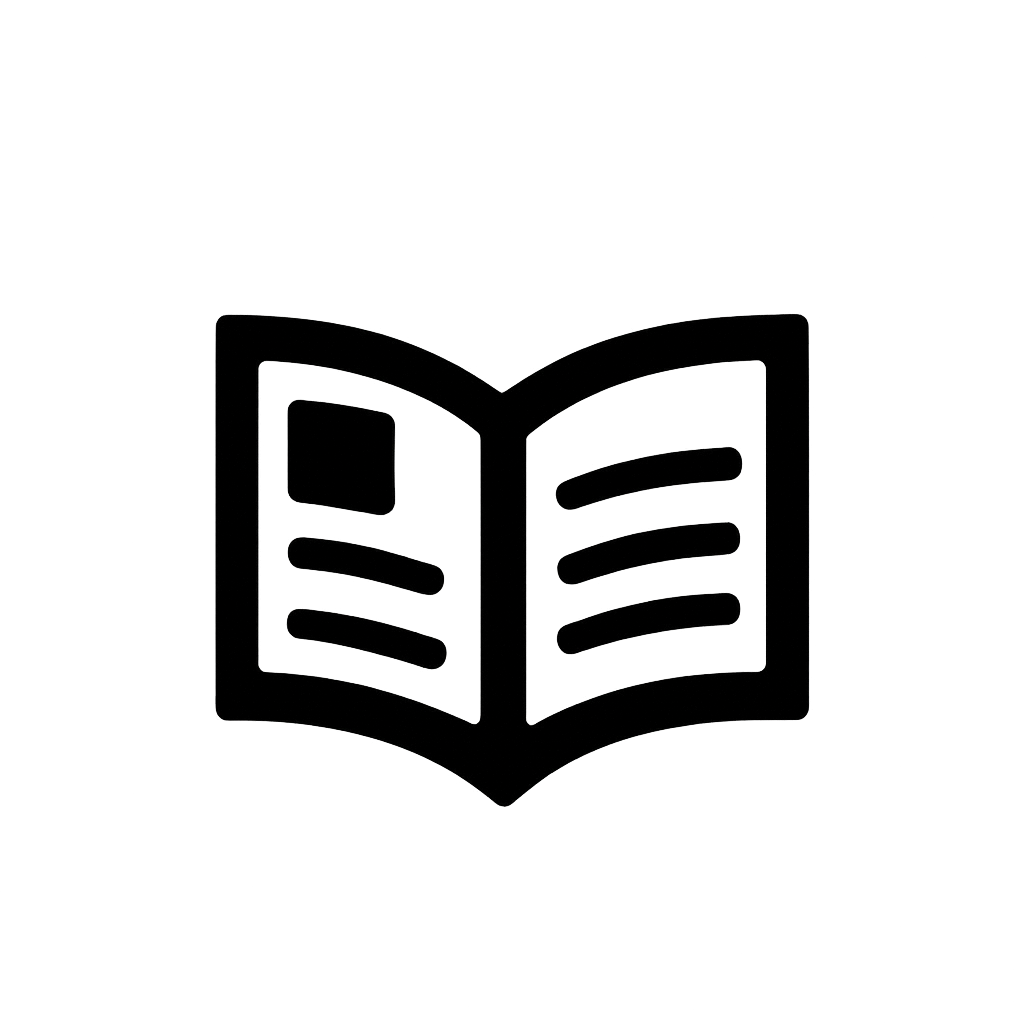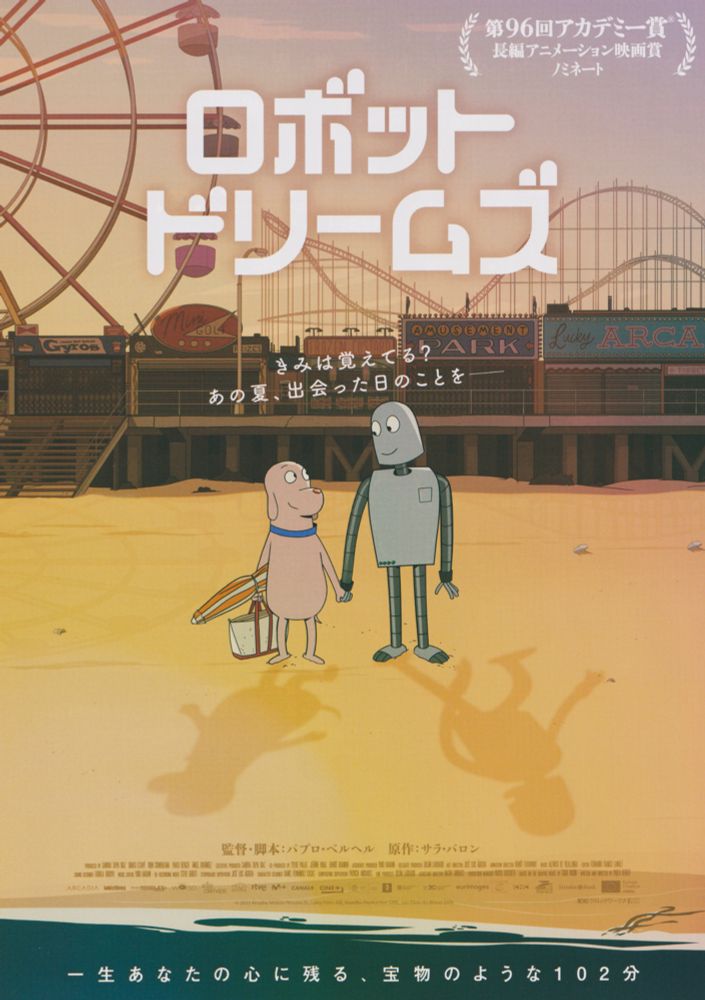青沼ペトロ
@petroaonuma.bsky.social
740 followers
1.5K following
2K posts
[Dodidn*]Dry Shack(乾いた家)主宰。Writer & Novelist。文藝ブログ[Petro Notes]執筆。1972年生。現代思想や社会学、セクシュアリティ教育に関心あり。プロの小説家志望。ウェブ小説サイト[架空の演劇の物語]、ウェブサイト[カゼヒカル やましい大人の性のテクスト]公開中。
https://dodidn.com
Posts
Media
Videos
Starter Packs