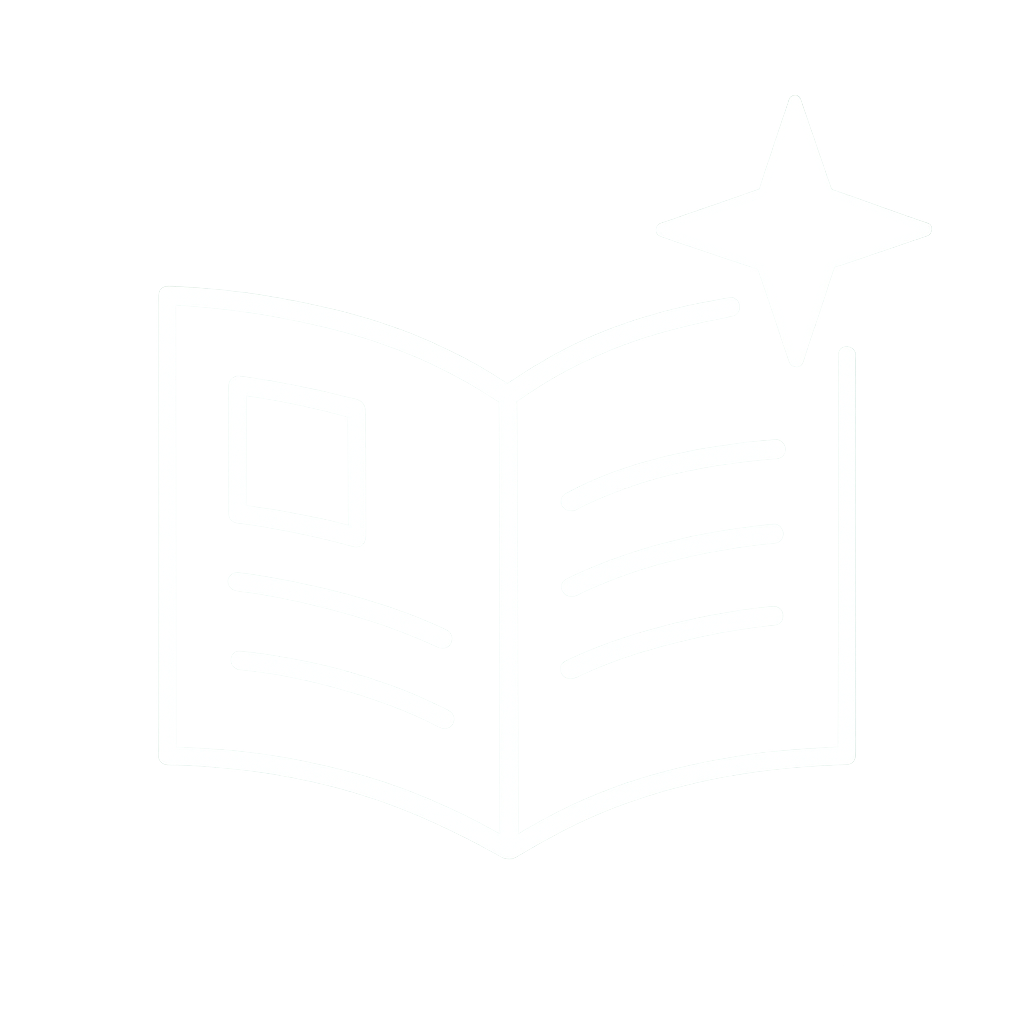X : @anteros
前書きで興味深かったのは、この話をwestern financierと名付けられているところだ。続刊があるし本書で主人公が銃を習っているので、いずれガンファイトなどあると思うが、本書ではお金というか財産のやり取りが問題になる。私が読んだウエスタンもののなかではかなり異色でジャンルの広がりを感じた。


前書きで興味深かったのは、この話をwestern financierと名付けられているところだ。続刊があるし本書で主人公が銃を習っているので、いずれガンファイトなどあると思うが、本書ではお金というか財産のやり取りが問題になる。私が読んだウエスタンもののなかではかなり異色でジャンルの広がりを感じた。
どう考えても話が終わってないので、次巻の予告とかそういうのは見当たらなかったが続刊があるだろう。ウエスタンものとしてあまりないなと思ったのは、砂漠のシーンが全くなかったことだ。冬で雪深いところが舞台だったのだが、いままでそういう作品に出会ったことなかったので興味深かった。


どう考えても話が終わってないので、次巻の予告とかそういうのは見当たらなかったが続刊があるだろう。ウエスタンものとしてあまりないなと思ったのは、砂漠のシーンが全くなかったことだ。冬で雪深いところが舞台だったのだが、いままでそういう作品に出会ったことなかったので興味深かった。
三部作といっても時間的に連続しているのではなく、同じ時期を異なる視点から描いているらしい。それにしてもこの一作目はなんというか、ひどい。作品的に劣っているということではなく、とにかく動物を殺しまくる。よく見たら表紙から想像できたわけだが、全然気づかずにわりとショックだった。


三部作といっても時間的に連続しているのではなく、同じ時期を異なる視点から描いているらしい。それにしてもこの一作目はなんというか、ひどい。作品的に劣っているということではなく、とにかく動物を殺しまくる。よく見たら表紙から想像できたわけだが、全然気づかずにわりとショックだった。
自伝的作品とみた場合に興味深いのは、作品にするために取材して、その取材を描いているのだから当然ある種のメタ構造、というか作品を描くことについて語ることになる。こういったことがみられるようになるのは90年代後半くらいだと思うのだが、それを早い時期から現在にいたるまでずうっとやり続けているのがダヴォドーなのかなと思っている。


自伝的作品とみた場合に興味深いのは、作品にするために取材して、その取材を描いているのだから当然ある種のメタ構造、というか作品を描くことについて語ることになる。こういったことがみられるようになるのは90年代後半くらいだと思うのだが、それを早い時期から現在にいたるまでずうっとやり続けているのがダヴォドーなのかなと思っている。
何よりも色の使い方が素晴らしい。基本はモノクロームで、いざというときにカラーで訴える、という感じ。ペンギンがたくさんのシーンなんかが圧巻。写真のシーンも海の感じが屋内の白黒とのコントラストで鮮やかな感じ。最新作も楽しみ。


何よりも色の使い方が素晴らしい。基本はモノクロームで、いざというときにカラーで訴える、という感じ。ペンギンがたくさんのシーンなんかが圧巻。写真のシーンも海の感じが屋内の白黒とのコントラストで鮮やかな感じ。最新作も楽しみ。
作者がケベックの人らしく、crissとかmardeとか見たことのない表現があり、バンド・デシネ読むならこういった表現も勉強しないとなと思った。写真のページは止まっているホテルに隠しカメラがつけられたところのシーンだが、これはちょっと怖い…。


作者がケベックの人らしく、crissとかmardeとか見たことのない表現があり、バンド・デシネ読むならこういった表現も勉強しないとなと思った。写真のページは止まっているホテルに隠しカメラがつけられたところのシーンだが、これはちょっと怖い…。
どうやらころ中で描いたらしく、話はUFO学から陰謀論の話につながる。自伝的作品というと病気ものが結構あって、その場合ある程度直った後で作品が書かれることが多いが、これもある種の病気という感じなのだろうか、結果的にUFOから距離をとったかたちになる。


どうやらころ中で描いたらしく、話はUFO学から陰謀論の話につながる。自伝的作品というと病気ものが結構あって、その場合ある程度直った後で作品が書かれることが多いが、これもある種の病気という感じなのだろうか、結果的にUFOから距離をとったかたちになる。
序文にダヴィッド・Bが書いていることもあり、縁が深いのだろうか、絵柄がかなり似ている。このドラッグやっていっちゃってる表情が素晴らしい。彼女の作品ではアングレームで賞をとった作品も入手済みなのでいずれ読むと思う。


序文にダヴィッド・Bが書いていることもあり、縁が深いのだろうか、絵柄がかなり似ている。このドラッグやっていっちゃってる表情が素晴らしい。彼女の作品ではアングレームで賞をとった作品も入手済みなのでいずれ読むと思う。
初出は1996年だが、そもそもこれまでリアリスティックな画風での自伝的作品ってほとんどなかったのではないかなと思う。こういうところからルポルタージュ的かつ自伝的なダヴォドーのような作品が生まれる土壌ができたのかなと。


初出は1996年だが、そもそもこれまでリアリスティックな画風での自伝的作品ってほとんどなかったのではないかなと思う。こういうところからルポルタージュ的かつ自伝的なダヴォドーのような作品が生まれる土壌ができたのかなと。
自分の中のいろんな性格の人と対話をするシーンで口からもう一人の自分を出すシーンが結構印象に残った。この人もMenuと同様ウバポの中心人物だと思うが、当然Menuも作品に登場するのだが、途中まで全く気付かなかった。ボーダーの人がそれで、確かMenuの作品でも同じ服着てたので気づいた。ボーダー好きなのか。


自分の中のいろんな性格の人と対話をするシーンで口からもう一人の自分を出すシーンが結構印象に残った。この人もMenuと同様ウバポの中心人物だと思うが、当然Menuも作品に登場するのだが、途中まで全く気付かなかった。ボーダーの人がそれで、確かMenuの作品でも同じ服着てたので気づいた。ボーダー好きなのか。
なにより字が読みにくい…。読み通すのにすごく難儀した。最初はaとoの区別がつかなかったが、だんだん字の癖がわかるようにはなった。字体の多様さはバンド・デシネの魅力の一つだが、これはしんどい…。


なにより字が読みにくい…。読み通すのにすごく難儀した。最初はaとoの区別がつかなかったが、だんだん字の癖がわかるようにはなった。字体の多様さはバンド・デシネの魅力の一つだが、これはしんどい…。
海辺に数十人の死体が発見される、というかなり派手な感じで始まるが、読んでみるとThilliezとは思えない展開で、ちょっとビビったが、どうやらもう一人の原作者であるNiko Tackianによるものっぽい。


海辺に数十人の死体が発見される、というかなり派手な感じで始まるが、読んでみるとThilliezとは思えない展開で、ちょっとビビったが、どうやらもう一人の原作者であるNiko Tackianによるものっぽい。
彼女自身の言葉は色を変えた字で書いてあって、その部分で自伝と言えなくはないが、(Lejeune的な意味ではなく)一般的な意味で自伝と言えるのか、というのはちょっと難しいが、バンド・デシネ特有の例なのかなと。


彼女自身の言葉は色を変えた字で書いてあって、その部分で自伝と言えなくはないが、(Lejeune的な意味ではなく)一般的な意味で自伝と言えるのか、というのはちょっと難しいが、バンド・デシネ特有の例なのかなと。
時代なのかお国柄なのか、わりときつい感じが多かった。その中でもびっくりしたのが、汲み取り式のトイレになっているのかトイレの下に声ダメみたいなところがあってそこに忍び込んで用を足そうとした人を驚かすといったもの。普通に引くんですけど…。


時代なのかお国柄なのか、わりときつい感じが多かった。その中でもびっくりしたのが、汲み取り式のトイレになっているのかトイレの下に声ダメみたいなところがあってそこに忍び込んで用を足そうとした人を驚かすといったもの。普通に引くんですけど…。
最初はモノクロ的な作品かなと思って読み進めると徐々にカラーが多くなって、そのせいかそのコントラストが非常に印象的に残る。この過程と作者がチェルノブイリおよびその周辺に住む人々との関係の鮮明化が並行している感じが面白かった。


最初はモノクロ的な作品かなと思って読み進めると徐々にカラーが多くなって、そのせいかそのコントラストが非常に印象的に残る。この過程と作者がチェルノブイリおよびその周辺に住む人々との関係の鮮明化が並行している感じが面白かった。
わりと驚いたのは父親に対する愛憎の後者の部分をかなりはっきりと書いているところで、端的に言うと殺したい的な感じ。こういってはなんだが、ある種好感は持てた。長い話だが読み続けることができたのはそういったところもあったと思う。


わりと驚いたのは父親に対する愛憎の後者の部分をかなりはっきりと書いているところで、端的に言うと殺したい的な感じ。こういってはなんだが、ある種好感は持てた。長い話だが読み続けることができたのはそういったところもあったと思う。
そもそも彼がこんなに料理ガチ勢だったことを知らなかった。普通に料理人になってたかもしれないレベル。それはそうと面白かったのは写真にあるように指導教員のロラン・バルトを家に招待した時のシーンで、バルトのお気に召さなかったらしく「お、おう…」的なリアクションをしている。


そもそも彼がこんなに料理ガチ勢だったことを知らなかった。普通に料理人になってたかもしれないレベル。それはそうと面白かったのは写真にあるように指導教員のロラン・バルトを家に招待した時のシーンで、バルトのお気に召さなかったらしく「お、おう…」的なリアクションをしている。
普通に勉強になるし、ご自身がてんかん症状で薬に依存的なこともあって、では甘いものへの依存は? という問いから出発する感じも面白かった。それと作者自身が登場するのだが、自分の造形と実際の取材先の研究者等の造形がやや異なることが気になった。後者がよりリアリスティックになっている感じ。


普通に勉強になるし、ご自身がてんかん症状で薬に依存的なこともあって、では甘いものへの依存は? という問いから出発する感じも面白かった。それと作者自身が登場するのだが、自分の造形と実際の取材先の研究者等の造形がやや異なることが気になった。後者がよりリアリスティックになっている感じ。
白黒ということもあって、何というかアフタヌーンとかに載っていそうな絵柄。非常に読みやすかった。やはり翻訳者の原さんにとってはマンガに近いという感じで翻訳されたのだろうか。


白黒ということもあって、何というかアフタヌーンとかに載っていそうな絵柄。非常に読みやすかった。やはり翻訳者の原さんにとってはマンガに近いという感じで翻訳されたのだろうか。
作者のもともとの画風なのだろうけど、いきなりリアリスティックではない幻想的ともいえるコマが急に出てくるのが印象的だった。あと桜沢如一の名前が急に出てきたのもびっくりした。そういえばフランスにいたんだっけ。


作者のもともとの画風なのだろうけど、いきなりリアリスティックではない幻想的ともいえるコマが急に出てくるのが印象的だった。あと桜沢如一の名前が急に出てきたのもびっくりした。そういえばフランスにいたんだっけ。
いくら何でもセックスのことばかりだろ…と思ってたら、終盤でこのページで、ぐうの音も出なかった…。自伝であろうと何だろうと物語は選択によって成り立っていて、一冊の本が一つの人生になることはない、という感じ。


いくら何でもセックスのことばかりだろ…と思ってたら、終盤でこのページで、ぐうの音も出なかった…。自伝であろうと何だろうと物語は選択によって成り立っていて、一冊の本が一つの人生になることはない、という感じ。
ちょっと面白かったのは子供の頃を語りながら急に執筆当時の湾岸戦争のコマとかが出てきて、急に語り手の実在のようなものを喚起してきたところだ。一瞬わかんなくって二度見してしまった。


ちょっと面白かったのは子供の頃を語りながら急に執筆当時の湾岸戦争のコマとかが出てきて、急に語り手の実在のようなものを喚起してきたところだ。一瞬わかんなくって二度見してしまった。
何より色遣いが素晴らしい。ムラのない単色が使われているが、リーニュ・クレールとは全く違う。視線誘導にも使われているし、白黒のページとのコントラストも面白い。この作者はほかにもいろいろ描いているらしいのでちょっと気にかけておこう。


何より色遣いが素晴らしい。ムラのない単色が使われているが、リーニュ・クレールとは全く違う。視線誘導にも使われているし、白黒のページとのコントラストも面白い。この作者はほかにもいろいろ描いているらしいのでちょっと気にかけておこう。
わりとシンプルというかあまりリアリスティックな造形ではないキャラだが、そのことによって主人公がフクロウになぞらえられるシーンに違和感がなくわりとストーリーにあってるなと感じた。


わりとシンプルというかあまりリアリスティックな造形ではないキャラだが、そのことによって主人公がフクロウになぞらえられるシーンに違和感がなくわりとストーリーにあってるなと感じた。