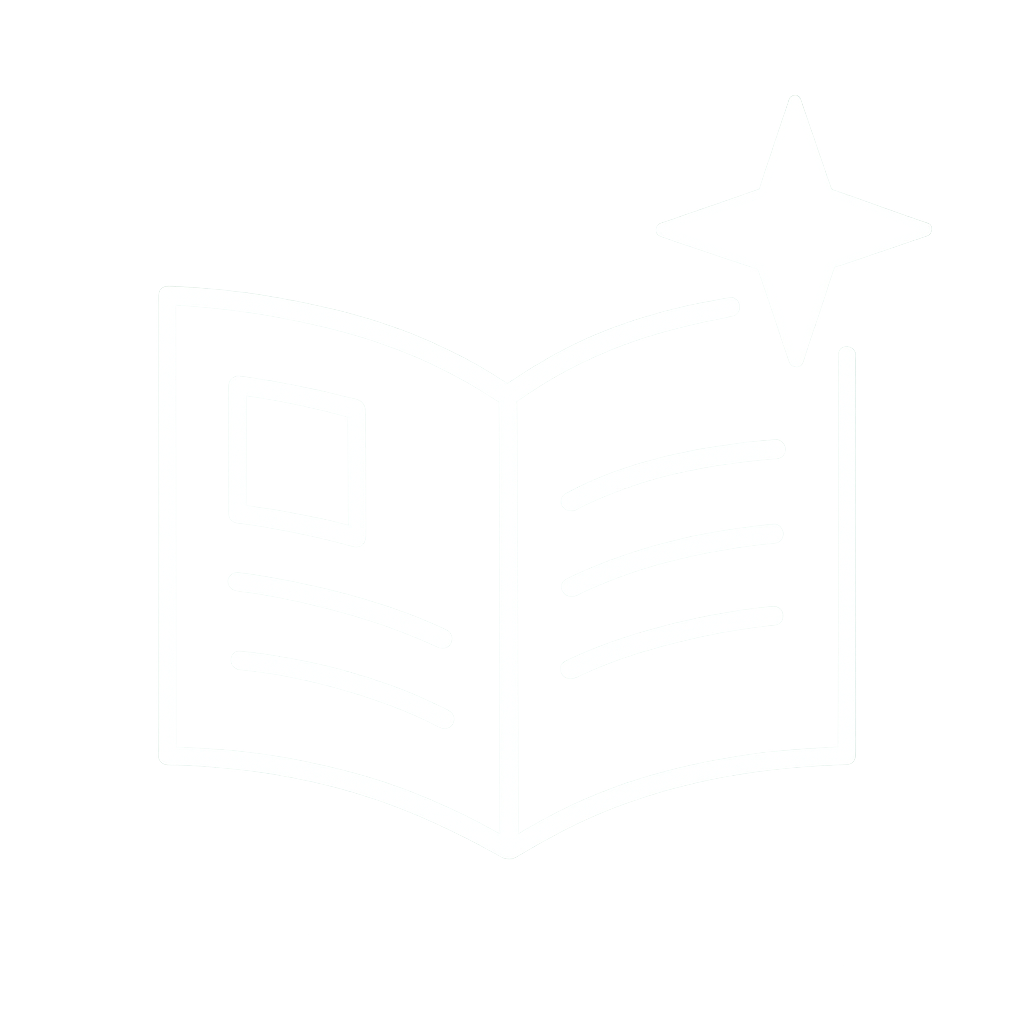伊サクは鍵が見つからないのか、バッグの中を漁り、それから上着のポケットに手を突っ込む。その隙に上着の右ポケットから鍵が転がり落ちた。
「あ」
「はい、どうぞ」
雑トは床に落ちた鍵を拾って伊サクに手渡した。
「ありがとうございます」
「私はもう行くね。また店で」
「はい、ありがとうございました!」
ぺこりと頭を下げる伊サクに手を振り背中を向ける。後ろからは伊サクが彼氏に謝る声と、これまた大きな舌打ちの音が聞こえていた。
伊サクは鍵が見つからないのか、バッグの中を漁り、それから上着のポケットに手を突っ込む。その隙に上着の右ポケットから鍵が転がり落ちた。
「あ」
「はい、どうぞ」
雑トは床に落ちた鍵を拾って伊サクに手渡した。
「ありがとうございます」
「私はもう行くね。また店で」
「はい、ありがとうございました!」
ぺこりと頭を下げる伊サクに手を振り背中を向ける。後ろからは伊サクが彼氏に謝る声と、これまた大きな舌打ちの音が聞こえていた。
「今日夜勤じゃなかったの?」
「体調悪くて帰ってきた。てかそれよりそのおっさん誰だよ。浮気?」
「違うよ。バイト先の常連さんで家が近いから送ってくれただけ」
「どうも雑トです」
男が伊サクの手を掴もうとした時、伊サクが咄嗟に腕を引っ込めるのが見えた。その反応に苛立ったのか、彼は大きく舌打ちを鳴らす。二人の間に割り込むようにして雑トが名乗ると、伊サクの彼氏は雑トのことを一瞥し、ふいと顔を逸らした。
「伊サク、鍵出せ」
「ちょっと待ってね」
「今日夜勤じゃなかったの?」
「体調悪くて帰ってきた。てかそれよりそのおっさん誰だよ。浮気?」
「違うよ。バイト先の常連さんで家が近いから送ってくれただけ」
「どうも雑トです」
男が伊サクの手を掴もうとした時、伊サクが咄嗟に腕を引っ込めるのが見えた。その反応に苛立ったのか、彼は大きく舌打ちを鳴らす。二人の間に割り込むようにして雑トが名乗ると、伊サクの彼氏は雑トのことを一瞥し、ふいと顔を逸らした。
「伊サク、鍵出せ」
「ちょっと待ってね」
「彼氏とは上手くいってるの?」
「はい。たまに喧嘩しますけど」
「学校は?」
「最近は行ってるみたいですよ」
「そう」
彼氏がアパートに転がり込んできて、パチンコ三昧の日々を送っているのだと少し前に伊サクが愚痴をこぼしていた。
「どこが好きなの?」
「うーん、僕がいないと生きていけなそうなところとか」
それはあまりに健全な関係ではないのではないかと思いつつ、それを指摘することはしなかった。
「彼氏とは上手くいってるの?」
「はい。たまに喧嘩しますけど」
「学校は?」
「最近は行ってるみたいですよ」
「そう」
彼氏がアパートに転がり込んできて、パチンコ三昧の日々を送っているのだと少し前に伊サクが愚痴をこぼしていた。
「どこが好きなの?」
「うーん、僕がいないと生きていけなそうなところとか」
それはあまりに健全な関係ではないのではないかと思いつつ、それを指摘することはしなかった。
「あら、もう帰るの?」
「明日も朝から仕事なんだよ。あと伊サクくんを送ってく約束したし」
「へぇ、ちゃっかりしてるじゃない」
彼はニヤリと笑いながら雑トのカードを受け取る。その時、荷物を持った伊サクが控え室から出てきた。この店は基本店子も私服で勤務をするので、着替えると言っても上着を羽織るぐらいだ。
「はい、まいどあり」
「また来るよ。伊サクくん帰ろっか」
「はい。お疲れ様でーす!」
「気をつけて帰るのよ」
ヒラヒラと手を振るマスターに見送られ二人は店を出た
「あら、もう帰るの?」
「明日も朝から仕事なんだよ。あと伊サクくんを送ってく約束したし」
「へぇ、ちゃっかりしてるじゃない」
彼はニヤリと笑いながら雑トのカードを受け取る。その時、荷物を持った伊サクが控え室から出てきた。この店は基本店子も私服で勤務をするので、着替えると言っても上着を羽織るぐらいだ。
「はい、まいどあり」
「また来るよ。伊サクくん帰ろっか」
「はい。お疲れ様でーす!」
「気をつけて帰るのよ」
ヒラヒラと手を振るマスターに見送られ二人は店を出た
アイコンの雑トさんは自分で描きました〜!本当に落書きなので拙くて恥ずかしいですが🙈💦
アイコンの雑トさんは自分で描きました〜!本当に落書きなので拙くて恥ずかしいですが🙈💦
「私達ももう若くないよねって話」
「伊サクくんはまだ二十歳でしょう?いいわよね、これからだもん。お肌もピチピチだし」
マスターが伊サクの頬を掴み、ぷにぷにと弄ぶ。
「いひゃいれす〜」
「伊サクくん、何か飲む?」
伊サクは赤くなった頬を手で押さえながら「いえ、もうすぐ上がりなので」と断りを入れる。
「もうそんな時間?」
驚きながら腕時計を見ると、既に23時45分を過ぎた頃だった。早く帰らないと、雑トだって明日も仕事だ。
「今日人少ないし、もう上がっていいわよ。0時まででつけとくから」
「いいんですか!じゃあ着替えてきますね」
「はーい」
「私達ももう若くないよねって話」
「伊サクくんはまだ二十歳でしょう?いいわよね、これからだもん。お肌もピチピチだし」
マスターが伊サクの頬を掴み、ぷにぷにと弄ぶ。
「いひゃいれす〜」
「伊サクくん、何か飲む?」
伊サクは赤くなった頬を手で押さえながら「いえ、もうすぐ上がりなので」と断りを入れる。
「もうそんな時間?」
驚きながら腕時計を見ると、既に23時45分を過ぎた頃だった。早く帰らないと、雑トだって明日も仕事だ。
「今日人少ないし、もう上がっていいわよ。0時まででつけとくから」
「いいんですか!じゃあ着替えてきますね」
「はーい」
「相手が雑トさんなら安心して任せられるんだけどね」
「ふふ、親みたいなことを言うね」
「まあ歳の差を考えるとそういう目線になっちゃうわよね」
「やめてよ。私と2個しか変わらないでしょう?こっちは伊サクくんのこと全然そういう目で見てるのに」
「雑トさんは40に見えないからいいじゃない。私なんか最近もう皺が凄くてさぁ……」
そこからひとしきりマスターの年齢トークに付き合わされていると、伊サクくんがやって来る。
「相手が雑トさんなら安心して任せられるんだけどね」
「ふふ、親みたいなことを言うね」
「まあ歳の差を考えるとそういう目線になっちゃうわよね」
「やめてよ。私と2個しか変わらないでしょう?こっちは伊サクくんのこと全然そういう目で見てるのに」
「雑トさんは40に見えないからいいじゃない。私なんか最近もう皺が凄くてさぁ……」
そこからひとしきりマスターの年齢トークに付き合わされていると、伊サクくんがやって来る。
「雑トさんって遊び慣れてる子が好きなのかと思ってたけど、意外とああいうのがタイプなんだね」
雑トさんと付き合いの長いマスターは揶揄うように声をかけてくる。(この後めっちゃモブ喋ります)
「まぁ遊びなら慣れてる子の方が楽だし。でも何となく目が離せないんだよね」
「まぁ分かるわよ。あの子最近よく怪我してて、彼氏と喧嘩した、仲直りしたから大丈夫って言うんだけど……」
「DV?」
「言わないけどその可能性もあるかなって」
「雑トさんって遊び慣れてる子が好きなのかと思ってたけど、意外とああいうのがタイプなんだね」
雑トさんと付き合いの長いマスターは揶揄うように声をかけてくる。(この後めっちゃモブ喋ります)
「まぁ遊びなら慣れてる子の方が楽だし。でも何となく目が離せないんだよね」
「まぁ分かるわよ。あの子最近よく怪我してて、彼氏と喧嘩した、仲直りしたから大丈夫って言うんだけど……」
「DV?」
「言わないけどその可能性もあるかなって」
「今日もお迎え来るの?」
「いえ、今日は向こうのバイトが夜勤の日なので」
「じゃあ私が駅まで送ろうか」
「え、悪いですよ」
「少しでも伊くんといる時間が伸びたら嬉しから」
「じゃあお言葉に甘えて」
ありがとうございます!と満面の笑みを浮かべる伊サクの顔を眺めていると仕事の疲れも吹っ飛ぶ。あーあ、この子の笑顔が自分にだけ向けられるのならいいのに、と思う雑トさん。
「今日もお迎え来るの?」
「いえ、今日は向こうのバイトが夜勤の日なので」
「じゃあ私が駅まで送ろうか」
「え、悪いですよ」
「少しでも伊くんといる時間が伸びたら嬉しから」
「じゃあお言葉に甘えて」
ありがとうございます!と満面の笑みを浮かべる伊サクの顔を眺めていると仕事の疲れも吹っ飛ぶ。あーあ、この子の笑顔が自分にだけ向けられるのならいいのに、と思う雑トさん。
特に火曜日は客も少なくて伊サクを独り占めできる時間が長いのが嬉しい。
「伊サクくん、その傷どうしたの?」
「あぁ、これは……彼氏とちょっと喧嘩しちゃって」
伊サクくんの唇の端が切れ、その周りが薄紫に変色している。内出血しているのだろう。
「殴られたの?」
「カッとなってつい手が出ちゃったみたいで。でもすぐに我に返って謝ってくれましたし、仲直りもしましたよ」
「仲直り出来たのなら良かった」
そう。悲しいことに伊サクくんには彼氏がいた。
特に火曜日は客も少なくて伊サクを独り占めできる時間が長いのが嬉しい。
「伊サクくん、その傷どうしたの?」
「あぁ、これは……彼氏とちょっと喧嘩しちゃって」
伊サクくんの唇の端が切れ、その周りが薄紫に変色している。内出血しているのだろう。
「殴られたの?」
「カッとなってつい手が出ちゃったみたいで。でもすぐに我に返って謝ってくれましたし、仲直りもしましたよ」
「仲直り出来たのなら良かった」
そう。悲しいことに伊サクくんには彼氏がいた。
こっちでは一旦ここまでです〜
ちゃんと伊サクくんが好きって伝えられるようになるまでのあれこれはXくんか普通に小説で書く
こっちでは一旦ここまでです〜
ちゃんと伊サクくんが好きって伝えられるようになるまでのあれこれはXくんか普通に小説で書く
「わ、苦しいよ」
「ごめん。でも嬉しくて」
首元にあたる雑の息が擽ったい。
「いつか絶対伊サクくんに私のこと好きって言わせてみせるから、私の恋人になってくれる?」
「僕でいいなら」
伊サクがそう言うと、雑はくすりと笑って伊サクの額にキスをした。
「伊サクくんが良いんだよ」
「じゃあ、よろしくお願いします」
「わ、苦しいよ」
「ごめん。でも嬉しくて」
首元にあたる雑の息が擽ったい。
「いつか絶対伊サクくんに私のこと好きって言わせてみせるから、私の恋人になってくれる?」
「僕でいいなら」
伊サクがそう言うと、雑はくすりと笑って伊サクの額にキスをした。
「伊サクくんが良いんだよ」
「じゃあ、よろしくお願いします」
そう言われて雑トの顔を見上げると、蜂蜜のような甘く蕩けた瞳と目が合い、胸がキュッと締め付けられた。
「私は伊サクくんのことが好きだよ」
「あ、の」
「伊サクくんは私の事どう思ってる?」
伊サクは酸素を求める魚のようにパクパクと口を動かした。そんな伊サクの様子を見て雑が小さく笑う。
「僕、は……」
「うん」
「好きって感情がまだよく分からないんだけど」
「うん」
雑は静かに頷きながら伊サクの辿たどしい言葉に耳を傾けていた。
「雑トくんに触れられるのは嬉しいし、雑トくんの特別になりたいって思う」
そう言われて雑トの顔を見上げると、蜂蜜のような甘く蕩けた瞳と目が合い、胸がキュッと締め付けられた。
「私は伊サクくんのことが好きだよ」
「あ、の」
「伊サクくんは私の事どう思ってる?」
伊サクは酸素を求める魚のようにパクパクと口を動かした。そんな伊サクの様子を見て雑が小さく笑う。
「僕、は……」
「うん」
「好きって感情がまだよく分からないんだけど」
「うん」
雑は静かに頷きながら伊サクの辿たどしい言葉に耳を傾けていた。
「雑トくんに触れられるのは嬉しいし、雑トくんの特別になりたいって思う」
「そう、だったんだ」
「でも伊サクくんのこと不安にさせたなら謝る。本当にごめん」
「不安というか、やっぱり雑トくんは誰とでもそういうこと出来るんだと思ったら、浮かれてた自分が馬鹿みたいで……」
「もしかして、嫉妬してくれたの?」
「そう、かも」
嫉妬、と言われて自分の感情が腑に落ちた。確かに自分は雑トが自分以外の人間と触れ合っているのが嫌だったんだ。
「そっか。嫉妬か……」
「なんで嬉しそうなの?」
「だって嫉妬ってその人の事特別だと思ってないとしないでしょ?」
「そう、だったんだ」
「でも伊サクくんのこと不安にさせたなら謝る。本当にごめん」
「不安というか、やっぱり雑トくんは誰とでもそういうこと出来るんだと思ったら、浮かれてた自分が馬鹿みたいで……」
「もしかして、嫉妬してくれたの?」
「そう、かも」
嫉妬、と言われて自分の感情が腑に落ちた。確かに自分は雑トが自分以外の人間と触れ合っているのが嫌だったんだ。
「そっか。嫉妬か……」
「なんで嬉しそうなの?」
「だって嫉妬ってその人の事特別だと思ってないとしないでしょ?」
「え?」
雑の顔を見るのが怖くて、胸元に顔を埋めたまま話し始める。
「この間、雑トくんが屋上に行く階段の踊り場で女の子といるところ、見ちゃって」
その瞬間雑が大きく息を飲む。
「どうしてもって気になって、こっそり見てたんだ、二人のこと。そしたらキスしてるのが見えて……」
「してない!」
突然大きな声を出した雑に伊サクは肩を震わせる。
「ごめん、でも誤解されたくなくて」
「え、でも……」
「伊サクくん以外とはキスもその先もしないって決めてるから」
雑の震える手が伊サクの頬に触れ「信じてくれる?」と縋るような声で尋ねられた。
「なんであんな近づいたの?」
「え?」
雑の顔を見るのが怖くて、胸元に顔を埋めたまま話し始める。
「この間、雑トくんが屋上に行く階段の踊り場で女の子といるところ、見ちゃって」
その瞬間雑が大きく息を飲む。
「どうしてもって気になって、こっそり見てたんだ、二人のこと。そしたらキスしてるのが見えて……」
「してない!」
突然大きな声を出した雑に伊サクは肩を震わせる。
「ごめん、でも誤解されたくなくて」
「え、でも……」
「伊サクくん以外とはキスもその先もしないって決めてるから」
雑の震える手が伊サクの頬に触れ「信じてくれる?」と縋るような声で尋ねられた。
「なんであんな近づいたの?」
そう尋ねてくる雑は少し泣きそうに見えた。
「嫌いになんてならないよ。キスされたのは、その、ちょっと嬉しかったし……」
言ってるうちに恥ずかしくなってきて声が小さくなる。全てを言い終わらないうちに、雑に腕を引かれ、そのまま抱きしめられた。ふわりと鼻腔を擽るのはこの間と同じ柔軟剤の匂い。
「良かった……」
噛み締めるような響に、伊サクは思わず雑の背中に手を回してぎゅっと抱きついた。顔を埋めた胸元からトクトクと駆け足な心臓の音が聞こえていた。
そう尋ねてくる雑は少し泣きそうに見えた。
「嫌いになんてならないよ。キスされたのは、その、ちょっと嬉しかったし……」
言ってるうちに恥ずかしくなってきて声が小さくなる。全てを言い終わらないうちに、雑に腕を引かれ、そのまま抱きしめられた。ふわりと鼻腔を擽るのはこの間と同じ柔軟剤の匂い。
「良かった……」
噛み締めるような響に、伊サクは思わず雑の背中に手を回してぎゅっと抱きついた。顔を埋めた胸元からトクトクと駆け足な心臓の音が聞こえていた。
「どうしたの?」
雑のことを見上げると、今まで見たことの無い不安そうな瞳と目が合う。
「伊サクくんに謝りたくて」
「謝る?なんで」
予想もしてなかったことを言われて伊サクは目を丸くする。雑は思い詰めた表情をしていた。
「この間、キスしたこと。伊サクくんは嫌だったのかもって、思って……」
「嫌だなんて思ってないよ」
「でも、伊サクくん保健室にもいないし、放課後教室に行っても会えないし、私避けられてるのかなって」
それは否定できなくて言葉に詰まる伊サクくん。
「確かにちょっと気まずかったけど、でも嫌じゃなかったよ。それは本当」
「どうしたの?」
雑のことを見上げると、今まで見たことの無い不安そうな瞳と目が合う。
「伊サクくんに謝りたくて」
「謝る?なんで」
予想もしてなかったことを言われて伊サクは目を丸くする。雑は思い詰めた表情をしていた。
「この間、キスしたこと。伊サクくんは嫌だったのかもって、思って……」
「嫌だなんて思ってないよ」
「でも、伊サクくん保健室にもいないし、放課後教室に行っても会えないし、私避けられてるのかなって」
それは否定できなくて言葉に詰まる伊サクくん。
「確かにちょっと気まずかったけど、でも嫌じゃなかったよ。それは本当」