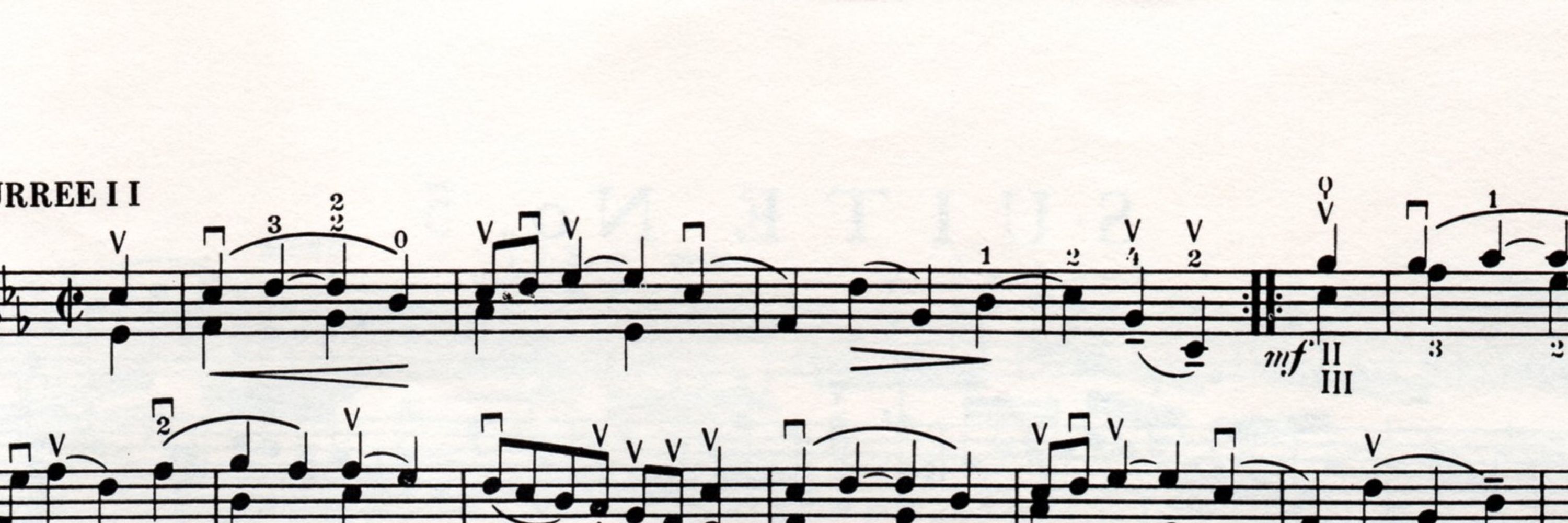

www.yomiuri.co.jp/national/202...
記事では鳥取県の風車1基からなる風力発電所(A)が「例」として取り上げられていますが、同じ鳥取県内には同時期に建てられ黒字を計上し、他の事業者に譲渡して運転延長する発電所(B)もあります。なぜBを紹介せずAのみを取り上げるのでしょうか。完全にチェリーピッキングです。
→

www.yomiuri.co.jp/national/202...
記事では鳥取県の風車1基からなる風力発電所(A)が「例」として取り上げられていますが、同じ鳥取県内には同時期に建てられ黒字を計上し、他の事業者に譲渡して運転延長する発電所(B)もあります。なぜBを紹介せずAのみを取り上げるのでしょうか。完全にチェリーピッキングです。
→
見出しの通り廃止の基数に着目するなら、リパワリング(同じ場所で新規風車に建て替え)にも言及すべきで、リパワリングが少ないとすれば、それは日本の低い再エネ導入目標に遠因があることも指摘しなければなりません。記事はどうにもピントがズレてます。
→
見出しの通り廃止の基数に着目するなら、リパワリング(同じ場所で新規風車に建て替え)にも言及すべきで、リパワリングが少ないとすれば、それは日本の低い再エネ導入目標に遠因があることも指摘しなければなりません。記事はどうにもピントがズレてます。
→
このように、「嘘をつかずに誤解を拡散させる」方法が日本で(米国でも)とても多く蔓延っているということを、日本の方は知っておく必要があります。
このように、「嘘をつかずに誤解を拡散させる」方法が日本で(米国でも)とても多く蔓延っているということを、日本の方は知っておく必要があります。

www.youtube.com/shorts/26MFb...
初心に戻って「そもそもなんで再エネを増やした方がよいの?」
特に🇯🇵は今選挙期間中のようなので、あまり争点になっていない気候変動・再エネについて、特に未来の子供だちに何を残すかという観点から、今一度深く考えてみる機会なれば幸いです。

www.youtube.com/shorts/26MFb...
初心に戻って「そもそもなんで再エネを増やした方がよいの?」
特に🇯🇵は今選挙期間中のようなので、あまり争点になっていない気候変動・再エネについて、特に未来の子供だちに何を残すかという観点から、今一度深く考えてみる機会なれば幸いです。
www.youtube.com/shorts/7bT5S...
脱炭素や再エネに関して、選挙活動と称してフェイクニュースを流しまくっている候補者も多い中、フェイクや非科学ナラティブに流されず、勇ましい断定調の見た目のカッコよさや雰囲気・情念に流されず、短期的な一時の高揚感で満足せず、長い目で見て子供や孫の世代に何が残せるか(あるいは、自分たちがおじさんおばさん世代になったときに何が残っているか)を今一度立ち止まってじっくり考えてにる機会になれば幸いです。

www.youtube.com/shorts/7bT5S...
脱炭素や再エネに関して、選挙活動と称してフェイクニュースを流しまくっている候補者も多い中、フェイクや非科学ナラティブに流されず、勇ましい断定調の見た目のカッコよさや雰囲気・情念に流されず、短期的な一時の高揚感で満足せず、長い目で見て子供や孫の世代に何が残せるか(あるいは、自分たちがおじさんおばさん世代になったときに何が残っているか)を今一度立ち止まってじっくり考えてにる機会になれば幸いです。
magazine.msz.co.jp

magazine.msz.co.jp



例えて言うなら、欧州は今まで100点の目標を掲げていたのを90点に変更したとか、80点取ろうとしてたのに75点になりそうとか、そのレベル。一方、日本と米国は未だ30点台しか取れてないのに他人を嘲笑って居直ってる感じ。
そしてそのこと自体がフェイクニュースの波に飲まれて国民に伝わらず、盛大に認知の歪みを起こしている状況です。
例えて言うなら、欧州は今まで100点の目標を掲げていたのを90点に変更したとか、80点取ろうとしてたのに75点になりそうとか、そのレベル。一方、日本と米国は未だ30点台しか取れてないのに他人を嘲笑って居直ってる感じ。
そしてそのこと自体がフェイクニュースの波に飲まれて国民に伝わらず、盛大に認知の歪みを起こしている状況です。
新しいかたちの解説目録
本との新たな出会いを提供する「岩波Web目録」を公開しました。パソコン、スマートフォンなどの端末で書誌情報を総覧できます。
☞ catalog.iwanami.co.jp
現在、岩波文庫、岩波新書、岩波現代文庫、岩波ジュニア新書が対応しています。対象レーベル、書籍は随時追加予定です。
操作方法はこちらからご覧ください。
☞ www.iwanami.co.jp/news/n117705...

新しいかたちの解説目録
本との新たな出会いを提供する「岩波Web目録」を公開しました。パソコン、スマートフォンなどの端末で書誌情報を総覧できます。
☞ catalog.iwanami.co.jp
現在、岩波文庫、岩波新書、岩波現代文庫、岩波ジュニア新書が対応しています。対象レーベル、書籍は随時追加予定です。
操作方法はこちらからご覧ください。
☞ www.iwanami.co.jp/news/n117705...



今年もよろしくお願いします。
classical.music.apple.com/jp/album/164...

今年もよろしくお願いします。
classical.music.apple.com/jp/album/164...








