長崎暢子 山内昌之(編)『現代アジア論の名著』1992年
東大教養学部の教官(当時)による「新入学生はこれくらい読んどけ!」的な目録の書評集です。
30年経ってもなお何冊かは現在でも価値ある名著だと思います。
近代韓国史においての経済的・文化的断絶については日本人が理解し得ないからこそ学ばねばならない事だと思いましたし、ナショナリズムという哲学的に貧困でいかがわしいものに人々を惹きつける力がある事にも考えさせられました。
ガンディーの『ヒンドゥ・スワラージ』は近代文明に対する弾劾の書であり、実現したインド独立の最大の批判者が著者だったんですね。
東大教養学部の教官(当時)による「新入学生はこれくらい読んどけ!」的な目録の書評集です。
30年経ってもなお何冊かは現在でも価値ある名著だと思います。
近代韓国史においての経済的・文化的断絶については日本人が理解し得ないからこそ学ばねばならない事だと思いましたし、ナショナリズムという哲学的に貧困でいかがわしいものに人々を惹きつける力がある事にも考えさせられました。
ガンディーの『ヒンドゥ・スワラージ』は近代文明に対する弾劾の書であり、実現したインド独立の最大の批判者が著者だったんですね。

November 9, 2025 at 12:31 PM
長崎暢子 山内昌之(編)『現代アジア論の名著』1992年
東大教養学部の教官(当時)による「新入学生はこれくらい読んどけ!」的な目録の書評集です。
30年経ってもなお何冊かは現在でも価値ある名著だと思います。
近代韓国史においての経済的・文化的断絶については日本人が理解し得ないからこそ学ばねばならない事だと思いましたし、ナショナリズムという哲学的に貧困でいかがわしいものに人々を惹きつける力がある事にも考えさせられました。
ガンディーの『ヒンドゥ・スワラージ』は近代文明に対する弾劾の書であり、実現したインド独立の最大の批判者が著者だったんですね。
東大教養学部の教官(当時)による「新入学生はこれくらい読んどけ!」的な目録の書評集です。
30年経ってもなお何冊かは現在でも価値ある名著だと思います。
近代韓国史においての経済的・文化的断絶については日本人が理解し得ないからこそ学ばねばならない事だと思いましたし、ナショナリズムという哲学的に貧困でいかがわしいものに人々を惹きつける力がある事にも考えさせられました。
ガンディーの『ヒンドゥ・スワラージ』は近代文明に対する弾劾の書であり、実現したインド独立の最大の批判者が著者だったんですね。
上村勝彦『バガヴァッド・ギーターの世界』2007年
岩波文庫での訳者である著者が、1995年のNHK講座テキストを底盤に同書の解説を数行毎に付した労書です。
紀元後一世紀前後のインドにはアートマン(自己)の内にブラフマン(至高存在)があり、そこには神々をはじめとする一切が在するという思想が定着していた事が解ります。この考えは大乗仏教に取り入れられて、日本仏教の本覚思想へと連なります。
仏教経典を絡めてのサンスクリット語原文解説を平易に行っている所に凄味があります。
物語は、顕現するカーラ(時間・運命・死を司る神)が『マハーバーラタ』という叙事詩自体の主軸を伴う事が神話を醸しています。
岩波文庫での訳者である著者が、1995年のNHK講座テキストを底盤に同書の解説を数行毎に付した労書です。
紀元後一世紀前後のインドにはアートマン(自己)の内にブラフマン(至高存在)があり、そこには神々をはじめとする一切が在するという思想が定着していた事が解ります。この考えは大乗仏教に取り入れられて、日本仏教の本覚思想へと連なります。
仏教経典を絡めてのサンスクリット語原文解説を平易に行っている所に凄味があります。
物語は、顕現するカーラ(時間・運命・死を司る神)が『マハーバーラタ』という叙事詩自体の主軸を伴う事が神話を醸しています。
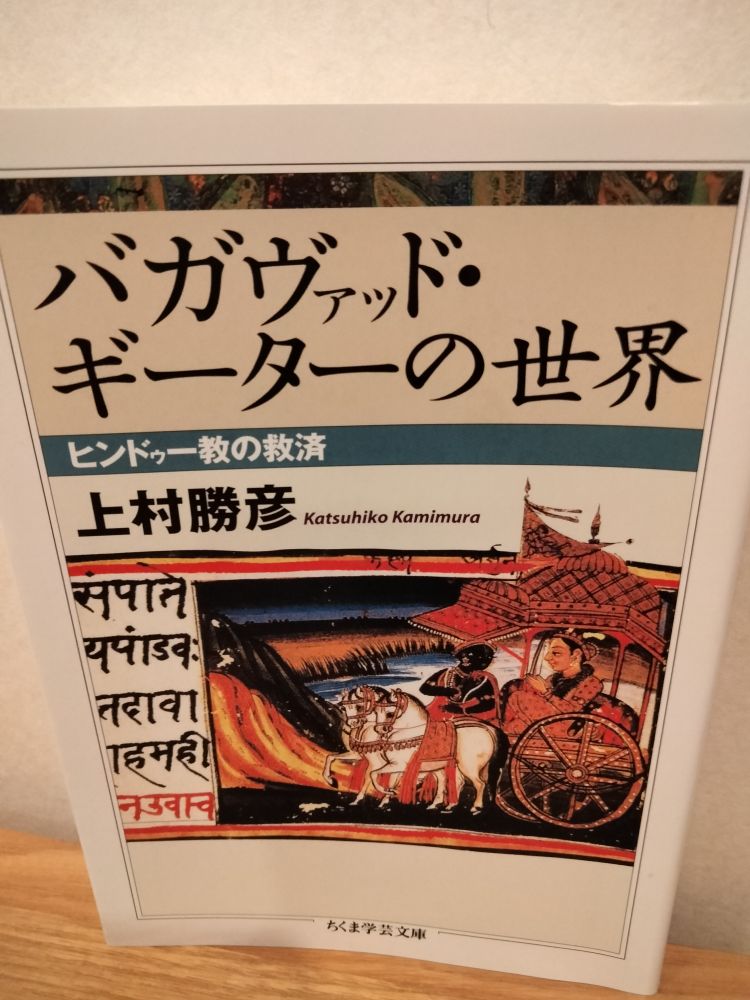
November 9, 2025 at 7:35 AM
上村勝彦『バガヴァッド・ギーターの世界』2007年
岩波文庫での訳者である著者が、1995年のNHK講座テキストを底盤に同書の解説を数行毎に付した労書です。
紀元後一世紀前後のインドにはアートマン(自己)の内にブラフマン(至高存在)があり、そこには神々をはじめとする一切が在するという思想が定着していた事が解ります。この考えは大乗仏教に取り入れられて、日本仏教の本覚思想へと連なります。
仏教経典を絡めてのサンスクリット語原文解説を平易に行っている所に凄味があります。
物語は、顕現するカーラ(時間・運命・死を司る神)が『マハーバーラタ』という叙事詩自体の主軸を伴う事が神話を醸しています。
岩波文庫での訳者である著者が、1995年のNHK講座テキストを底盤に同書の解説を数行毎に付した労書です。
紀元後一世紀前後のインドにはアートマン(自己)の内にブラフマン(至高存在)があり、そこには神々をはじめとする一切が在するという思想が定着していた事が解ります。この考えは大乗仏教に取り入れられて、日本仏教の本覚思想へと連なります。
仏教経典を絡めてのサンスクリット語原文解説を平易に行っている所に凄味があります。
物語は、顕現するカーラ(時間・運命・死を司る神)が『マハーバーラタ』という叙事詩自体の主軸を伴う事が神話を醸しています。
山際素男『マハーバーラタ インド千夜一夜物語』2002年
古代インドの大叙事詩から16篇を完訳版の訳者がセレクトしています。本筋は壮大な相続闘争で世界が滅亡寸前にまで陥るらしいのですが、ここでは枝葉にあたる説話や神話を中心に紹介されています。
面白かったエピソードとしては「死神ヤマを誑かした女」が随一ですね。仏教では夜摩=閻魔大王になるのですが、ここでは印象が全く違って人間臭くて泥臭いのが神様です。インドラ天(=帝釈天)に至ってはもう小物感がすごくて笑ってしまいます。
インド哲学についても一部の説話で触れられますが、そちらはバガヴァッド・ギーターと呼ばれる説話になるそうです。
古代インドの大叙事詩から16篇を完訳版の訳者がセレクトしています。本筋は壮大な相続闘争で世界が滅亡寸前にまで陥るらしいのですが、ここでは枝葉にあたる説話や神話を中心に紹介されています。
面白かったエピソードとしては「死神ヤマを誑かした女」が随一ですね。仏教では夜摩=閻魔大王になるのですが、ここでは印象が全く違って人間臭くて泥臭いのが神様です。インドラ天(=帝釈天)に至ってはもう小物感がすごくて笑ってしまいます。
インド哲学についても一部の説話で触れられますが、そちらはバガヴァッド・ギーターと呼ばれる説話になるそうです。

November 8, 2025 at 5:13 AM
山際素男『マハーバーラタ インド千夜一夜物語』2002年
古代インドの大叙事詩から16篇を完訳版の訳者がセレクトしています。本筋は壮大な相続闘争で世界が滅亡寸前にまで陥るらしいのですが、ここでは枝葉にあたる説話や神話を中心に紹介されています。
面白かったエピソードとしては「死神ヤマを誑かした女」が随一ですね。仏教では夜摩=閻魔大王になるのですが、ここでは印象が全く違って人間臭くて泥臭いのが神様です。インドラ天(=帝釈天)に至ってはもう小物感がすごくて笑ってしまいます。
インド哲学についても一部の説話で触れられますが、そちらはバガヴァッド・ギーターと呼ばれる説話になるそうです。
古代インドの大叙事詩から16篇を完訳版の訳者がセレクトしています。本筋は壮大な相続闘争で世界が滅亡寸前にまで陥るらしいのですが、ここでは枝葉にあたる説話や神話を中心に紹介されています。
面白かったエピソードとしては「死神ヤマを誑かした女」が随一ですね。仏教では夜摩=閻魔大王になるのですが、ここでは印象が全く違って人間臭くて泥臭いのが神様です。インドラ天(=帝釈天)に至ってはもう小物感がすごくて笑ってしまいます。
インド哲学についても一部の説話で触れられますが、そちらはバガヴァッド・ギーターと呼ばれる説話になるそうです。
イタロ・カルヴィーノ/須賀敦子[訳]『なぜ古典を読むのか』2012年
著者の「古典文学」に関する各所寄稿文を一冊にまとめた書評作家論です。
表題の文学論の噛み締める内容にトキメキますが、書評は唯一「懐疑主義と科学と文学が一体であると理解した」とレーモン・クノーに評されたフローベールの『三つの物語』が機会があれば読みたいと思えたくらいです。
以下、14の古典定義の中で好きなひとつを抜粋。
「古典とは、読んでそれが好きになった人にとって、ひとつの豊かさとなる本だ。しかし、これを、よりよい条件で初めて味わう幸運にまだめぐりあっていない人間にとっても、同じくらい重要な資産だ。」
著者の「古典文学」に関する各所寄稿文を一冊にまとめた書評作家論です。
表題の文学論の噛み締める内容にトキメキますが、書評は唯一「懐疑主義と科学と文学が一体であると理解した」とレーモン・クノーに評されたフローベールの『三つの物語』が機会があれば読みたいと思えたくらいです。
以下、14の古典定義の中で好きなひとつを抜粋。
「古典とは、読んでそれが好きになった人にとって、ひとつの豊かさとなる本だ。しかし、これを、よりよい条件で初めて味わう幸運にまだめぐりあっていない人間にとっても、同じくらい重要な資産だ。」

November 6, 2025 at 11:27 AM
イタロ・カルヴィーノ/須賀敦子[訳]『なぜ古典を読むのか』2012年
著者の「古典文学」に関する各所寄稿文を一冊にまとめた書評作家論です。
表題の文学論の噛み締める内容にトキメキますが、書評は唯一「懐疑主義と科学と文学が一体であると理解した」とレーモン・クノーに評されたフローベールの『三つの物語』が機会があれば読みたいと思えたくらいです。
以下、14の古典定義の中で好きなひとつを抜粋。
「古典とは、読んでそれが好きになった人にとって、ひとつの豊かさとなる本だ。しかし、これを、よりよい条件で初めて味わう幸運にまだめぐりあっていない人間にとっても、同じくらい重要な資産だ。」
著者の「古典文学」に関する各所寄稿文を一冊にまとめた書評作家論です。
表題の文学論の噛み締める内容にトキメキますが、書評は唯一「懐疑主義と科学と文学が一体であると理解した」とレーモン・クノーに評されたフローベールの『三つの物語』が機会があれば読みたいと思えたくらいです。
以下、14の古典定義の中で好きなひとつを抜粋。
「古典とは、読んでそれが好きになった人にとって、ひとつの豊かさとなる本だ。しかし、これを、よりよい条件で初めて味わう幸運にまだめぐりあっていない人間にとっても、同じくらい重要な資産だ。」
古市憲寿『謎とき 世界の宗教・神話』2023年
キリスト教、ロシア正教、イスラム教、ゾロアスター教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、儒教、密教、北欧神話、万葉集(?)、日本仏教、古代宗教の各専門家と著者(聞き手)との対談集です。前作『10分で名著』からの第二弾になります。
広くて浅いけれど「なるほど!そういうことなのね」とツボだけ押さえた入門書としてとても良いと思います。
私の場合は宗教よりも神話の方に興味があったのですけれど、一挙両得ということで丁度いい一冊でした。
巻末に世界宗教史がコンパクトにまとめてあるのが案外役に立ちました。世界史忘れかけていたので…。
キリスト教、ロシア正教、イスラム教、ゾロアスター教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、儒教、密教、北欧神話、万葉集(?)、日本仏教、古代宗教の各専門家と著者(聞き手)との対談集です。前作『10分で名著』からの第二弾になります。
広くて浅いけれど「なるほど!そういうことなのね」とツボだけ押さえた入門書としてとても良いと思います。
私の場合は宗教よりも神話の方に興味があったのですけれど、一挙両得ということで丁度いい一冊でした。
巻末に世界宗教史がコンパクトにまとめてあるのが案外役に立ちました。世界史忘れかけていたので…。

November 5, 2025 at 11:43 AM
古市憲寿『謎とき 世界の宗教・神話』2023年
キリスト教、ロシア正教、イスラム教、ゾロアスター教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、儒教、密教、北欧神話、万葉集(?)、日本仏教、古代宗教の各専門家と著者(聞き手)との対談集です。前作『10分で名著』からの第二弾になります。
広くて浅いけれど「なるほど!そういうことなのね」とツボだけ押さえた入門書としてとても良いと思います。
私の場合は宗教よりも神話の方に興味があったのですけれど、一挙両得ということで丁度いい一冊でした。
巻末に世界宗教史がコンパクトにまとめてあるのが案外役に立ちました。世界史忘れかけていたので…。
キリスト教、ロシア正教、イスラム教、ゾロアスター教、ヒンドゥー教、ジャイナ教、儒教、密教、北欧神話、万葉集(?)、日本仏教、古代宗教の各専門家と著者(聞き手)との対談集です。前作『10分で名著』からの第二弾になります。
広くて浅いけれど「なるほど!そういうことなのね」とツボだけ押さえた入門書としてとても良いと思います。
私の場合は宗教よりも神話の方に興味があったのですけれど、一挙両得ということで丁度いい一冊でした。
巻末に世界宗教史がコンパクトにまとめてあるのが案外役に立ちました。世界史忘れかけていたので…。
小川仁志『ジブリアニメで哲学する』2017年
取り上げられているものは宮崎駿監督作品オンリーなのが解せないところではありますが、世間的にジブリ=宮崎駿だという事はわかります。
本当に本編のみでの考察なんでしょう。フォークロア抜きの『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』とマルクス主義抜きの『紅の豚』『もののけ姫』には考察に深みが感じられませんでした。
逆に『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』の考察は面白かったです。
いやはや「これはね…」と絶対的な一つの答えを提示することなく、多くの人が様々な考え方をする所が作品の良さだと思うのです。
取り上げられているものは宮崎駿監督作品オンリーなのが解せないところではありますが、世間的にジブリ=宮崎駿だという事はわかります。
本当に本編のみでの考察なんでしょう。フォークロア抜きの『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』とマルクス主義抜きの『紅の豚』『もののけ姫』には考察に深みが感じられませんでした。
逆に『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』の考察は面白かったです。
いやはや「これはね…」と絶対的な一つの答えを提示することなく、多くの人が様々な考え方をする所が作品の良さだと思うのです。

November 5, 2025 at 4:30 AM
小川仁志『ジブリアニメで哲学する』2017年
取り上げられているものは宮崎駿監督作品オンリーなのが解せないところではありますが、世間的にジブリ=宮崎駿だという事はわかります。
本当に本編のみでの考察なんでしょう。フォークロア抜きの『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』とマルクス主義抜きの『紅の豚』『もののけ姫』には考察に深みが感じられませんでした。
逆に『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』の考察は面白かったです。
いやはや「これはね…」と絶対的な一つの答えを提示することなく、多くの人が様々な考え方をする所が作品の良さだと思うのです。
取り上げられているものは宮崎駿監督作品オンリーなのが解せないところではありますが、世間的にジブリ=宮崎駿だという事はわかります。
本当に本編のみでの考察なんでしょう。フォークロア抜きの『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』とマルクス主義抜きの『紅の豚』『もののけ姫』には考察に深みが感じられませんでした。
逆に『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』の考察は面白かったです。
いやはや「これはね…」と絶対的な一つの答えを提示することなく、多くの人が様々な考え方をする所が作品の良さだと思うのです。
アタモト『タヌキとキツネ 小さな友達』『〃 冬のおはなし』『〃 ちびっこの冒険』2020年〜2021年
長文に次ぐ長文に困憊して絵本を読むのでした。
タヌキはマイペース。
キツネは好奇心旺盛。
かわいい絵とやさしい文。
ナカヨキコトハウツクシキコトカナ
長文に次ぐ長文に困憊して絵本を読むのでした。
タヌキはマイペース。
キツネは好奇心旺盛。
かわいい絵とやさしい文。
ナカヨキコトハウツクシキコトカナ

November 4, 2025 at 10:10 AM
アタモト『タヌキとキツネ 小さな友達』『〃 冬のおはなし』『〃 ちびっこの冒険』2020年〜2021年
長文に次ぐ長文に困憊して絵本を読むのでした。
タヌキはマイペース。
キツネは好奇心旺盛。
かわいい絵とやさしい文。
ナカヨキコトハウツクシキコトカナ
長文に次ぐ長文に困憊して絵本を読むのでした。
タヌキはマイペース。
キツネは好奇心旺盛。
かわいい絵とやさしい文。
ナカヨキコトハウツクシキコトカナ
ミヒャエル・エンデ/田村都志夫[訳]『エンデのメモ帳』2013年
雑文短編百十数点から著者を読み解く一冊です。
エッセンスとしては人間、美、ユーモアが挙げられます。なんだか小林賢太郎と発想法が似ているなあと思いました。具体的には問の立て方です。美について「絵が鑑賞者の内に起こすプロセスが大切」と述べる事からも問を中心とする感があります。
逆に解については煙に巻くように掴みかねます。これはヘーゲルの弁証法に思えます。
「そもそも読者に詩人を理解する義務があるのでしょうか?あるいは詩人に読者が理解できるように書く義務があるのでしょうか?」
やはり読者に精読を通して考えさせたいみたいです。
雑文短編百十数点から著者を読み解く一冊です。
エッセンスとしては人間、美、ユーモアが挙げられます。なんだか小林賢太郎と発想法が似ているなあと思いました。具体的には問の立て方です。美について「絵が鑑賞者の内に起こすプロセスが大切」と述べる事からも問を中心とする感があります。
逆に解については煙に巻くように掴みかねます。これはヘーゲルの弁証法に思えます。
「そもそも読者に詩人を理解する義務があるのでしょうか?あるいは詩人に読者が理解できるように書く義務があるのでしょうか?」
やはり読者に精読を通して考えさせたいみたいです。

November 4, 2025 at 7:15 AM
ミヒャエル・エンデ/田村都志夫[訳]『エンデのメモ帳』2013年
雑文短編百十数点から著者を読み解く一冊です。
エッセンスとしては人間、美、ユーモアが挙げられます。なんだか小林賢太郎と発想法が似ているなあと思いました。具体的には問の立て方です。美について「絵が鑑賞者の内に起こすプロセスが大切」と述べる事からも問を中心とする感があります。
逆に解については煙に巻くように掴みかねます。これはヘーゲルの弁証法に思えます。
「そもそも読者に詩人を理解する義務があるのでしょうか?あるいは詩人に読者が理解できるように書く義務があるのでしょうか?」
やはり読者に精読を通して考えさせたいみたいです。
雑文短編百十数点から著者を読み解く一冊です。
エッセンスとしては人間、美、ユーモアが挙げられます。なんだか小林賢太郎と発想法が似ているなあと思いました。具体的には問の立て方です。美について「絵が鑑賞者の内に起こすプロセスが大切」と述べる事からも問を中心とする感があります。
逆に解については煙に巻くように掴みかねます。これはヘーゲルの弁証法に思えます。
「そもそも読者に詩人を理解する義務があるのでしょうか?あるいは詩人に読者が理解できるように書く義務があるのでしょうか?」
やはり読者に精読を通して考えさせたいみたいです。
酒井敏/小木曽哲/山内裕/那須耕介/川上浩司/神川龍馬/対談・山極寿一と越前屋俵太『京大変人講座』2019年
2017年からの公開講座をベースに書籍化。
【地球岩石学】学校では教えてくれない!恐怖の「地球46億史」
【サービス経営学】「お客さまは神さま」ではない!
【法哲学】安心、安全が人類を滅ぼす
【システム工学】人は「不便」じゃないと萌えない
【進化生物学】“単細胞生物”から、進化の極みが見えてくる
【地球物理学】未来はわからないけど、なるようになっている
経営サービス学がきっかけで手にしましたが、どれも興味深く、面白くて、わかりやすいです。これは良いものです。
2017年からの公開講座をベースに書籍化。
【地球岩石学】学校では教えてくれない!恐怖の「地球46億史」
【サービス経営学】「お客さまは神さま」ではない!
【法哲学】安心、安全が人類を滅ぼす
【システム工学】人は「不便」じゃないと萌えない
【進化生物学】“単細胞生物”から、進化の極みが見えてくる
【地球物理学】未来はわからないけど、なるようになっている
経営サービス学がきっかけで手にしましたが、どれも興味深く、面白くて、わかりやすいです。これは良いものです。

November 3, 2025 at 2:22 PM
酒井敏/小木曽哲/山内裕/那須耕介/川上浩司/神川龍馬/対談・山極寿一と越前屋俵太『京大変人講座』2019年
2017年からの公開講座をベースに書籍化。
【地球岩石学】学校では教えてくれない!恐怖の「地球46億史」
【サービス経営学】「お客さまは神さま」ではない!
【法哲学】安心、安全が人類を滅ぼす
【システム工学】人は「不便」じゃないと萌えない
【進化生物学】“単細胞生物”から、進化の極みが見えてくる
【地球物理学】未来はわからないけど、なるようになっている
経営サービス学がきっかけで手にしましたが、どれも興味深く、面白くて、わかりやすいです。これは良いものです。
2017年からの公開講座をベースに書籍化。
【地球岩石学】学校では教えてくれない!恐怖の「地球46億史」
【サービス経営学】「お客さまは神さま」ではない!
【法哲学】安心、安全が人類を滅ぼす
【システム工学】人は「不便」じゃないと萌えない
【進化生物学】“単細胞生物”から、進化の極みが見えてくる
【地球物理学】未来はわからないけど、なるようになっている
経営サービス学がきっかけで手にしましたが、どれも興味深く、面白くて、わかりやすいです。これは良いものです。
知里幸惠編訳『アイヌ神謡集』1978年
金田一京助による解説によるとアイヌ文学は韻文と散文に分けられるそうです。前者は叙事詩として更に神謡と英雄詞曲に分けられ、神謡は自然神によるユーカラと人格神によるオイナに大別されるとのことです。
現在の視点からするとオチのないような御伽草子ばかりで、註釈の方が興味深い内容でした。
巫女が女性であるのは、高音の方がより遠くまで声が伝わる故というのは(大塚英志も同じ事を述べていた気がします)神聖というよりももっと始原的な理由として面白く思いました。
熊、狼、梟…という序列はロマサガの迷いの森のモチーフとなっていたんだなあと追憶してしまいました。
金田一京助による解説によるとアイヌ文学は韻文と散文に分けられるそうです。前者は叙事詩として更に神謡と英雄詞曲に分けられ、神謡は自然神によるユーカラと人格神によるオイナに大別されるとのことです。
現在の視点からするとオチのないような御伽草子ばかりで、註釈の方が興味深い内容でした。
巫女が女性であるのは、高音の方がより遠くまで声が伝わる故というのは(大塚英志も同じ事を述べていた気がします)神聖というよりももっと始原的な理由として面白く思いました。
熊、狼、梟…という序列はロマサガの迷いの森のモチーフとなっていたんだなあと追憶してしまいました。

November 3, 2025 at 7:11 AM
知里幸惠編訳『アイヌ神謡集』1978年
金田一京助による解説によるとアイヌ文学は韻文と散文に分けられるそうです。前者は叙事詩として更に神謡と英雄詞曲に分けられ、神謡は自然神によるユーカラと人格神によるオイナに大別されるとのことです。
現在の視点からするとオチのないような御伽草子ばかりで、註釈の方が興味深い内容でした。
巫女が女性であるのは、高音の方がより遠くまで声が伝わる故というのは(大塚英志も同じ事を述べていた気がします)神聖というよりももっと始原的な理由として面白く思いました。
熊、狼、梟…という序列はロマサガの迷いの森のモチーフとなっていたんだなあと追憶してしまいました。
金田一京助による解説によるとアイヌ文学は韻文と散文に分けられるそうです。前者は叙事詩として更に神謡と英雄詞曲に分けられ、神謡は自然神によるユーカラと人格神によるオイナに大別されるとのことです。
現在の視点からするとオチのないような御伽草子ばかりで、註釈の方が興味深い内容でした。
巫女が女性であるのは、高音の方がより遠くまで声が伝わる故というのは(大塚英志も同じ事を述べていた気がします)神聖というよりももっと始原的な理由として面白く思いました。
熊、狼、梟…という序列はロマサガの迷いの森のモチーフとなっていたんだなあと追憶してしまいました。
紺野天龍『錬金術師の消失』2020年
本作のテーマは賢者の石。作り方は、水銀と硫黄(硫化水銀)に神霊を加えて錬金釜で焼き上げるそうです。原材料が分かってもレシピの分からないコカ・コーラのようなものでしょうか?
嵐で孤立した中州にそびえ立つ孤塔(絶海の孤島)、密室連続殺人、首の消えた死体と前作を踏まえるとミステリ要素強強の読み応えでした。
設定は特殊だけれど、振り返ると全部伏線張ってある事に愕然とします。むしろ特殊設定が映える展開かと思いましたね。
シリーズとして続きそうな終わり方でしたが、錬金術ガチ設定で展開するには先の解釈が難しい所かなあ。
本作のテーマは賢者の石。作り方は、水銀と硫黄(硫化水銀)に神霊を加えて錬金釜で焼き上げるそうです。原材料が分かってもレシピの分からないコカ・コーラのようなものでしょうか?
嵐で孤立した中州にそびえ立つ孤塔(絶海の孤島)、密室連続殺人、首の消えた死体と前作を踏まえるとミステリ要素強強の読み応えでした。
設定は特殊だけれど、振り返ると全部伏線張ってある事に愕然とします。むしろ特殊設定が映える展開かと思いましたね。
シリーズとして続きそうな終わり方でしたが、錬金術ガチ設定で展開するには先の解釈が難しい所かなあ。
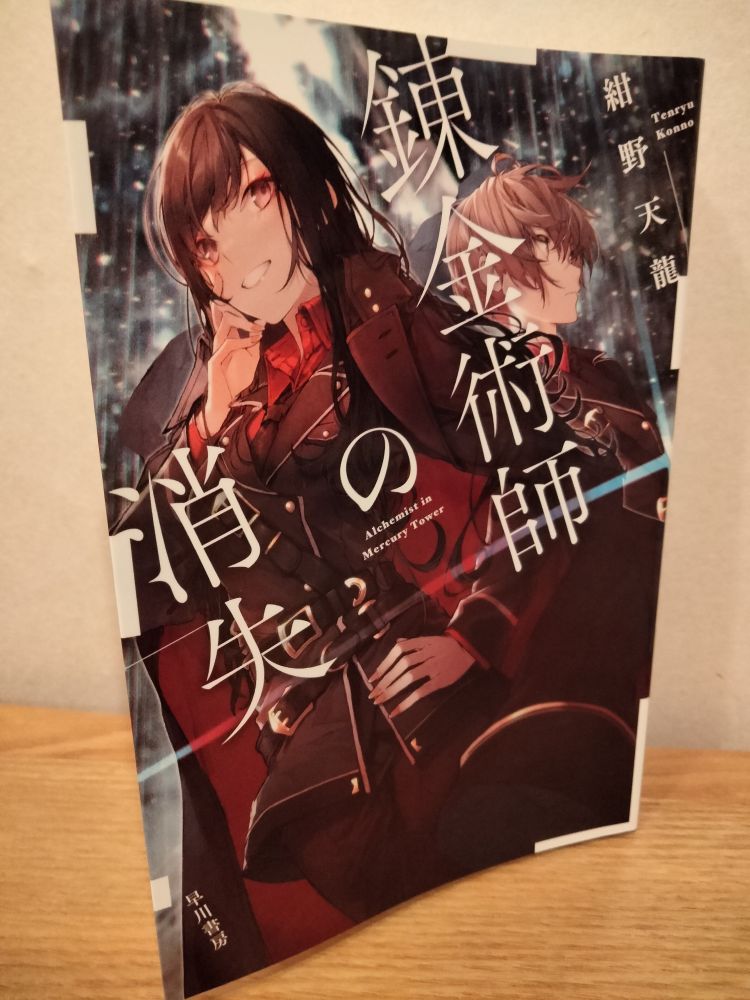
November 2, 2025 at 12:04 PM
紺野天龍『錬金術師の消失』2020年
本作のテーマは賢者の石。作り方は、水銀と硫黄(硫化水銀)に神霊を加えて錬金釜で焼き上げるそうです。原材料が分かってもレシピの分からないコカ・コーラのようなものでしょうか?
嵐で孤立した中州にそびえ立つ孤塔(絶海の孤島)、密室連続殺人、首の消えた死体と前作を踏まえるとミステリ要素強強の読み応えでした。
設定は特殊だけれど、振り返ると全部伏線張ってある事に愕然とします。むしろ特殊設定が映える展開かと思いましたね。
シリーズとして続きそうな終わり方でしたが、錬金術ガチ設定で展開するには先の解釈が難しい所かなあ。
本作のテーマは賢者の石。作り方は、水銀と硫黄(硫化水銀)に神霊を加えて錬金釜で焼き上げるそうです。原材料が分かってもレシピの分からないコカ・コーラのようなものでしょうか?
嵐で孤立した中州にそびえ立つ孤塔(絶海の孤島)、密室連続殺人、首の消えた死体と前作を踏まえるとミステリ要素強強の読み応えでした。
設定は特殊だけれど、振り返ると全部伏線張ってある事に愕然とします。むしろ特殊設定が映える展開かと思いましたね。
シリーズとして続きそうな終わり方でしたが、錬金術ガチ設定で展開するには先の解釈が難しい所かなあ。
紺野天龍『錬金術師の密室』2020年
ドラゴンボールのように死んでも生き返る事が日常的となると不老不死の価値はどれくらいあるのか?と思ってしまう所ですが、錬金術とは魂の解明を通して神の観測を目的とした神学になります。なので理論構築の点で言えばSFかと思いますね。
前半における小説のふりをした錬金術の解説を読むと「ホムンクルスとアンドロイドの違いとは?」とか「サイボーグとリジェネーターだったら?」など思索が去来します。
あと、貴金属の対義語として卑金属と言われると『聖痕のクェイサー』が思い浮かびます。天賦の才が全ての世界ってこわいなあ。
ミステリとして読むと本作は邪道ですね。
ドラゴンボールのように死んでも生き返る事が日常的となると不老不死の価値はどれくらいあるのか?と思ってしまう所ですが、錬金術とは魂の解明を通して神の観測を目的とした神学になります。なので理論構築の点で言えばSFかと思いますね。
前半における小説のふりをした錬金術の解説を読むと「ホムンクルスとアンドロイドの違いとは?」とか「サイボーグとリジェネーターだったら?」など思索が去来します。
あと、貴金属の対義語として卑金属と言われると『聖痕のクェイサー』が思い浮かびます。天賦の才が全ての世界ってこわいなあ。
ミステリとして読むと本作は邪道ですね。

November 2, 2025 at 5:02 AM
紺野天龍『錬金術師の密室』2020年
ドラゴンボールのように死んでも生き返る事が日常的となると不老不死の価値はどれくらいあるのか?と思ってしまう所ですが、錬金術とは魂の解明を通して神の観測を目的とした神学になります。なので理論構築の点で言えばSFかと思いますね。
前半における小説のふりをした錬金術の解説を読むと「ホムンクルスとアンドロイドの違いとは?」とか「サイボーグとリジェネーターだったら?」など思索が去来します。
あと、貴金属の対義語として卑金属と言われると『聖痕のクェイサー』が思い浮かびます。天賦の才が全ての世界ってこわいなあ。
ミステリとして読むと本作は邪道ですね。
ドラゴンボールのように死んでも生き返る事が日常的となると不老不死の価値はどれくらいあるのか?と思ってしまう所ですが、錬金術とは魂の解明を通して神の観測を目的とした神学になります。なので理論構築の点で言えばSFかと思いますね。
前半における小説のふりをした錬金術の解説を読むと「ホムンクルスとアンドロイドの違いとは?」とか「サイボーグとリジェネーターだったら?」など思索が去来します。
あと、貴金属の対義語として卑金属と言われると『聖痕のクェイサー』が思い浮かびます。天賦の才が全ての世界ってこわいなあ。
ミステリとして読むと本作は邪道ですね。
五条紀夫『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』2025年
言わずと知れた太宰治の『走れメロス』を題材とした特殊ミステリーです。
古代ギリシャの雑学が満載なのでパロディ以上の面白さがあります。熱海事件を題材としたエピソードには抱腹絶倒です。
メロスの半分は正義の心でできていますが、もう半分はフィジカルなので、正義の鉄槌その人です。つまり脳筋探偵なのです。(笑)
「よし、分かった。事件を解決しようではないか。皆、一列に並べ!犯人はすぐ名乗り出ろ。名乗り出ないのであれば、右から順に一人ずつ殴っていく!」
もう「ちょwwwおまwwww」が最後まで止まらない面白さに(笑)
言わずと知れた太宰治の『走れメロス』を題材とした特殊ミステリーです。
古代ギリシャの雑学が満載なのでパロディ以上の面白さがあります。熱海事件を題材としたエピソードには抱腹絶倒です。
メロスの半分は正義の心でできていますが、もう半分はフィジカルなので、正義の鉄槌その人です。つまり脳筋探偵なのです。(笑)
「よし、分かった。事件を解決しようではないか。皆、一列に並べ!犯人はすぐ名乗り出ろ。名乗り出ないのであれば、右から順に一人ずつ殴っていく!」
もう「ちょwwwおまwwww」が最後まで止まらない面白さに(笑)

November 1, 2025 at 6:25 AM
五条紀夫『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』2025年
言わずと知れた太宰治の『走れメロス』を題材とした特殊ミステリーです。
古代ギリシャの雑学が満載なのでパロディ以上の面白さがあります。熱海事件を題材としたエピソードには抱腹絶倒です。
メロスの半分は正義の心でできていますが、もう半分はフィジカルなので、正義の鉄槌その人です。つまり脳筋探偵なのです。(笑)
「よし、分かった。事件を解決しようではないか。皆、一列に並べ!犯人はすぐ名乗り出ろ。名乗り出ないのであれば、右から順に一人ずつ殴っていく!」
もう「ちょwwwおまwwww」が最後まで止まらない面白さに(笑)
言わずと知れた太宰治の『走れメロス』を題材とした特殊ミステリーです。
古代ギリシャの雑学が満載なのでパロディ以上の面白さがあります。熱海事件を題材としたエピソードには抱腹絶倒です。
メロスの半分は正義の心でできていますが、もう半分はフィジカルなので、正義の鉄槌その人です。つまり脳筋探偵なのです。(笑)
「よし、分かった。事件を解決しようではないか。皆、一列に並べ!犯人はすぐ名乗り出ろ。名乗り出ないのであれば、右から順に一人ずつ殴っていく!」
もう「ちょwwwおまwwww」が最後まで止まらない面白さに(笑)
今月の読了は16冊で、15冊の購入でした。よき。

October 31, 2025 at 2:10 PM
今月の読了は16冊で、15冊の購入でした。よき。
西尾維新『接物語』2025年
物語シリーズ第…何弾?三十数冊目くらい?第九十九話「よつぎフランク」は斧乃木余接が付喪神という設定(忘れ去っていました)からの99ですね。本作の語り部は忍野メメ、お久しぶりです。20年振りくらいの登場ですね。珍しく雑談小説として道を外れた脱線しない語り部でした。
7年前を前日譚と言って良いものかという疑問はありますが、スピンオフとしてアナザーサイドとしてのエピソードゼロですね。本編での助演オールスターズが勢揃いという、キャラクター小説としてのある意味豪華なキャスティングにwktkしてしまいます。
本編の伏線回収として明かされた物語として、想定外の物語でした。
物語シリーズ第…何弾?三十数冊目くらい?第九十九話「よつぎフランク」は斧乃木余接が付喪神という設定(忘れ去っていました)からの99ですね。本作の語り部は忍野メメ、お久しぶりです。20年振りくらいの登場ですね。珍しく雑談小説として道を外れた脱線しない語り部でした。
7年前を前日譚と言って良いものかという疑問はありますが、スピンオフとしてアナザーサイドとしてのエピソードゼロですね。本編での助演オールスターズが勢揃いという、キャラクター小説としてのある意味豪華なキャスティングにwktkしてしまいます。
本編の伏線回収として明かされた物語として、想定外の物語でした。

October 31, 2025 at 2:06 PM
西尾維新『接物語』2025年
物語シリーズ第…何弾?三十数冊目くらい?第九十九話「よつぎフランク」は斧乃木余接が付喪神という設定(忘れ去っていました)からの99ですね。本作の語り部は忍野メメ、お久しぶりです。20年振りくらいの登場ですね。珍しく雑談小説として道を外れた脱線しない語り部でした。
7年前を前日譚と言って良いものかという疑問はありますが、スピンオフとしてアナザーサイドとしてのエピソードゼロですね。本編での助演オールスターズが勢揃いという、キャラクター小説としてのある意味豪華なキャスティングにwktkしてしまいます。
本編の伏線回収として明かされた物語として、想定外の物語でした。
物語シリーズ第…何弾?三十数冊目くらい?第九十九話「よつぎフランク」は斧乃木余接が付喪神という設定(忘れ去っていました)からの99ですね。本作の語り部は忍野メメ、お久しぶりです。20年振りくらいの登場ですね。珍しく雑談小説として道を外れた脱線しない語り部でした。
7年前を前日譚と言って良いものかという疑問はありますが、スピンオフとしてアナザーサイドとしてのエピソードゼロですね。本編での助演オールスターズが勢揃いという、キャラクター小説としてのある意味豪華なキャスティングにwktkしてしまいます。
本編の伏線回収として明かされた物語として、想定外の物語でした。
ど 憧憬☆カトマンズ
く 空気の発見
し シンボルの哲学
よ (読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法
の 脳は世界をどう見ているのか
あ 新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書
き きみとぼくの壊れた世界
#あなたの本棚のどくしょのあき
く 空気の発見
し シンボルの哲学
よ (読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法
の 脳は世界をどう見ているのか
あ 新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書
き きみとぼくの壊れた世界
#あなたの本棚のどくしょのあき

October 29, 2025 at 10:45 AM
ど 憧憬☆カトマンズ
く 空気の発見
し シンボルの哲学
よ (読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法
の 脳は世界をどう見ているのか
あ 新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書
き きみとぼくの壊れた世界
#あなたの本棚のどくしょのあき
く 空気の発見
し シンボルの哲学
よ (読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法
の 脳は世界をどう見ているのか
あ 新しい「マイケル・ジャクソン」の教科書
き きみとぼくの壊れた世界
#あなたの本棚のどくしょのあき
柚木麻子『ねじまき片想い』2018年
こんなにも恋愛小説に没入できるものとは思っていませんでした。いや、片想いなんですけどね。
安心と信頼の創元推理文庫なのでミステリかと思っていたのですが、謎が浮上するまでそんな事は忘却の彼方にすっ飛んでいたくらいの薄味ミステリの他にもお仕事ドラマとして、女性の友情物語としての要素も多分に詰め込まれているのに塩梅よろしくバランサーとしての手腕が問われる作品と言うよりも読み手の受け取り方次第という所でしょうか?オチはさておき爽やかな印象の小説でした。
本作でも活字で表現される機微の独自性に際して、固有名詞の取り扱いセンスが上手い事に感服しました。
こんなにも恋愛小説に没入できるものとは思っていませんでした。いや、片想いなんですけどね。
安心と信頼の創元推理文庫なのでミステリかと思っていたのですが、謎が浮上するまでそんな事は忘却の彼方にすっ飛んでいたくらいの薄味ミステリの他にもお仕事ドラマとして、女性の友情物語としての要素も多分に詰め込まれているのに塩梅よろしくバランサーとしての手腕が問われる作品と言うよりも読み手の受け取り方次第という所でしょうか?オチはさておき爽やかな印象の小説でした。
本作でも活字で表現される機微の独自性に際して、固有名詞の取り扱いセンスが上手い事に感服しました。

October 27, 2025 at 3:09 PM
柚木麻子『ねじまき片想い』2018年
こんなにも恋愛小説に没入できるものとは思っていませんでした。いや、片想いなんですけどね。
安心と信頼の創元推理文庫なのでミステリかと思っていたのですが、謎が浮上するまでそんな事は忘却の彼方にすっ飛んでいたくらいの薄味ミステリの他にもお仕事ドラマとして、女性の友情物語としての要素も多分に詰め込まれているのに塩梅よろしくバランサーとしての手腕が問われる作品と言うよりも読み手の受け取り方次第という所でしょうか?オチはさておき爽やかな印象の小説でした。
本作でも活字で表現される機微の独自性に際して、固有名詞の取り扱いセンスが上手い事に感服しました。
こんなにも恋愛小説に没入できるものとは思っていませんでした。いや、片想いなんですけどね。
安心と信頼の創元推理文庫なのでミステリかと思っていたのですが、謎が浮上するまでそんな事は忘却の彼方にすっ飛んでいたくらいの薄味ミステリの他にもお仕事ドラマとして、女性の友情物語としての要素も多分に詰め込まれているのに塩梅よろしくバランサーとしての手腕が問われる作品と言うよりも読み手の受け取り方次第という所でしょうか?オチはさておき爽やかな印象の小説でした。
本作でも活字で表現される機微の独自性に際して、固有名詞の取り扱いセンスが上手い事に感服しました。
吉本隆明『宮沢賢治』1996年
詩人、思想家として知られる著者には、宮沢賢治研究者としての一面もありました。
通読してみると『銀河鉄道の夜』を精読する為のという但し書きが註釈されている一冊というような印象を受けます。
作品を読み解くキーワードとしては、日蓮宗と大乗仏教の理念の理解が筆頭に挙げられますが、揺るぎなき信仰者となる以前から心象風景としての目線で世界を掴み取っていたようです。
そこから詩や童話の世界に入ったので「人間関係の内紛や葛藤」が無い代わりに「自然の景観との交歓」が限りない。そこに「紙面の裏すら貫こうとする見えないものを見見る目線」が作品に加えられている点が重要みたいです。
詩人、思想家として知られる著者には、宮沢賢治研究者としての一面もありました。
通読してみると『銀河鉄道の夜』を精読する為のという但し書きが註釈されている一冊というような印象を受けます。
作品を読み解くキーワードとしては、日蓮宗と大乗仏教の理念の理解が筆頭に挙げられますが、揺るぎなき信仰者となる以前から心象風景としての目線で世界を掴み取っていたようです。
そこから詩や童話の世界に入ったので「人間関係の内紛や葛藤」が無い代わりに「自然の景観との交歓」が限りない。そこに「紙面の裏すら貫こうとする見えないものを見見る目線」が作品に加えられている点が重要みたいです。

October 26, 2025 at 10:39 AM
吉本隆明『宮沢賢治』1996年
詩人、思想家として知られる著者には、宮沢賢治研究者としての一面もありました。
通読してみると『銀河鉄道の夜』を精読する為のという但し書きが註釈されている一冊というような印象を受けます。
作品を読み解くキーワードとしては、日蓮宗と大乗仏教の理念の理解が筆頭に挙げられますが、揺るぎなき信仰者となる以前から心象風景としての目線で世界を掴み取っていたようです。
そこから詩や童話の世界に入ったので「人間関係の内紛や葛藤」が無い代わりに「自然の景観との交歓」が限りない。そこに「紙面の裏すら貫こうとする見えないものを見見る目線」が作品に加えられている点が重要みたいです。
詩人、思想家として知られる著者には、宮沢賢治研究者としての一面もありました。
通読してみると『銀河鉄道の夜』を精読する為のという但し書きが註釈されている一冊というような印象を受けます。
作品を読み解くキーワードとしては、日蓮宗と大乗仏教の理念の理解が筆頭に挙げられますが、揺るぎなき信仰者となる以前から心象風景としての目線で世界を掴み取っていたようです。
そこから詩や童話の世界に入ったので「人間関係の内紛や葛藤」が無い代わりに「自然の景観との交歓」が限りない。そこに「紙面の裏すら貫こうとする見えないものを見見る目線」が作品に加えられている点が重要みたいです。
今日は寒雨でもってすこぶる冷え込みの中、屋外で過ごしていました。
「そうだ、お夕飯はお鍋にしよう💡」と春先に新しく出迎えた土鍋を出して、残り物の鍋の素を見ると何日か賞味期限が過ぎていました。まあいいか。
食材を放り込んで日にかけて蒸気が噴いたら半刻ほど放置するだけで調理が終わるなんてマジックアイテムじみてるなあ。
「そうだ、お夕飯はお鍋にしよう💡」と春先に新しく出迎えた土鍋を出して、残り物の鍋の素を見ると何日か賞味期限が過ぎていました。まあいいか。
食材を放り込んで日にかけて蒸気が噴いたら半刻ほど放置するだけで調理が終わるなんてマジックアイテムじみてるなあ。

October 22, 2025 at 11:40 AM
今日は寒雨でもってすこぶる冷え込みの中、屋外で過ごしていました。
「そうだ、お夕飯はお鍋にしよう💡」と春先に新しく出迎えた土鍋を出して、残り物の鍋の素を見ると何日か賞味期限が過ぎていました。まあいいか。
食材を放り込んで日にかけて蒸気が噴いたら半刻ほど放置するだけで調理が終わるなんてマジックアイテムじみてるなあ。
「そうだ、お夕飯はお鍋にしよう💡」と春先に新しく出迎えた土鍋を出して、残り物の鍋の素を見ると何日か賞味期限が過ぎていました。まあいいか。
食材を放り込んで日にかけて蒸気が噴いたら半刻ほど放置するだけで調理が終わるなんてマジックアイテムじみてるなあ。
柳田邦男『砂漠でみつけた一冊の絵本』2025年
2003年「今、おとなこそ絵本を」というキャンペーンを著者が発起人となって打ち出されました。21年を経た絵本にまつわるドキュメンタリー&エッセイの文庫化です。
この背景として著者は「カネとモノを第一とする人々には、詩人は言葉遊びをしているだけに見えるだろう。だが、詩には世界に色彩を加えて生きる力を湧き立たせる言葉を響かせる力がある。心と言葉の危機が人々を覆いつつある今、絵本も詩に劣らぬ心の再生の役割を果たす可能性を秘めていると思う」というような事を述べています。
一行の言葉の力の下には数万文字を超える下地があってこその大人の読み方でした。
2003年「今、おとなこそ絵本を」というキャンペーンを著者が発起人となって打ち出されました。21年を経た絵本にまつわるドキュメンタリー&エッセイの文庫化です。
この背景として著者は「カネとモノを第一とする人々には、詩人は言葉遊びをしているだけに見えるだろう。だが、詩には世界に色彩を加えて生きる力を湧き立たせる言葉を響かせる力がある。心と言葉の危機が人々を覆いつつある今、絵本も詩に劣らぬ心の再生の役割を果たす可能性を秘めていると思う」というような事を述べています。
一行の言葉の力の下には数万文字を超える下地があってこその大人の読み方でした。

October 19, 2025 at 2:16 PM
柳田邦男『砂漠でみつけた一冊の絵本』2025年
2003年「今、おとなこそ絵本を」というキャンペーンを著者が発起人となって打ち出されました。21年を経た絵本にまつわるドキュメンタリー&エッセイの文庫化です。
この背景として著者は「カネとモノを第一とする人々には、詩人は言葉遊びをしているだけに見えるだろう。だが、詩には世界に色彩を加えて生きる力を湧き立たせる言葉を響かせる力がある。心と言葉の危機が人々を覆いつつある今、絵本も詩に劣らぬ心の再生の役割を果たす可能性を秘めていると思う」というような事を述べています。
一行の言葉の力の下には数万文字を超える下地があってこその大人の読み方でした。
2003年「今、おとなこそ絵本を」というキャンペーンを著者が発起人となって打ち出されました。21年を経た絵本にまつわるドキュメンタリー&エッセイの文庫化です。
この背景として著者は「カネとモノを第一とする人々には、詩人は言葉遊びをしているだけに見えるだろう。だが、詩には世界に色彩を加えて生きる力を湧き立たせる言葉を響かせる力がある。心と言葉の危機が人々を覆いつつある今、絵本も詩に劣らぬ心の再生の役割を果たす可能性を秘めていると思う」というような事を述べています。
一行の言葉の力の下には数万文字を超える下地があってこその大人の読み方でした。
三上修『身近な鳥の生活図鑑』2015年
著者は電柱鳥類学という都市部の電柱と電線を生活の拠点としている鳥を専門としているという事を以前ラジオ番組で知って手頃な新書があったので読んでみました。
内容はスズメとハトとカラスの三本柱です。
著者の主張する「身の回りにいる生き物がわからなければ、その価値も感じられません。知らないものが消え去っても何の痛痒も感じません。こういう時代の中で、スズメのようなわかりやすい鳥が身の回りにいることは、とても大切な事だと思うのです」に共感します。
知識としては雑学ですが、季節の移ろいを感じて暮らしに楽しみを見出せるのなら、これもひとつの教養と言えそうです。
著者は電柱鳥類学という都市部の電柱と電線を生活の拠点としている鳥を専門としているという事を以前ラジオ番組で知って手頃な新書があったので読んでみました。
内容はスズメとハトとカラスの三本柱です。
著者の主張する「身の回りにいる生き物がわからなければ、その価値も感じられません。知らないものが消え去っても何の痛痒も感じません。こういう時代の中で、スズメのようなわかりやすい鳥が身の回りにいることは、とても大切な事だと思うのです」に共感します。
知識としては雑学ですが、季節の移ろいを感じて暮らしに楽しみを見出せるのなら、これもひとつの教養と言えそうです。

October 18, 2025 at 5:21 PM
三上修『身近な鳥の生活図鑑』2015年
著者は電柱鳥類学という都市部の電柱と電線を生活の拠点としている鳥を専門としているという事を以前ラジオ番組で知って手頃な新書があったので読んでみました。
内容はスズメとハトとカラスの三本柱です。
著者の主張する「身の回りにいる生き物がわからなければ、その価値も感じられません。知らないものが消え去っても何の痛痒も感じません。こういう時代の中で、スズメのようなわかりやすい鳥が身の回りにいることは、とても大切な事だと思うのです」に共感します。
知識としては雑学ですが、季節の移ろいを感じて暮らしに楽しみを見出せるのなら、これもひとつの教養と言えそうです。
著者は電柱鳥類学という都市部の電柱と電線を生活の拠点としている鳥を専門としているという事を以前ラジオ番組で知って手頃な新書があったので読んでみました。
内容はスズメとハトとカラスの三本柱です。
著者の主張する「身の回りにいる生き物がわからなければ、その価値も感じられません。知らないものが消え去っても何の痛痒も感じません。こういう時代の中で、スズメのようなわかりやすい鳥が身の回りにいることは、とても大切な事だと思うのです」に共感します。
知識としては雑学ですが、季節の移ろいを感じて暮らしに楽しみを見出せるのなら、これもひとつの教養と言えそうです。
クレア・キップス/梨木香歩[訳]『ある小さなスズメの記録 人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯』2015年
障碍によって親鳥に見離された雛雀と彼を拾い育てた老ピアニストの記録、と書くと感動を誘うドキュメンタリーっぽい語感が漂います。
私としては生老病死に対しての感傷的方面ではなく「知的生物には社会構成主義に基づく考え方の形成があるものだなあ」というinterestingの方面で読んでいました。
これは飼主としての従属的矯正を行わないこそ、生活の上での様々な行動実験を試みているあたりの話になります。
とは言え、動物の学習行動としての刷り込みとは強固なものである事が伺えますね。
障碍によって親鳥に見離された雛雀と彼を拾い育てた老ピアニストの記録、と書くと感動を誘うドキュメンタリーっぽい語感が漂います。
私としては生老病死に対しての感傷的方面ではなく「知的生物には社会構成主義に基づく考え方の形成があるものだなあ」というinterestingの方面で読んでいました。
これは飼主としての従属的矯正を行わないこそ、生活の上での様々な行動実験を試みているあたりの話になります。
とは言え、動物の学習行動としての刷り込みとは強固なものである事が伺えますね。

October 18, 2025 at 11:03 AM
クレア・キップス/梨木香歩[訳]『ある小さなスズメの記録 人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯』2015年
障碍によって親鳥に見離された雛雀と彼を拾い育てた老ピアニストの記録、と書くと感動を誘うドキュメンタリーっぽい語感が漂います。
私としては生老病死に対しての感傷的方面ではなく「知的生物には社会構成主義に基づく考え方の形成があるものだなあ」というinterestingの方面で読んでいました。
これは飼主としての従属的矯正を行わないこそ、生活の上での様々な行動実験を試みているあたりの話になります。
とは言え、動物の学習行動としての刷り込みとは強固なものである事が伺えますね。
障碍によって親鳥に見離された雛雀と彼を拾い育てた老ピアニストの記録、と書くと感動を誘うドキュメンタリーっぽい語感が漂います。
私としては生老病死に対しての感傷的方面ではなく「知的生物には社会構成主義に基づく考え方の形成があるものだなあ」というinterestingの方面で読んでいました。
これは飼主としての従属的矯正を行わないこそ、生活の上での様々な行動実験を試みているあたりの話になります。
とは言え、動物の学習行動としての刷り込みとは強固なものである事が伺えますね。
冨原眞弓『ムーミン谷のひみつ』2008年
シリーズから特徴的なエピソードを選び出し、キャラクターごとに解説した入門書です。ムーミンエコバッグ(もらいもの)を長年使っていますが、作品をあまり知らなかったもので…。
驚いたことに、ほとんど全てのキャラクターの名前は固有名ではなく種族名か通り名でした。
それと程度の違いこそあれ各位「自分にしか興味がない」という内面性が意外です。
そうすると個性的というより属性的、世界観としては『インサイド・ヘッド』に近い気がします。
作者トーベ・ヤンソンのアルカディアはブルジョアとボヘミアン、審美と実利など対が渾然一体とした複雑な世界でした。
シリーズから特徴的なエピソードを選び出し、キャラクターごとに解説した入門書です。ムーミンエコバッグ(もらいもの)を長年使っていますが、作品をあまり知らなかったもので…。
驚いたことに、ほとんど全てのキャラクターの名前は固有名ではなく種族名か通り名でした。
それと程度の違いこそあれ各位「自分にしか興味がない」という内面性が意外です。
そうすると個性的というより属性的、世界観としては『インサイド・ヘッド』に近い気がします。
作者トーベ・ヤンソンのアルカディアはブルジョアとボヘミアン、審美と実利など対が渾然一体とした複雑な世界でした。

October 18, 2025 at 6:02 AM
冨原眞弓『ムーミン谷のひみつ』2008年
シリーズから特徴的なエピソードを選び出し、キャラクターごとに解説した入門書です。ムーミンエコバッグ(もらいもの)を長年使っていますが、作品をあまり知らなかったもので…。
驚いたことに、ほとんど全てのキャラクターの名前は固有名ではなく種族名か通り名でした。
それと程度の違いこそあれ各位「自分にしか興味がない」という内面性が意外です。
そうすると個性的というより属性的、世界観としては『インサイド・ヘッド』に近い気がします。
作者トーベ・ヤンソンのアルカディアはブルジョアとボヘミアン、審美と実利など対が渾然一体とした複雑な世界でした。
シリーズから特徴的なエピソードを選び出し、キャラクターごとに解説した入門書です。ムーミンエコバッグ(もらいもの)を長年使っていますが、作品をあまり知らなかったもので…。
驚いたことに、ほとんど全てのキャラクターの名前は固有名ではなく種族名か通り名でした。
それと程度の違いこそあれ各位「自分にしか興味がない」という内面性が意外です。
そうすると個性的というより属性的、世界観としては『インサイド・ヘッド』に近い気がします。
作者トーベ・ヤンソンのアルカディアはブルジョアとボヘミアン、審美と実利など対が渾然一体とした複雑な世界でした。
阿刀田高『アラビアンナイトを楽しむために』昭和61年
バートン版千夜一夜物語の副読本のような一冊です。ガリバーは愚か者という意味らしいですが、こちらに出てくる人物の方がそれらしいと言いますか、粗忽者と言いますか「石のほうが多い玉石混淆(例外の方が多いルールブックに語感が似て念能力みたいだ)」という感じでした。
40という数字は中東では「いっぱい」という意味らしいです。日本では千、トルコだと千一ですね。
「インシャラー(何事も神様の思し召し)」が全ての根底にあって、逸話が事実か否かも「神のみぞ知る」だそうです。
バートン版千夜一夜物語の副読本のような一冊です。ガリバーは愚か者という意味らしいですが、こちらに出てくる人物の方がそれらしいと言いますか、粗忽者と言いますか「石のほうが多い玉石混淆(例外の方が多いルールブックに語感が似て念能力みたいだ)」という感じでした。
40という数字は中東では「いっぱい」という意味らしいです。日本では千、トルコだと千一ですね。
「インシャラー(何事も神様の思し召し)」が全ての根底にあって、逸話が事実か否かも「神のみぞ知る」だそうです。

October 14, 2025 at 12:16 PM
阿刀田高『アラビアンナイトを楽しむために』昭和61年
バートン版千夜一夜物語の副読本のような一冊です。ガリバーは愚か者という意味らしいですが、こちらに出てくる人物の方がそれらしいと言いますか、粗忽者と言いますか「石のほうが多い玉石混淆(例外の方が多いルールブックに語感が似て念能力みたいだ)」という感じでした。
40という数字は中東では「いっぱい」という意味らしいです。日本では千、トルコだと千一ですね。
「インシャラー(何事も神様の思し召し)」が全ての根底にあって、逸話が事実か否かも「神のみぞ知る」だそうです。
バートン版千夜一夜物語の副読本のような一冊です。ガリバーは愚か者という意味らしいですが、こちらに出てくる人物の方がそれらしいと言いますか、粗忽者と言いますか「石のほうが多い玉石混淆(例外の方が多いルールブックに語感が似て念能力みたいだ)」という感じでした。
40という数字は中東では「いっぱい」という意味らしいです。日本では千、トルコだと千一ですね。
「インシャラー(何事も神様の思し召し)」が全ての根底にあって、逸話が事実か否かも「神のみぞ知る」だそうです。
阿刀田高『あなたの知らないガリバー旅行記』昭和63年
ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記の解説本です。正しくは『ルミュエル・ガリバー著・世界のさまざまな遠方民族への旅』で「リリパット国渡航記」「ブロブディンナグ国渡航記」「ラピュータ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップおよび日本への渡航記」「フウイヌム国渡航記」の四部構成で、実話である体裁を装っているのだそう。
実際には冒険譚ではなく風刺小説であって、人間の根源的部分では今も昔も変わらない事が伺えます。
解説と共に与太話から学ぶ事も多いのですが、何か実生活の役に立つかと言われると何の訳にも立たない所が良いのですよね。
ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記の解説本です。正しくは『ルミュエル・ガリバー著・世界のさまざまな遠方民族への旅』で「リリパット国渡航記」「ブロブディンナグ国渡航記」「ラピュータ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップおよび日本への渡航記」「フウイヌム国渡航記」の四部構成で、実話である体裁を装っているのだそう。
実際には冒険譚ではなく風刺小説であって、人間の根源的部分では今も昔も変わらない事が伺えます。
解説と共に与太話から学ぶ事も多いのですが、何か実生活の役に立つかと言われると何の訳にも立たない所が良いのですよね。

October 14, 2025 at 4:13 AM
阿刀田高『あなたの知らないガリバー旅行記』昭和63年
ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記の解説本です。正しくは『ルミュエル・ガリバー著・世界のさまざまな遠方民族への旅』で「リリパット国渡航記」「ブロブディンナグ国渡航記」「ラピュータ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップおよび日本への渡航記」「フウイヌム国渡航記」の四部構成で、実話である体裁を装っているのだそう。
実際には冒険譚ではなく風刺小説であって、人間の根源的部分では今も昔も変わらない事が伺えます。
解説と共に与太話から学ぶ事も多いのですが、何か実生活の役に立つかと言われると何の訳にも立たない所が良いのですよね。
ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記の解説本です。正しくは『ルミュエル・ガリバー著・世界のさまざまな遠方民族への旅』で「リリパット国渡航記」「ブロブディンナグ国渡航記」「ラピュータ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップおよび日本への渡航記」「フウイヌム国渡航記」の四部構成で、実話である体裁を装っているのだそう。
実際には冒険譚ではなく風刺小説であって、人間の根源的部分では今も昔も変わらない事が伺えます。
解説と共に与太話から学ぶ事も多いのですが、何か実生活の役に立つかと言われると何の訳にも立たない所が良いのですよね。

