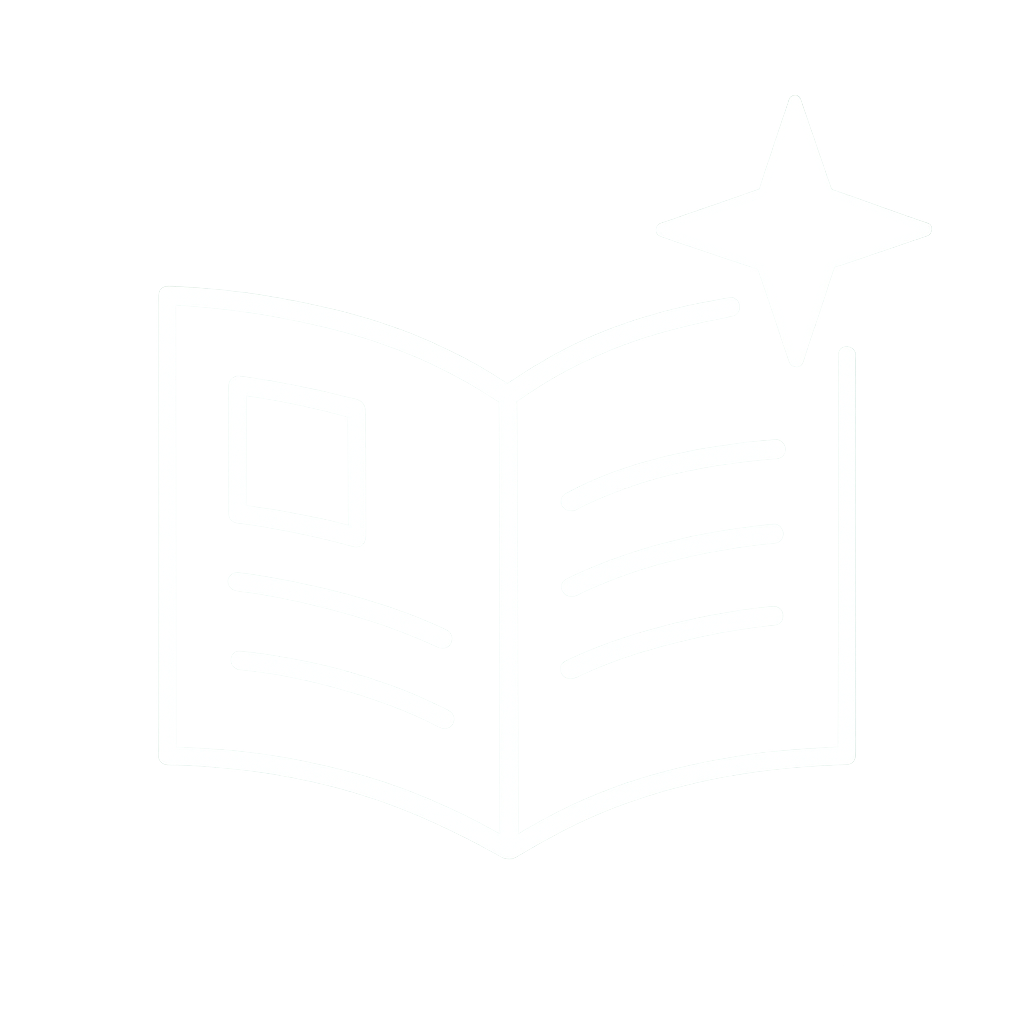好きな文章、気になる文章をここに集めてます。(Threads:https://www.threads.com/@wanwan65537 では本にまつわる話を投稿中)
「世界がまだ若く、五世紀ほどもまえのころには、人生の出来事は、いまよりももっとくっきりとしたかたちをみせていた。悲しみと喜びのあいだの、幸と不幸のあいだのへだたりは、わたしたちの場合よりも大きかったようだ。すべて、ひとの体験には、喜び悲しむ子供の心にいまなおうかがえる、あの直接性、絶対性が、まだ失われてはいなかった。」
(ホイジンガ『中世の秋(上)』堀越孝一訳、中公文庫、1976、p.11)

「世界がまだ若く、五世紀ほどもまえのころには、人生の出来事は、いまよりももっとくっきりとしたかたちをみせていた。悲しみと喜びのあいだの、幸と不幸のあいだのへだたりは、わたしたちの場合よりも大きかったようだ。すべて、ひとの体験には、喜び悲しむ子供の心にいまなおうかがえる、あの直接性、絶対性が、まだ失われてはいなかった。」
(ホイジンガ『中世の秋(上)』堀越孝一訳、中公文庫、1976、p.11)
「そういうわけで、去年の秋に黄昏の散歩を始めてみると」
(テジュ・コール『オープン・シティ』新潮社クレスト・ブックス、2017、p.7)

「そういうわけで、去年の秋に黄昏の散歩を始めてみると」
(テジュ・コール『オープン・シティ』新潮社クレスト・ブックス、2017、p.7)
「ホルタで船を降りる航海者は、かならず、埠頭の壁に絵、あるいは名前か日付を書き残すことになっている。一〇〇メートルほどの長さの壁に、帆船の絵やめいめいの国や船の旗の色どりや数字や短い文章などがごちゃごちゃと書いてある。ひとつだけ、ここに書き写してみよう。ブリスベインのナット。風の吹くまま、ぼくは旅をする。」
(アントニオ・タブッキ『島とクジラと女をめぐる断片(新版)』須賀敦子訳、2009、青土社、pp.58-59)

「ホルタで船を降りる航海者は、かならず、埠頭の壁に絵、あるいは名前か日付を書き残すことになっている。一〇〇メートルほどの長さの壁に、帆船の絵やめいめいの国や船の旗の色どりや数字や短い文章などがごちゃごちゃと書いてある。ひとつだけ、ここに書き写してみよう。ブリスベインのナット。風の吹くまま、ぼくは旅をする。」
(アントニオ・タブッキ『島とクジラと女をめぐる断片(新版)』須賀敦子訳、2009、青土社、pp.58-59)
「眠りは平坦で浅かった。あなたは、眠りの視野の縁飾りが朱色に染まり始めたように感じ、目が覚めた。窓にかけられたカーテンをちょっとめくって外を見ると、地平線が一直線に朱色に染まり、樹木のシルエットが並んでいた。」
(多和田葉子『容疑者の夜行列車』青土社、2002、p.76)

「眠りは平坦で浅かった。あなたは、眠りの視野の縁飾りが朱色に染まり始めたように感じ、目が覚めた。窓にかけられたカーテンをちょっとめくって外を見ると、地平線が一直線に朱色に染まり、樹木のシルエットが並んでいた。」
(多和田葉子『容疑者の夜行列車』青土社、2002、p.76)
「図書館学校で好きだったのは、デューイ十進分類法だ。アメリカ人の司書メルヴィル・デューイによって一九七六年に創案され、主題に基づいて、図書館の書架にある本を十クラスに分類するものだ。すべてに数字が割り振られていて、誰でも、どの図書館ででも、どんな本でも見つけることができる。たとえばママは自分の六四八(家事)に誇りを持っている。パパは自分では認めないけれど、本当は七八五(室内楽)が好き。」
(ジャネット・スケスリン・チャールズ『あの図書館の彼女たち』髙山祥子 訳、東京創元社、2022、p.6)

「図書館学校で好きだったのは、デューイ十進分類法だ。アメリカ人の司書メルヴィル・デューイによって一九七六年に創案され、主題に基づいて、図書館の書架にある本を十クラスに分類するものだ。すべてに数字が割り振られていて、誰でも、どの図書館ででも、どんな本でも見つけることができる。たとえばママは自分の六四八(家事)に誇りを持っている。パパは自分では認めないけれど、本当は七八五(室内楽)が好き。」
(ジャネット・スケスリン・チャールズ『あの図書館の彼女たち』髙山祥子 訳、東京創元社、2022、p.6)
「いつから匂いの記録をつけるようになったのだろう。彼女には、はっきりとは思いだせなかった。ただ確かなのは、そのころの子供なら誰もがしていたように鉛筆でせっせと埋められたページには、その日に嗅いだものの箇条書きや描写がすでに現れていたことだった。」
(関口涼子『匂いに呼ばれて』講談社、2025、p.5)

「いつから匂いの記録をつけるようになったのだろう。彼女には、はっきりとは思いだせなかった。ただ確かなのは、そのころの子供なら誰もがしていたように鉛筆でせっせと埋められたページには、その日に嗅いだものの箇条書きや描写がすでに現れていたことだった。」
(関口涼子『匂いに呼ばれて』講談社、2025、p.5)
「「彼は人生を無為にすごした」とか、「今日はなにもしなかった」などというではないか。とんでもないいいぐさだ。あなたは生きてきたではないか。それこそが、あなたの仕事の基本であるばかりか、もっとも輝かしい仕事なのに。」
(モンテーニュ「経験について」、『モンテーニュ エセー抄』宮下志朗編訳、みすず書房、2003、所収、pp.209-210)

「「彼は人生を無為にすごした」とか、「今日はなにもしなかった」などというではないか。とんでもないいいぐさだ。あなたは生きてきたではないか。それこそが、あなたの仕事の基本であるばかりか、もっとも輝かしい仕事なのに。」
(モンテーニュ「経験について」、『モンテーニュ エセー抄』宮下志朗編訳、みすず書房、2003、所収、pp.209-210)
「水の流ほど見ているものに言い知れぬ空想の喜びを与えるものはない。薄く曇った風のない秋の日の夕暮近くは、ここのみならず何処(いずこ)の河、いずこの流れも見るには最もよき時であろう。」
(永井荷風「水のながれ」、『荷風随筆集(上)』野口冨士男編、岩波文庫、1986、所収、p.286 )

「水の流ほど見ているものに言い知れぬ空想の喜びを与えるものはない。薄く曇った風のない秋の日の夕暮近くは、ここのみならず何処(いずこ)の河、いずこの流れも見るには最もよき時であろう。」
(永井荷風「水のながれ」、『荷風随筆集(上)』野口冨士男編、岩波文庫、1986、所収、p.286 )
「それで今年は誕生日をやってみることにした。」
(津村記久子「誕生日の一日」、『うそコンシェルジュ』新潮社、2024、所収、p.53)

「それで今年は誕生日をやってみることにした。」
(津村記久子「誕生日の一日」、『うそコンシェルジュ』新潮社、2024、所収、p.53)
「旅でふしぎに印象に残る時間は、都市の広場に面したカフェテラスで何もしないで行き交う人たちを眺めてすごした朝だとか、海岸線を陽が暮れるまでただ歩きつづけた一日とか、要するに何かに有効に「使われた」時間ではなく、ただ「生きられた」時間です。」
(見田宗介『社会学入門』岩波新書、2006、p.32)

「旅でふしぎに印象に残る時間は、都市の広場に面したカフェテラスで何もしないで行き交う人たちを眺めてすごした朝だとか、海岸線を陽が暮れるまでただ歩きつづけた一日とか、要するに何かに有効に「使われた」時間ではなく、ただ「生きられた」時間です。」
(見田宗介『社会学入門』岩波新書、2006、p.32)
ストーナーは英文学の講義でシェイクスピアの73番目のソネットの朗読を聞く。それが意味するところが何であるかは言葉にできないが、そこに何かを感じる――
「ウィリアム・ストーナーは、自分がしばしのあいだ息を詰めていたことに気づいた。そうっと息を吐き、肺から空気が出ていくにつれて服が少しずつ皮膚の上で動くのを意識する。」
(ジョン・ウィリアムズ『ストーナー』東江一紀 訳、作品社、2014、p.15)

ストーナーは英文学の講義でシェイクスピアの73番目のソネットの朗読を聞く。それが意味するところが何であるかは言葉にできないが、そこに何かを感じる――
「ウィリアム・ストーナーは、自分がしばしのあいだ息を詰めていたことに気づいた。そうっと息を吐き、肺から空気が出ていくにつれて服が少しずつ皮膚の上で動くのを意識する。」
(ジョン・ウィリアムズ『ストーナー』東江一紀 訳、作品社、2014、p.15)
「ラレレ、ラレレ、ラレレ、 あるいは生は美しいのかもしれない、無に等しいほどに 」
「細い通りをたどること 」
「水たまりのほとりではどの猫も違った跳ね方をする 」
「小さな停車駅のまなざし ユルゲン・フックスにおける記憶の方眼紙 」
ヘルタ・ミュラー『いつもおなじ雪といつもおなじおじさん――ヘルタ・ミュラー エッセイ集』新本史斉訳、三修社、2025年、の目次からいくつか引用した。

「ラレレ、ラレレ、ラレレ、 あるいは生は美しいのかもしれない、無に等しいほどに 」
「細い通りをたどること 」
「水たまりのほとりではどの猫も違った跳ね方をする 」
「小さな停車駅のまなざし ユルゲン・フックスにおける記憶の方眼紙 」
ヘルタ・ミュラー『いつもおなじ雪といつもおなじおじさん――ヘルタ・ミュラー エッセイ集』新本史斉訳、三修社、2025年、の目次からいくつか引用した。
「ようやくあとがきを書くところに漕ぎつけた。まったく途中で死なないでよかったという感じである。」
(新関公子「あとがき」より、『東京美術学校物語――国粋と国際のはざまに揺れて』岩波新書、2025、p.245)

「ようやくあとがきを書くところに漕ぎつけた。まったく途中で死なないでよかったという感じである。」
(新関公子「あとがき」より、『東京美術学校物語――国粋と国際のはざまに揺れて』岩波新書、2025、p.245)
「そこへはむかし同様鉄道で行きたいと思っていた。飛行機で、あるいは車で行けばやはり町は相貌を変えてしまう。電車で、それだけの時間をかけて、町のおもかげを胸のうちで反芻しながら近づいて行くのでなければならない。」
(山田稔『別れの手続き――山田稔散文選』(大人の本棚)、みすず書房、2011、p.118)

「そこへはむかし同様鉄道で行きたいと思っていた。飛行機で、あるいは車で行けばやはり町は相貌を変えてしまう。電車で、それだけの時間をかけて、町のおもかげを胸のうちで反芻しながら近づいて行くのでなければならない。」
(山田稔『別れの手続き――山田稔散文選』(大人の本棚)、みすず書房、2011、p.118)
「本を読み終えたら文章を抜粋する。その部分をカメラで撮っておくこともあれば、一文一文、メモアプリに書き写すこともある。書き写す場合、ゆうに一、二時間はかかるけれど、作業を終えるたびにひとり味わう達成感は格別だ。そうやって抜粋に力を入れていると、ふと、自分は文章を収集するために本を読んでいるのだろうか、と思うこともある。 できることなら、良い文章を一文たりとも逃したくない。」
(ファン・ボルム『毎日読みます』牧野美加訳、集英社、2025、p.93)

「本を読み終えたら文章を抜粋する。その部分をカメラで撮っておくこともあれば、一文一文、メモアプリに書き写すこともある。書き写す場合、ゆうに一、二時間はかかるけれど、作業を終えるたびにひとり味わう達成感は格別だ。そうやって抜粋に力を入れていると、ふと、自分は文章を収集するために本を読んでいるのだろうか、と思うこともある。 できることなら、良い文章を一文たりとも逃したくない。」
(ファン・ボルム『毎日読みます』牧野美加訳、集英社、2025、p.93)
「私たちの関係で彼が好きだったのは、と彼は言っていた、私たちが決して他の人々や私たち共通の知人について話さないことだった。彼に言わせれば、私たちは駅のプラットホームで出会う旅行者のように話し合っていた。」
* 彼とはサルトルのこと。
(フランソワーズ・サガン『私自身のための優しい回想』朝吹三吉 訳、新潮文庫、1995、p.153)

「私たちの関係で彼が好きだったのは、と彼は言っていた、私たちが決して他の人々や私たち共通の知人について話さないことだった。彼に言わせれば、私たちは駅のプラットホームで出会う旅行者のように話し合っていた。」
* 彼とはサルトルのこと。
(フランソワーズ・サガン『私自身のための優しい回想』朝吹三吉 訳、新潮文庫、1995、p.153)
「仕事か遊びか、労働か余暇かといった二者択一が問題なのではなく、同じ行為がどういうきっかけで愉しみになり、どういうきっかけで労苦になるのか、その展開軸を見さだめることが必要である。」
(鷲田清一『思考のエシックス——反・方法主義論』ナカニシヤ出版、2007、p.280)

「仕事か遊びか、労働か余暇かといった二者択一が問題なのではなく、同じ行為がどういうきっかけで愉しみになり、どういうきっかけで労苦になるのか、その展開軸を見さだめることが必要である。」
(鷲田清一『思考のエシックス——反・方法主義論』ナカニシヤ出版、2007、p.280)
「私の祖母が私の襦袢にポケットを縫いつけ、その中に入れてくれた金であった。祖母は言ったのである――都にゆけばじき冬になる。都の冬には新しいくびまきが要るであろう。いなかの店のくびまきは都の娘子衆のくびまきに見劣りのすることは必定(ひつじょう)であろ。この金で好いた柄のを買いなされ。」
(尾崎翠『第七官界彷徨』河出文庫、2009、p.21)

「私の祖母が私の襦袢にポケットを縫いつけ、その中に入れてくれた金であった。祖母は言ったのである――都にゆけばじき冬になる。都の冬には新しいくびまきが要るであろう。いなかの店のくびまきは都の娘子衆のくびまきに見劣りのすることは必定(ひつじょう)であろ。この金で好いた柄のを買いなされ。」
(尾崎翠『第七官界彷徨』河出文庫、2009、p.21)
「「こいさん、頼むわ。――――」
鏡の中で、廊下からうしろへ這入(はい)って来た妙子を見ると、自分で襟を塗りかけていた刷毛(はけ)を渡して、其方(そちら)はみずに、目の前に映っている長襦袢(ながじゅばん)姿の、抜き衣紋(えもん)の顔を他人の顔のように見据えながら、
「雪子ちゃん下で何してる」
と、幸子はきいた。
「悦ちゃんのピアノ見たげてるらしい」」
* 読み進めていくと、この日は、昭和11年(1936)11月8日(日曜日)であることがわかる。
(谷崎潤一郎『細雪(上)』、新潮文庫、1997、p.5)

「「こいさん、頼むわ。――――」
鏡の中で、廊下からうしろへ這入(はい)って来た妙子を見ると、自分で襟を塗りかけていた刷毛(はけ)を渡して、其方(そちら)はみずに、目の前に映っている長襦袢(ながじゅばん)姿の、抜き衣紋(えもん)の顔を他人の顔のように見据えながら、
「雪子ちゃん下で何してる」
と、幸子はきいた。
「悦ちゃんのピアノ見たげてるらしい」」
* 読み進めていくと、この日は、昭和11年(1936)11月8日(日曜日)であることがわかる。
(谷崎潤一郎『細雪(上)』、新潮文庫、1997、p.5)
「去年から、ジョーは頭の中である壮大な計画を立てていた。この一生に読んだ小説の物語をもう一度読み直し、すべての物語をつないでいこうというのだ。そうすれば本を手に取っただけで、ひとつの物語からべつな物語へと停まることなく渡っていける。」
(残雪『最後の恋人』近藤直子訳、平凡社、2014、p.16)

「去年から、ジョーは頭の中である壮大な計画を立てていた。この一生に読んだ小説の物語をもう一度読み直し、すべての物語をつないでいこうというのだ。そうすれば本を手に取っただけで、ひとつの物語からべつな物語へと停まることなく渡っていける。」
(残雪『最後の恋人』近藤直子訳、平凡社、2014、p.16)
「こんにちでは誰しも死の判定といえばすべて医学の問題として疑わない。しかし、明治以前は死の判定は家族がしていた。文化人類学者の波平恵美子によると、「通夜」というのは死者を悼むためだけのものではなく、死者が生き返ってこないかどうかを確認するためのものであったという。」
(立川昭二『昭和の跫音』筑摩書房、1992、p.42)

「こんにちでは誰しも死の判定といえばすべて医学の問題として疑わない。しかし、明治以前は死の判定は家族がしていた。文化人類学者の波平恵美子によると、「通夜」というのは死者を悼むためだけのものではなく、死者が生き返ってこないかどうかを確認するためのものであったという。」
(立川昭二『昭和の跫音』筑摩書房、1992、p.42)
「建築もそこにいることがただ気持ちのいいものでなければ意味がない。」
(松家仁之『天使も踏むを畏れるところ(上)』新潮社、2025、p.222)

「建築もそこにいることがただ気持ちのいいものでなければ意味がない。」
(松家仁之『天使も踏むを畏れるところ(上)』新潮社、2025、p.222)
「おとなになると、周りはすでに見知った「何か」ばかりであり、いったん「何か」として分類してしまえば、それ以上きちんと見ようとしない。」
(齋藤亜矢『ヒトはなぜ絵を描くのか――芸術認知科学への招待』岩波科学ライブラリー、2014、p.89)

「おとなになると、周りはすでに見知った「何か」ばかりであり、いったん「何か」として分類してしまえば、それ以上きちんと見ようとしない。」
(齋藤亜矢『ヒトはなぜ絵を描くのか――芸術認知科学への招待』岩波科学ライブラリー、2014、p.89)
「十一月自体が秋から冬に向かう旅だと考えてもいいかもしれない。いながらにしての旅。移動するのは自分ではない。周囲の世界全体が冬に向かって旅をしているのだ。空は高みを増し、空気は新しくなる。花の色は薄く変わり、街や人はほかの季節より穏やかな色に包まれる。」
(西崎憲「跋」より、西崎憲編『11月の本』国書刊行会、2025、p.267)

「十一月自体が秋から冬に向かう旅だと考えてもいいかもしれない。いながらにしての旅。移動するのは自分ではない。周囲の世界全体が冬に向かって旅をしているのだ。空は高みを増し、空気は新しくなる。花の色は薄く変わり、街や人はほかの季節より穏やかな色に包まれる。」
(西崎憲「跋」より、西崎憲編『11月の本』国書刊行会、2025、p.267)
「定家明月記私抄」を雑誌「波」に連載していた(1981〜)頃の父・堀田善衛について――
「定家さんは独自な漢文、父は読み下すのに本当に四苦八苦していました。教養がないと嘆き、「明月記わからん帳」というノートを作り、一言一句を理解するのに三日も四日もかかり、それが定家さんの当て字だったりすると、もう啞然、茫然、どっと疲れていました。当然機嫌も悪くなります。それが三年四ヵ月続きました。その後休筆をはさんで、日本において書かれた続篇〔正篇はバルセロナで書かれた〕、二年三ヵ月も併せれば、約八年です。」〔 〕内は引用者注。
(堀田百合子『ただの文士』岩波書店、2018、p.164)

「定家明月記私抄」を雑誌「波」に連載していた(1981〜)頃の父・堀田善衛について――
「定家さんは独自な漢文、父は読み下すのに本当に四苦八苦していました。教養がないと嘆き、「明月記わからん帳」というノートを作り、一言一句を理解するのに三日も四日もかかり、それが定家さんの当て字だったりすると、もう啞然、茫然、どっと疲れていました。当然機嫌も悪くなります。それが三年四ヵ月続きました。その後休筆をはさんで、日本において書かれた続篇〔正篇はバルセロナで書かれた〕、二年三ヵ月も併せれば、約八年です。」〔 〕内は引用者注。
(堀田百合子『ただの文士』岩波書店、2018、p.164)