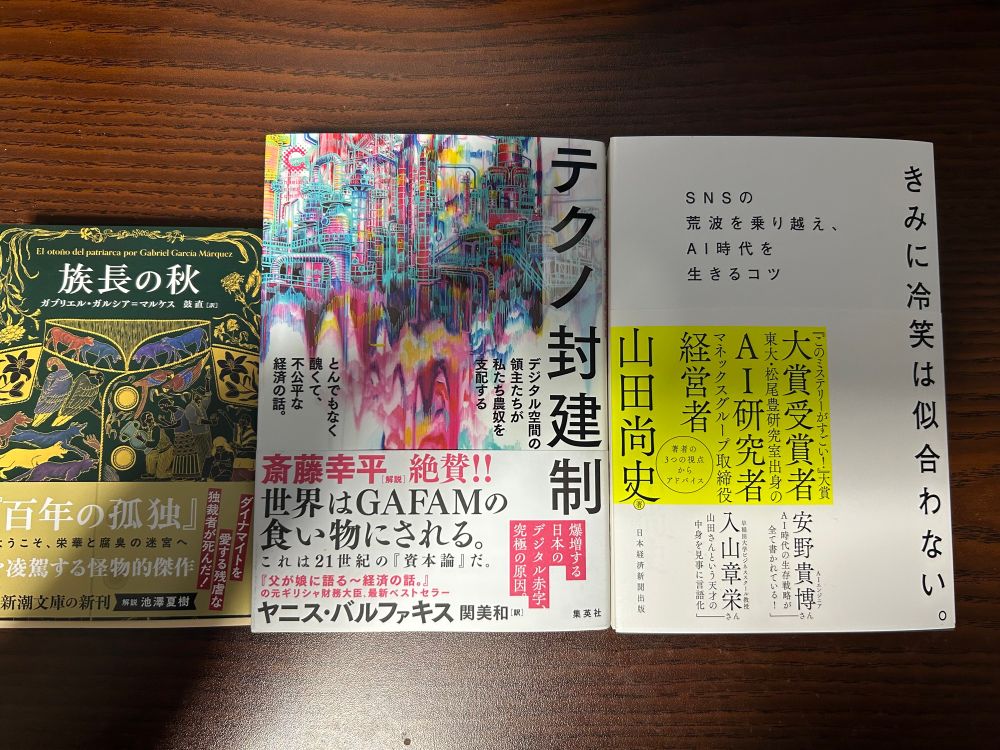ヤニス・バルファキス『テクノ封建制』
ヤニス・バルファキス『テクノ封建制』
言葉が出ない。もう少し著者近辺の類書を読まねばならない。
この本もとりあえずあと何度か読み返す必要がある。今年読んだ本の中で最重要書。
言葉が出ない。もう少し著者近辺の類書を読まねばならない。
この本もとりあえずあと何度か読み返す必要がある。今年読んだ本の中で最重要書。

読み物としてすごい面白かった。
本のなかにあるように、我々は歴史を一元的にとらえてそれを良いとか悪いとかなんだといいがちだけど、実際は世界中で様々な文化と社会があったという当たり前のことに新鮮に気付かされたのも良かったな。
家父長制と一言に言っても、そこには当然グラデーションがあるし、どんな形の自由や平等を求めるかは人それぞれというのも改めて実感した。
そのうえで人が人に対して抑圧的な支配を向けるのはジェンダー以前の人権に対する冒涜だし、何より自分が属する社会が平和であってこそそこに目を向け闘うことが出来るんだなとも思えた。
読み物としてすごい面白かった。
本のなかにあるように、我々は歴史を一元的にとらえてそれを良いとか悪いとかなんだといいがちだけど、実際は世界中で様々な文化と社会があったという当たり前のことに新鮮に気付かされたのも良かったな。
家父長制と一言に言っても、そこには当然グラデーションがあるし、どんな形の自由や平等を求めるかは人それぞれというのも改めて実感した。
そのうえで人が人に対して抑圧的な支配を向けるのはジェンダー以前の人権に対する冒涜だし、何より自分が属する社会が平和であってこそそこに目を向け闘うことが出来るんだなとも思えた。
www.shueisha.co.jp/books/items/...
「家父長制は普遍でも不変でもない。
歴史のなかに起源のあるものには、必ず終わりがある。
先史時代から現代まで、最新の知見にもとづいた挑戦の書」

www.shueisha.co.jp/books/items/...
「家父長制は普遍でも不変でもない。
歴史のなかに起源のあるものには、必ず終わりがある。
先史時代から現代まで、最新の知見にもとづいた挑戦の書」
著者:アンジェラ・サイニー 訳者:道本 美穂
www.shueisha.co.jp/books/items/...
"なぜ男性ばかりが社会的地位を独占しているのか。
男が女性を支配する「家父長制」は、人類の始まりから続く不可避なものなのか。
これらの問いに答えるべく、著者は歴史をひもとき、世界各地を訪ねながら、さまざまな家父長制なき社会を掘り下げていく。
丹念な取材によって見えてきたものとは……。
抑圧の真の根源を探りながら、未来の変革と希望へと読者を誘う話題作。"

著者:アンジェラ・サイニー 訳者:道本 美穂
www.shueisha.co.jp/books/items/...
"なぜ男性ばかりが社会的地位を独占しているのか。
男が女性を支配する「家父長制」は、人類の始まりから続く不可避なものなのか。
これらの問いに答えるべく、著者は歴史をひもとき、世界各地を訪ねながら、さまざまな家父長制なき社会を掘り下げていく。
丹念な取材によって見えてきたものとは……。
抑圧の真の根源を探りながら、未来の変革と希望へと読者を誘う話題作。"
shueisha-common.jp/books/978-4-...

shueisha-common.jp/books/978-4-...
『「世界の終わり」の地政学』。上下巻とも4刷が決まりました。
shueisha-common.jp/books/978-4-...

『「世界の終わり」の地政学』。上下巻とも4刷が決まりました。
shueisha-common.jp/books/978-4-...
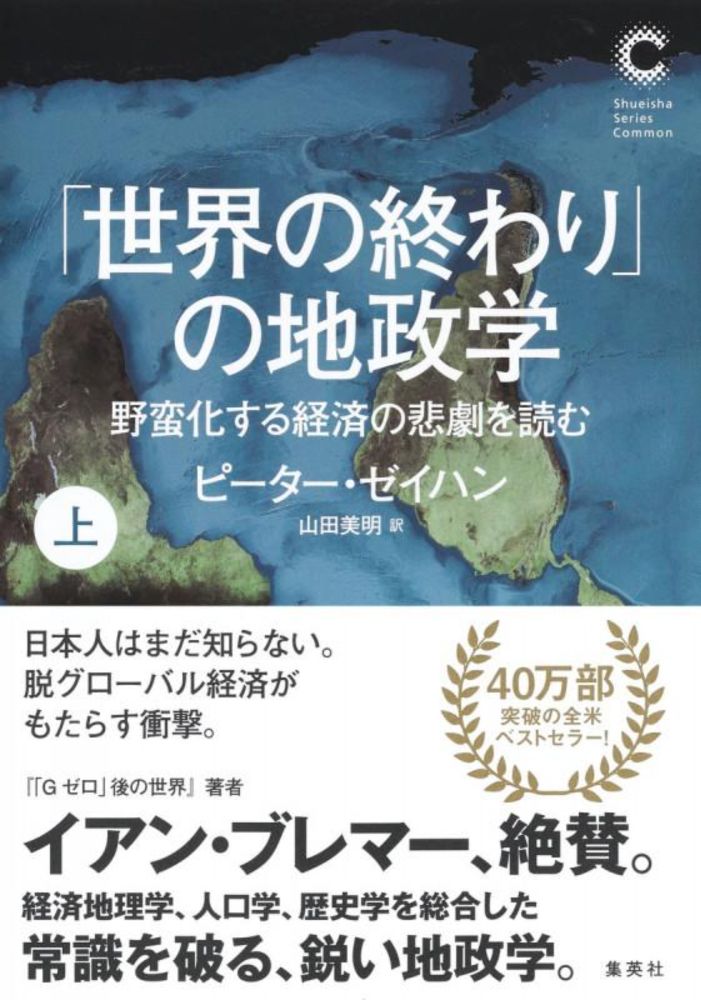
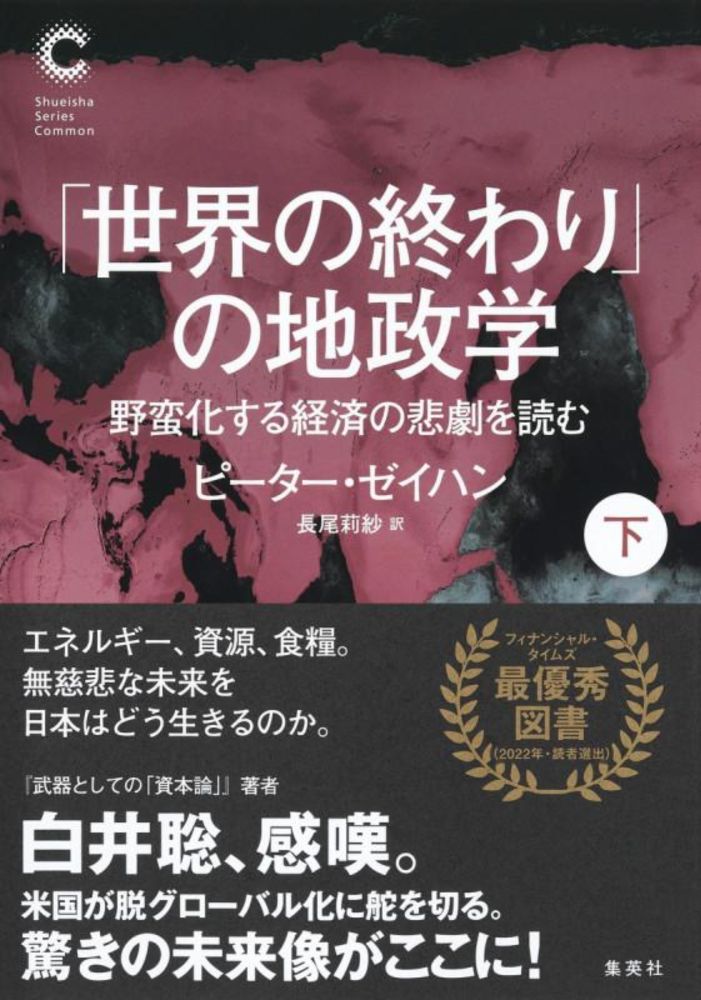
『Plurality』本が指摘する「テック VS民主主義」の構図は、いわばアメリカのテック界隈が見ている現実でした(おそらくグレン・ワイルの執筆パート)。
客観的に見れば、これは「資本主義 VS 民主主義」の構図であり、さらにヤニス・バルファキスによればビッグテックは資本主義すら食い尽くしテクノ封建制に移行している。つまり「テック封建制 VS 民主主義」になってしまっている。
大きく見ると、資本主義を取り戻し(健全な競争と規制を取り戻し)、民主主義を機能させる(偽情報や憎悪言説を規制し、健全な熟議を復活させる)取り組みが、求められています。
勿論、資本主義というシステムが抱える致命的なバグも要因だとは思うけど、もっと本質的な問題は「ヒトの中に巣食う強欲」ってことなんだよね
愚かだよなぁ
2018年頃のケンブリッジ・アナリティカ事件がターニングポイントだった。あるドキュメンタリーで、こんなセリフがある。「それまで、ソフトウェアエンジニアはパーカを着た善人だと思っていた。今は違う」
2025年現在、イーロン・マスクのおかげでテック界隈の評判は地に落ちている。
その風潮を変えようとしたのが、オードリー・タンとグレン・ワイルの共著「Plurality」だった。これは「民主主義とテクノロジーが敵対せずに済む道」を探る本である。(つまり、放っておけば敵対するというのだ)
(続く
『Plurality』本が指摘する「テック VS民主主義」の構図は、いわばアメリカのテック界隈が見ている現実でした(おそらくグレン・ワイルの執筆パート)。
客観的に見れば、これは「資本主義 VS 民主主義」の構図であり、さらにヤニス・バルファキスによればビッグテックは資本主義すら食い尽くしテクノ封建制に移行している。つまり「テック封建制 VS 民主主義」になってしまっている。
大きく見ると、資本主義を取り戻し(健全な競争と規制を取り戻し)、民主主義を機能させる(偽情報や憎悪言説を規制し、健全な熟議を復活させる)取り組みが、求められています。
「では、私の仮説とは?それは、資本主義はすでに死んでいる、というものだ。つまり資本主義の力学がもはや経済を動かしてはいない、という意味だ。資本主義が担ってきた役割はまったく別のなにかに置き換えられている。その別のなにかを私は「テクノ封建制」と名づけた。」

「では、私の仮説とは?それは、資本主義はすでに死んでいる、というものだ。つまり資本主義の力学がもはや経済を動かしてはいない、という意味だ。資本主義が担ってきた役割はまったく別のなにかに置き換えられている。その別のなにかを私は「テクノ封建制」と名づけた。」
イーロン・マスクがTwitter(現X)を買収した理由について解説されています。
それは単なる気まぐれや道楽ではなく、彼がまだ手に入れていないものを得るためでした。
テクノ封建制の論理からマスクの真意を解き明かします。

イーロン・マスクがTwitter(現X)を買収した理由について解説されています。
それは単なる気まぐれや道楽ではなく、彼がまだ手に入れていないものを得るためでした。
テクノ封建制の論理からマスクの真意を解き明かします。
アンジェラ・サイニー 著/上野千鶴子 解説/道本美穂 訳『家父長制の起源 男たちはいかにして支配者になったのか』(集英社シリーズ・コモン)を斎藤美奈子さんが読む
shueisha-common.jp/reviews/kafu...

アンジェラ・サイニー 著/上野千鶴子 解説/道本美穂 訳『家父長制の起源 男たちはいかにして支配者になったのか』(集英社シリーズ・コモン)を斎藤美奈子さんが読む
shueisha-common.jp/reviews/kafu...
『NEXUS 人類の情報史』と分野が中らずと雖も遠からずなんだよなあ
巨大テック企業が国家に匹敵する、いや国家以上の大プレイヤーになった現代の世界情勢を把握する上でとても有力な本だと思う
GAFAMは世界80億人の生殺与奪の権を掌握していると言って過言ではない
『NEXUS 人類の情報史』と分野が中らずと雖も遠からずなんだよなあ
巨大テック企業が国家に匹敵する、いや国家以上の大プレイヤーになった現代の世界情勢を把握する上でとても有力な本だと思う
GAFAMは世界80億人の生殺与奪の権を掌握していると言って過言ではない
世界はテクノ封建制になりつつ話がおもろかった、俺たちはクラウド奴隷

世界はテクノ封建制になりつつ話がおもろかった、俺たちはクラウド奴隷
まず、きちんと説明すれば、ビッグテック周辺の怪しい思想に対する問題意識は、日本の読者にも理解可能なものだと信じます。
例えば、2025年2月に、Yanis Varoufakis, "TECHNOFEUDALISM: What Killed Capitalism"の翻訳「テクノ封建制」が日本で出版されて、かなり話題になりました。日本の読者の間でも、「BigTechのやり方は本当に正しいのか」という関心が高まっています。
ただし、まだまだ初期の段階です。Existential crisis、TESCREALといった概念は、いまのところ日本ではあまり有名ではありません。
まず、きちんと説明すれば、ビッグテック周辺の怪しい思想に対する問題意識は、日本の読者にも理解可能なものだと信じます。
例えば、2025年2月に、Yanis Varoufakis, "TECHNOFEUDALISM: What Killed Capitalism"の翻訳「テクノ封建制」が日本で出版されて、かなり話題になりました。日本の読者の間でも、「BigTechのやり方は本当に正しいのか」という関心が高まっています。
ただし、まだまだ初期の段階です。Existential crisis、TESCREALといった概念は、いまのところ日本ではあまり有名ではありません。
Xでためらいもなくgrokを使い物事の白黒判定をしてもらっているポストとか見ると、ヤニス・バルファキスの懸念はかなりの確率で的中してるんだろうなとか思えてなー…
prtimes.jp/main/html/rd...

Xでためらいもなくgrokを使い物事の白黒判定をしてもらっているポストとか見ると、ヤニス・バルファキスの懸念はかなりの確率で的中してるんだろうなとか思えてなー…
prtimes.jp/main/html/rd...
blog.tatsuru.com/2025/05/02_1...
blog.tatsuru.com/2025/05/02_1...