そっか、亡くなってから20年以上経つから現代文庫になるわけはないな。
でも評論だから青帯かと勝手に思ってた。まさか文学のくくりとは。
でも評論だから青帯かと勝手に思ってた。まさか文学のくくりとは。
November 10, 2025 at 7:47 AM
そっか、亡くなってから20年以上経つから現代文庫になるわけはないな。
でも評論だから青帯かと勝手に思ってた。まさか文学のくくりとは。
でも評論だから青帯かと勝手に思ってた。まさか文学のくくりとは。
【社主のニュース解説】《文化》
例えば、第1集には自身の『トロッコ』のほか比較的読みやすい作品を集める一方、第5集では志賀直哉氏の私小説『城の崎にて』に始まり、夏目漱石の評論『スウィフトと厭世文学』で終える配列になっています。ここからは、芥川氏の意図と同時に深い見識も垣間見えます。
例えば、第1集には自身の『トロッコ』のほか比較的読みやすい作品を集める一方、第5集では志賀直哉氏の私小説『城の崎にて』に始まり、夏目漱石の評論『スウィフトと厭世文学』で終える配列になっています。ここからは、芥川氏の意図と同時に深い見識も垣間見えます。
November 8, 2025 at 12:45 PM
【社主のニュース解説】《文化》
例えば、第1集には自身の『トロッコ』のほか比較的読みやすい作品を集める一方、第5集では志賀直哉氏の私小説『城の崎にて』に始まり、夏目漱石の評論『スウィフトと厭世文学』で終える配列になっています。ここからは、芥川氏の意図と同時に深い見識も垣間見えます。
例えば、第1集には自身の『トロッコ』のほか比較的読みやすい作品を集める一方、第5集では志賀直哉氏の私小説『城の崎にて』に始まり、夏目漱石の評論『スウィフトと厭世文学』で終える配列になっています。ここからは、芥川氏の意図と同時に深い見識も垣間見えます。
【社主のニュース解説】《文化》
本日、興文社から『近代日本文芸読本』全5集が発行されました。各巻310ページ前後で、低下は1冊1円70銭。明治から大正の120人以上の作家から、おもな小説、随筆、戯曲、評論、日記、翻訳、詩歌など148編の作品を網羅的に取り上げた、いわば近代文学全集の決定版です。
本日、興文社から『近代日本文芸読本』全5集が発行されました。各巻310ページ前後で、低下は1冊1円70銭。明治から大正の120人以上の作家から、おもな小説、随筆、戯曲、評論、日記、翻訳、詩歌など148編の作品を網羅的に取り上げた、いわば近代文学全集の決定版です。
November 8, 2025 at 12:20 PM
【社主のニュース解説】《文化》
本日、興文社から『近代日本文芸読本』全5集が発行されました。各巻310ページ前後で、低下は1冊1円70銭。明治から大正の120人以上の作家から、おもな小説、随筆、戯曲、評論、日記、翻訳、詩歌など148編の作品を網羅的に取り上げた、いわば近代文学全集の決定版です。
本日、興文社から『近代日本文芸読本』全5集が発行されました。各巻310ページ前後で、低下は1冊1円70銭。明治から大正の120人以上の作家から、おもな小説、随筆、戯曲、評論、日記、翻訳、詩歌など148編の作品を網羅的に取り上げた、いわば近代文学全集の決定版です。
信頼の書評家、斉藤美奈子さんの月イチのこの連載、各都道府県を一つずつ取り上げてご当地小説を紹介されてるのだけど数えたらこの最新の宮城編で43本目!
古い作品から新しい作品まで、一般小説から児童小説まで目配りされてて、自分の出身県の小説でも知らない作品もあったりして読みたい本が増えた。
連載終わったら一冊の本にしてほしいな〜
有料記事がプレゼントされました! 11月4日 16:24まで全文お読みいただけます
(旅する文学)宮城編 青春の陰影がにじむ杜の都 文芸評論家・斎藤美奈子:朝日新聞
digital.asahi.com/articles/DA3...
古い作品から新しい作品まで、一般小説から児童小説まで目配りされてて、自分の出身県の小説でも知らない作品もあったりして読みたい本が増えた。
連載終わったら一冊の本にしてほしいな〜
有料記事がプレゼントされました! 11月4日 16:24まで全文お読みいただけます
(旅する文学)宮城編 青春の陰影がにじむ杜の都 文芸評論家・斎藤美奈子:朝日新聞
digital.asahi.com/articles/DA3...

(旅する文学)宮城編 青春の陰影がにじむ杜の都 文芸評論家・斎藤美奈子:朝日新聞
こと文学に関していえば、杜(もり)の都仙台は青春小説の街である。それも青春を謳歌(おうか)するのではなく、悩み考えるタイプの若者たちの。 佐伯一麦(かずみ)の三島由紀夫賞受賞作『ア・ルース・ボーイ』…
digital.asahi.com
November 3, 2025 at 7:31 AM
信頼の書評家、斉藤美奈子さんの月イチのこの連載、各都道府県を一つずつ取り上げてご当地小説を紹介されてるのだけど数えたらこの最新の宮城編で43本目!
古い作品から新しい作品まで、一般小説から児童小説まで目配りされてて、自分の出身県の小説でも知らない作品もあったりして読みたい本が増えた。
連載終わったら一冊の本にしてほしいな〜
有料記事がプレゼントされました! 11月4日 16:24まで全文お読みいただけます
(旅する文学)宮城編 青春の陰影がにじむ杜の都 文芸評論家・斎藤美奈子:朝日新聞
digital.asahi.com/articles/DA3...
古い作品から新しい作品まで、一般小説から児童小説まで目配りされてて、自分の出身県の小説でも知らない作品もあったりして読みたい本が増えた。
連載終わったら一冊の本にしてほしいな〜
有料記事がプレゼントされました! 11月4日 16:24まで全文お読みいただけます
(旅する文学)宮城編 青春の陰影がにじむ杜の都 文芸評論家・斎藤美奈子:朝日新聞
digital.asahi.com/articles/DA3...
11月23日開催 #文学フリマ東京41 スペースK-88「生ケ物同盟」にて、サークルメンバーの二木氏の手になる個人誌が出ます。初の評論エリアでの参加です。
新刊「成人向け音声作品を聴き始めたアナタに!」。
筆者厳選のおススメ作品30本以上をレビュー。タイトル通り、成人向け同人音声作品の『入聞(にゅうもん)書』としてぜひあなたのお手元に!
題材が題材なので本誌もR-18です。700円で頒布予定。
新刊「成人向け音声作品を聴き始めたアナタに!」。
筆者厳選のおススメ作品30本以上をレビュー。タイトル通り、成人向け同人音声作品の『入聞(にゅうもん)書』としてぜひあなたのお手元に!
題材が題材なので本誌もR-18です。700円で頒布予定。

November 4, 2025 at 1:45 PM
11月23日開催 #文学フリマ東京41 スペースK-88「生ケ物同盟」にて、サークルメンバーの二木氏の手になる個人誌が出ます。初の評論エリアでの参加です。
新刊「成人向け音声作品を聴き始めたアナタに!」。
筆者厳選のおススメ作品30本以上をレビュー。タイトル通り、成人向け同人音声作品の『入聞(にゅうもん)書』としてぜひあなたのお手元に!
題材が題材なので本誌もR-18です。700円で頒布予定。
新刊「成人向け音声作品を聴き始めたアナタに!」。
筆者厳選のおススメ作品30本以上をレビュー。タイトル通り、成人向け同人音声作品の『入聞(にゅうもん)書』としてぜひあなたのお手元に!
題材が題材なので本誌もR-18です。700円で頒布予定。
コミケ参加者が減ってる件だけど、いまは評論やレポサークルだったら「文学フリマ」や「おもしろ同人誌バザール」もあるから、コミケの必要性が下がってるということもあるかもね
October 26, 2025 at 8:47 AM
コミケ参加者が減ってる件だけど、いまは評論やレポサークルだったら「文学フリマ」や「おもしろ同人誌バザール」もあるから、コミケの必要性が下がってるということもあるかもね
SFマガジン12月号、長山靖生連載評論「SFのある文学誌」は、筆者が直接薫陶を受ける機会のあった故・紀田順一郎について、個人的な思い出などもまじえながらのSFや怪奇幻想文学、古典SF研究での業績に関する小評伝というべきもので、初期のSFファンダムや日本SF大会の話題も出てくる。
October 25, 2025 at 6:18 AM
SFマガジン12月号、長山靖生連載評論「SFのある文学誌」は、筆者が直接薫陶を受ける機会のあった故・紀田順一郎について、個人的な思い出などもまじえながらのSFや怪奇幻想文学、古典SF研究での業績に関する小評伝というべきもので、初期のSFファンダムや日本SF大会の話題も出てくる。
"日本人は憧れの都をどう描いたか──第一次世界大戦期から1960年代にかけてパリを訪れた作家や画家たちによる、エッセイ、小説、詩、評論をまとめた都市アンソロジー"
和田博文 編 『パリと日本人 近代文学セレクション 〈平凡社ライブラリー〉』
www.heibonsha.co.jp/book/b669941...
和田博文 編 『パリと日本人 近代文学セレクション 〈平凡社ライブラリー〉』
www.heibonsha.co.jp/book/b669941...
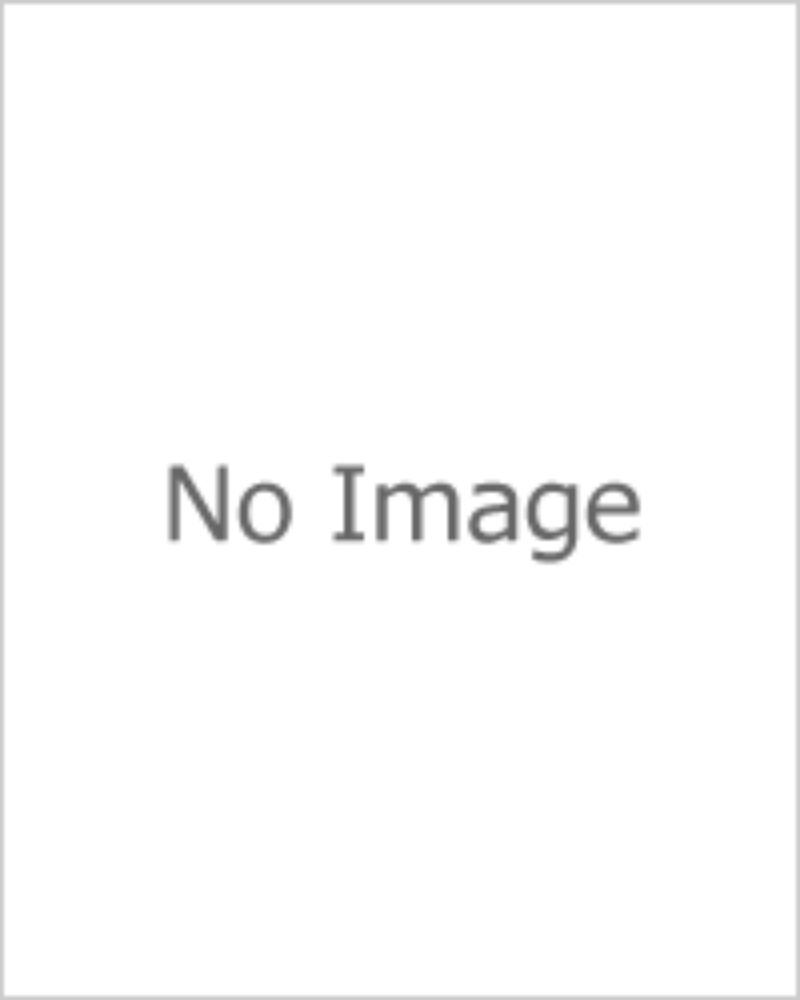
パリと日本人 近代文学セレクション - 平凡社
パリと日本人 近代文学セレクション詳細をご覧いただけます。
www.heibonsha.co.jp
October 24, 2025 at 12:22 PM
"日本人は憧れの都をどう描いたか──第一次世界大戦期から1960年代にかけてパリを訪れた作家や画家たちによる、エッセイ、小説、詩、評論をまとめた都市アンソロジー"
和田博文 編 『パリと日本人 近代文学セレクション 〈平凡社ライブラリー〉』
www.heibonsha.co.jp/book/b669941...
和田博文 編 『パリと日本人 近代文学セレクション 〈平凡社ライブラリー〉』
www.heibonsha.co.jp/book/b669941...
磯田光一『昭和への鎮魂』読了。
保守の評論家である著者が昭和が終わる時に自身とは反対の左派の思想家達を論じる。
昔の日本の文学評論って難しい。
最初に取り上げるのが蔵原惟人。プロレタリア文学の立役者で階級闘争に寄与するのが文学とした人。
続いて竹内好、小林秀雄を経て花田清輝が出てくる。柳田國男にも触りつつ村上一郎を取り上げ、野坂昭如、寺山修司で少し休んで、片岡啓治の攘夷論。この攘夷論の章が面白かった。
攘夷のための開国ってまさにいま…
最後は戦後文学で締める。
ヘーゲルの弁証法的な考え方が普通にできていた時代と、構造として解体する現代思想を経た時代。分断が進む世界ではもしかしたら…
保守の評論家である著者が昭和が終わる時に自身とは反対の左派の思想家達を論じる。
昔の日本の文学評論って難しい。
最初に取り上げるのが蔵原惟人。プロレタリア文学の立役者で階級闘争に寄与するのが文学とした人。
続いて竹内好、小林秀雄を経て花田清輝が出てくる。柳田國男にも触りつつ村上一郎を取り上げ、野坂昭如、寺山修司で少し休んで、片岡啓治の攘夷論。この攘夷論の章が面白かった。
攘夷のための開国ってまさにいま…
最後は戦後文学で締める。
ヘーゲルの弁証法的な考え方が普通にできていた時代と、構造として解体する現代思想を経た時代。分断が進む世界ではもしかしたら…

October 23, 2025 at 1:29 PM
磯田光一『昭和への鎮魂』読了。
保守の評論家である著者が昭和が終わる時に自身とは反対の左派の思想家達を論じる。
昔の日本の文学評論って難しい。
最初に取り上げるのが蔵原惟人。プロレタリア文学の立役者で階級闘争に寄与するのが文学とした人。
続いて竹内好、小林秀雄を経て花田清輝が出てくる。柳田國男にも触りつつ村上一郎を取り上げ、野坂昭如、寺山修司で少し休んで、片岡啓治の攘夷論。この攘夷論の章が面白かった。
攘夷のための開国ってまさにいま…
最後は戦後文学で締める。
ヘーゲルの弁証法的な考え方が普通にできていた時代と、構造として解体する現代思想を経た時代。分断が進む世界ではもしかしたら…
保守の評論家である著者が昭和が終わる時に自身とは反対の左派の思想家達を論じる。
昔の日本の文学評論って難しい。
最初に取り上げるのが蔵原惟人。プロレタリア文学の立役者で階級闘争に寄与するのが文学とした人。
続いて竹内好、小林秀雄を経て花田清輝が出てくる。柳田國男にも触りつつ村上一郎を取り上げ、野坂昭如、寺山修司で少し休んで、片岡啓治の攘夷論。この攘夷論の章が面白かった。
攘夷のための開国ってまさにいま…
最後は戦後文学で締める。
ヘーゲルの弁証法的な考え方が普通にできていた時代と、構造として解体する現代思想を経た時代。分断が進む世界ではもしかしたら…
“個人的に、批評や評論って歴史の堆積を前提とした中央集権的な言葉についていけなくて疎外感をおぼえることが多い。
『月のZINE』は各カルチャーの背景を親切に共有したうえで、平易なことばで開陳されてるやさしさを感じた。好きなカルチャーがたくさん扱われていて、知らないカルチャーも気になってた名前を見受けたので見てみたい……とくに米津玄師の新譜と轟音系を厚く読み解かれていて楽しく読んだ。”
とても嬉しい感想を頂きました😭 批評の言葉だけになりすぎないように、は書く上で最も考えたことでした🙏
文フリと映画と公園日記|Surface #文学フリマ note.com/mitume/n/n16...
『月のZINE』は各カルチャーの背景を親切に共有したうえで、平易なことばで開陳されてるやさしさを感じた。好きなカルチャーがたくさん扱われていて、知らないカルチャーも気になってた名前を見受けたので見てみたい……とくに米津玄師の新譜と轟音系を厚く読み解かれていて楽しく読んだ。”
とても嬉しい感想を頂きました😭 批評の言葉だけになりすぎないように、は書く上で最も考えたことでした🙏
文フリと映画と公園日記|Surface #文学フリマ note.com/mitume/n/n16...

文フリと映画と公園日記|Surface
10/5(Sun.) 文フリ福岡にいった。 買ったZINE、アート系のほんも買えてよかった! そのなかで、ポップカルチャー評論とのことで気になっていた 月の人さんの『月のZINE』を読みおえた。(以下リンクを貼らせていただく……)
個人的に、批評や評論って歴史の堆積を前提とした中央集権的な言葉についていけなくて疎外感をおぼえることが多い。 『月のZINE』は各カルチャーの背景を親切に共有した...
note.com
October 20, 2025 at 1:37 PM
“個人的に、批評や評論って歴史の堆積を前提とした中央集権的な言葉についていけなくて疎外感をおぼえることが多い。
『月のZINE』は各カルチャーの背景を親切に共有したうえで、平易なことばで開陳されてるやさしさを感じた。好きなカルチャーがたくさん扱われていて、知らないカルチャーも気になってた名前を見受けたので見てみたい……とくに米津玄師の新譜と轟音系を厚く読み解かれていて楽しく読んだ。”
とても嬉しい感想を頂きました😭 批評の言葉だけになりすぎないように、は書く上で最も考えたことでした🙏
文フリと映画と公園日記|Surface #文学フリマ note.com/mitume/n/n16...
『月のZINE』は各カルチャーの背景を親切に共有したうえで、平易なことばで開陳されてるやさしさを感じた。好きなカルチャーがたくさん扱われていて、知らないカルチャーも気になってた名前を見受けたので見てみたい……とくに米津玄師の新譜と轟音系を厚く読み解かれていて楽しく読んだ。”
とても嬉しい感想を頂きました😭 批評の言葉だけになりすぎないように、は書く上で最も考えたことでした🙏
文フリと映画と公園日記|Surface #文学フリマ note.com/mitume/n/n16...
『ホーロー質』加藤 典洋
評論を読もうフェス。文学、とくに私小説に関する評論が多くて面白かった。"いわゆる「文学青年」たちの小説は「世間」にたいし、「社会」にたいし、また「いえ」にたいしてこれを否定する「文学」の全能を...
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1309...
評論を読もうフェス。文学、とくに私小説に関する評論が多くて面白かった。"いわゆる「文学青年」たちの小説は「世間」にたいし、「社会」にたいし、また「いえ」にたいしてこれを否定する「文学」の全能を...
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1309...

ホーロー質 KoHiさんの感想 - 読書メーター
ホーロー質。評論を読もうフェス。文学、とくに私小説に関する評論が多くて面白かった。"いわゆる「文学青年」たちの小説は「世間」にたいし、「社会」にたいし、また「いえ」にたいしてこれを否定する「文学」の全能を信じるところに、なりたっている。"という一文が、やけに心に残っている。
bookmeter.com
October 15, 2025 at 12:56 PM
『ホーロー質』加藤 典洋
評論を読もうフェス。文学、とくに私小説に関する評論が多くて面白かった。"いわゆる「文学青年」たちの小説は「世間」にたいし、「社会」にたいし、また「いえ」にたいしてこれを否定する「文学」の全能を...
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1309...
評論を読もうフェス。文学、とくに私小説に関する評論が多くて面白かった。"いわゆる「文学青年」たちの小説は「世間」にたいし、「社会」にたいし、また「いえ」にたいしてこれを否定する「文学」の全能を...
#読書メーター
bookmeter.com/reviews/1309...
10月8日は小酒井不木(本名、小酒井光次)の誕生日(1890)。医学者で医学知識を生かした探偵小説の評論、随筆で探偵小説を大衆に根付かせる。 地主の家庭に生まれる。東京帝国大学大学院卒。医学研究の傍ら探偵小説の随筆や創作を行う。『犯罪文学研究』『殺人論』など。

October 7, 2025 at 11:05 PM
10月8日は小酒井不木(本名、小酒井光次)の誕生日(1890)。医学者で医学知識を生かした探偵小説の評論、随筆で探偵小説を大衆に根付かせる。 地主の家庭に生まれる。東京帝国大学大学院卒。医学研究の傍ら探偵小説の随筆や創作を行う。『犯罪文学研究』『殺人論』など。
🎃 10月7日(火)発売
📖 文學界 11月号
―――――――――
【特集】作家はAIと何を話すのか
🗣 対談 村田沙耶香 × 栗原聡
✍ 19人の「あなたはAIと何を話していますか?」
🖊 体験記 古川真人/向坂くじら
🎤 インタビュー 三宅陽一郎
🍨 新連載 斧屋
📚 創作 杉本裕孝/板垣真任
🌹 特集 市川沙央『女の子の背骨』の背骨
―――――――――
📖 文學界 11月号
―――――――――
【特集】作家はAIと何を話すのか
🗣 対談 村田沙耶香 × 栗原聡
✍ 19人の「あなたはAIと何を話していますか?」
🖊 体験記 古川真人/向坂くじら
🎤 インタビュー 三宅陽一郎
🍨 新連載 斧屋
📚 創作 杉本裕孝/板垣真任
🌹 特集 市川沙央『女の子の背骨』の背骨
―――――――――




October 3, 2025 at 3:06 AM
🎃 10月7日(火)発売
📖 文學界 11月号
―――――――――
【特集】作家はAIと何を話すのか
🗣 対談 村田沙耶香 × 栗原聡
✍ 19人の「あなたはAIと何を話していますか?」
🖊 体験記 古川真人/向坂くじら
🎤 インタビュー 三宅陽一郎
🍨 新連載 斧屋
📚 創作 杉本裕孝/板垣真任
🌹 特集 市川沙央『女の子の背骨』の背骨
―――――――――
📖 文學界 11月号
―――――――――
【特集】作家はAIと何を話すのか
🗣 対談 村田沙耶香 × 栗原聡
✍ 19人の「あなたはAIと何を話していますか?」
🖊 体験記 古川真人/向坂くじら
🎤 インタビュー 三宅陽一郎
🍨 新連載 斧屋
📚 創作 杉本裕孝/板垣真任
🌹 特集 市川沙央『女の子の背骨』の背骨
―――――――――
『民主文学』2025年11月号は、旭爪あかねさんの没後5年特集。支部誌に発表された単行本未収録作品、短編、評論、エッセイ、詩が掲載されています。松田繁郎の評論「『美しい人と人との力』ーー旭爪あかね『稲の旋律』三部作以後ーー」も。

October 1, 2025 at 9:31 PM
『民主文学』2025年11月号は、旭爪あかねさんの没後5年特集。支部誌に発表された単行本未収録作品、短編、評論、エッセイ、詩が掲載されています。松田繁郎の評論「『美しい人と人との力』ーー旭爪あかね『稲の旋律』三部作以後ーー」も。
ChatGPT5にヴァージニア・ウルフの書評や評論を集めた本(日本語訳)を挙げてくださいと入力した結果。
1. 『ヴァージニア・ウルフ エッセイ集』全3巻(みすず書房)
2. 『自分ひとりの部屋』(青土社、岩波文庫など)
3. 『女性にとって職業としての文学』(岩波文庫)
4. 『モダン・フィクション』を収録した評論集 日本語では単独刊行ではなく、エッセイ集の中に収録されることが多い。
5. 『書くことについて』(白水Uブックス など)
6. 『読書について』(ちくま文庫)
私が知る範囲では、4だけが正しい。
1. 『ヴァージニア・ウルフ エッセイ集』全3巻(みすず書房)
2. 『自分ひとりの部屋』(青土社、岩波文庫など)
3. 『女性にとって職業としての文学』(岩波文庫)
4. 『モダン・フィクション』を収録した評論集 日本語では単独刊行ではなく、エッセイ集の中に収録されることが多い。
5. 『書くことについて』(白水Uブックス など)
6. 『読書について』(ちくま文庫)
私が知る範囲では、4だけが正しい。
September 27, 2025 at 10:08 AM
ChatGPT5にヴァージニア・ウルフの書評や評論を集めた本(日本語訳)を挙げてくださいと入力した結果。
1. 『ヴァージニア・ウルフ エッセイ集』全3巻(みすず書房)
2. 『自分ひとりの部屋』(青土社、岩波文庫など)
3. 『女性にとって職業としての文学』(岩波文庫)
4. 『モダン・フィクション』を収録した評論集 日本語では単独刊行ではなく、エッセイ集の中に収録されることが多い。
5. 『書くことについて』(白水Uブックス など)
6. 『読書について』(ちくま文庫)
私が知る範囲では、4だけが正しい。
1. 『ヴァージニア・ウルフ エッセイ集』全3巻(みすず書房)
2. 『自分ひとりの部屋』(青土社、岩波文庫など)
3. 『女性にとって職業としての文学』(岩波文庫)
4. 『モダン・フィクション』を収録した評論集 日本語では単独刊行ではなく、エッセイ集の中に収録されることが多い。
5. 『書くことについて』(白水Uブックス など)
6. 『読書について』(ちくま文庫)
私が知る範囲では、4だけが正しい。
「無言の帰宅」を国会図書館で全文検索してみたら、用例が
・ジャーナリスティックなもの(評論・手記を含む)
・詩歌
の2つに偏っていて、詩歌以外の文学にはめったに使われてない感じ。面白い。
・ジャーナリスティックなもの(評論・手記を含む)
・詩歌
の2つに偏っていて、詩歌以外の文学にはめったに使われてない感じ。面白い。


September 26, 2025 at 3:57 AM
「無言の帰宅」を国会図書館で全文検索してみたら、用例が
・ジャーナリスティックなもの(評論・手記を含む)
・詩歌
の2つに偏っていて、詩歌以外の文学にはめったに使われてない感じ。面白い。
・ジャーナリスティックなもの(評論・手記を含む)
・詩歌
の2つに偏っていて、詩歌以外の文学にはめったに使われてない感じ。面白い。
昨日の文学フリマでは、思っていたよりも多くのアダルト系作品があったけど、
よく見ると「評論」「歴史」「BL」「百合」などのジャンルがほとんどで、ガチで男女がまぐわうアダルト小説を扱っていたのは、近隣ではウチとお隣の「おきのはな」(X:@hanaokino)さん、の2サークルだけだった印象です。
お隣さんとは
「成人向がウチだけじゃなくて良かった」
「今日はお互い頑張りましょうね」
と、冒頭から仲良くなれて本当に楽しかったです。
とてもきれいな方で、ご自身の緊縛姿を表紙にして、自身の体験に取材したSM系小説を書かれています。
男女関係なく多くの方に売れていました。すごい。
よく見ると「評論」「歴史」「BL」「百合」などのジャンルがほとんどで、ガチで男女がまぐわうアダルト小説を扱っていたのは、近隣ではウチとお隣の「おきのはな」(X:@hanaokino)さん、の2サークルだけだった印象です。
お隣さんとは
「成人向がウチだけじゃなくて良かった」
「今日はお互い頑張りましょうね」
と、冒頭から仲良くなれて本当に楽しかったです。
とてもきれいな方で、ご自身の緊縛姿を表紙にして、自身の体験に取材したSM系小説を書かれています。
男女関係なく多くの方に売れていました。すごい。


September 15, 2025 at 5:36 AM
昨日の文学フリマでは、思っていたよりも多くのアダルト系作品があったけど、
よく見ると「評論」「歴史」「BL」「百合」などのジャンルがほとんどで、ガチで男女がまぐわうアダルト小説を扱っていたのは、近隣ではウチとお隣の「おきのはな」(X:@hanaokino)さん、の2サークルだけだった印象です。
お隣さんとは
「成人向がウチだけじゃなくて良かった」
「今日はお互い頑張りましょうね」
と、冒頭から仲良くなれて本当に楽しかったです。
とてもきれいな方で、ご自身の緊縛姿を表紙にして、自身の体験に取材したSM系小説を書かれています。
男女関係なく多くの方に売れていました。すごい。
よく見ると「評論」「歴史」「BL」「百合」などのジャンルがほとんどで、ガチで男女がまぐわうアダルト小説を扱っていたのは、近隣ではウチとお隣の「おきのはな」(X:@hanaokino)さん、の2サークルだけだった印象です。
お隣さんとは
「成人向がウチだけじゃなくて良かった」
「今日はお互い頑張りましょうね」
と、冒頭から仲良くなれて本当に楽しかったです。
とてもきれいな方で、ご自身の緊縛姿を表紙にして、自身の体験に取材したSM系小説を書かれています。
男女関係なく多くの方に売れていました。すごい。
春日武彦『自滅帳』(晶文社)を読了。
精神科医である著者が、「自滅」をテーマにした13篇の文学作品を取り上げ解説するという本です。文学的な価値があるのかどうかや、傑作かどうか、といった点は関係なく、飽くまで異様な行動や心理を描いた作品をセレクションしているところが特色です。
文学作品そのものの解説だけでなく、それに応じて連想された著者自身の体験や随想がまざってくるのも特徴で、評論というよりは、文学作品をきっかけにしたエッセイといった感触が強いですね。
取り上げられているのは、松本清張『断崖』、デルフィーヌ・ド・ヴィガン『子供が王様』、吉行淳之介『痴』、パトリシア・ハイスミス『手持ちの鳥』、
精神科医である著者が、「自滅」をテーマにした13篇の文学作品を取り上げ解説するという本です。文学的な価値があるのかどうかや、傑作かどうか、といった点は関係なく、飽くまで異様な行動や心理を描いた作品をセレクションしているところが特色です。
文学作品そのものの解説だけでなく、それに応じて連想された著者自身の体験や随想がまざってくるのも特徴で、評論というよりは、文学作品をきっかけにしたエッセイといった感触が強いですね。
取り上げられているのは、松本清張『断崖』、デルフィーヌ・ド・ヴィガン『子供が王様』、吉行淳之介『痴』、パトリシア・ハイスミス『手持ちの鳥』、

September 14, 2025 at 11:06 AM
春日武彦『自滅帳』(晶文社)を読了。
精神科医である著者が、「自滅」をテーマにした13篇の文学作品を取り上げ解説するという本です。文学的な価値があるのかどうかや、傑作かどうか、といった点は関係なく、飽くまで異様な行動や心理を描いた作品をセレクションしているところが特色です。
文学作品そのものの解説だけでなく、それに応じて連想された著者自身の体験や随想がまざってくるのも特徴で、評論というよりは、文学作品をきっかけにしたエッセイといった感触が強いですね。
取り上げられているのは、松本清張『断崖』、デルフィーヌ・ド・ヴィガン『子供が王様』、吉行淳之介『痴』、パトリシア・ハイスミス『手持ちの鳥』、
精神科医である著者が、「自滅」をテーマにした13篇の文学作品を取り上げ解説するという本です。文学的な価値があるのかどうかや、傑作かどうか、といった点は関係なく、飽くまで異様な行動や心理を描いた作品をセレクションしているところが特色です。
文学作品そのものの解説だけでなく、それに応じて連想された著者自身の体験や随想がまざってくるのも特徴で、評論というよりは、文学作品をきっかけにしたエッセイといった感触が強いですね。
取り上げられているのは、松本清張『断崖』、デルフィーヌ・ド・ヴィガン『子供が王様』、吉行淳之介『痴』、パトリシア・ハイスミス『手持ちの鳥』、
「本当に不思議だ。こんな気持ちは今まで一度も感じたことがない。自分の人生にどれほどたくさんの悲しいことがあったのか、どれほどうれしいことや、感謝すべきことがあったのか、苦しい時間と平和な時間があったのか、十分に知っているつもりだったけど……」ノーベル文学賞作家ハン・ガンが描く大人のための童話『涙の箱』(評論社)入荷しました。絵はjunaidaさん! tinyurl.com/5z4uf7yz

September 13, 2025 at 11:38 PM
「本当に不思議だ。こんな気持ちは今まで一度も感じたことがない。自分の人生にどれほどたくさんの悲しいことがあったのか、どれほどうれしいことや、感謝すべきことがあったのか、苦しい時間と平和な時間があったのか、十分に知っているつもりだったけど……」ノーベル文学賞作家ハン・ガンが描く大人のための童話『涙の箱』(評論社)入荷しました。絵はjunaidaさん! tinyurl.com/5z4uf7yz
歌人の平岡直子さんがはるか昔「平岡姓でいちばん出世した文学者は三島由紀夫だから」と言っていて、三島由紀夫が同姓なのうらやましいな〜と思った記憶があるのだけど、吉田姓だと吉田健一、次いで吉田秀和というシブい評論家になりそう 今だと吉田修一もいるか 兼好法師はひところ吉田神社と関係あるから吉田姓で呼ばれていたが、なんかいろいろ研究の成果を勘案すると卜部兼好(うらべのかねよし)なので、吉田という呼び名は正確でないらしい
September 13, 2025 at 7:41 AM
歌人の平岡直子さんがはるか昔「平岡姓でいちばん出世した文学者は三島由紀夫だから」と言っていて、三島由紀夫が同姓なのうらやましいな〜と思った記憶があるのだけど、吉田姓だと吉田健一、次いで吉田秀和というシブい評論家になりそう 今だと吉田修一もいるか 兼好法師はひところ吉田神社と関係あるから吉田姓で呼ばれていたが、なんかいろいろ研究の成果を勘案すると卜部兼好(うらべのかねよし)なので、吉田という呼び名は正確でないらしい
9月13日はロアルド・ダールの誕生日(1916)。執筆活動は幅広い。児童文学では度々映像化される『チョコレート工場の秘密』(評論社)。怪奇集は『キス・キス』、元パイロットの履歴を生かし、飛行士たちの話を集めた『飛行士たちの話』(以上、早川書房)等がある。

September 12, 2025 at 11:05 PM
9月13日はロアルド・ダールの誕生日(1916)。執筆活動は幅広い。児童文学では度々映像化される『チョコレート工場の秘密』(評論社)。怪奇集は『キス・キス』、元パイロットの履歴を生かし、飛行士たちの話を集めた『飛行士たちの話』(以上、早川書房)等がある。
【新刊】 『涙の箱』 (ハン・ガン著,きむふな訳/評論社)。ノーベル文学賞作家ハン・ガンがえがく、大人のための童話。この世で最も美しく、すべての人のこころを濡らすという「純粋な涙」を探して――。童話と銘打ちながらも、深い絶望や痛みを描き、そこを通過して見える光を描くハン・ガンの作品世界を色濃く感じられる。本国韓国では2008年刊行。日本語版の装画はハン・ガン自身、長年ファンだったというjunaida。
porvenirbookstore.stores.jp/items/68a840...
porvenirbookstore.stores.jp/items/68a840...

涙の箱
ハン・ガン (著),きむ ふな (訳)
ISBN 978-4-566-02489-2
四六判 88ページ
発行 評論社 2025年8月
ノーベル文学賞作家ハン・ガンがえがく、大人のための童話。この世で最も美しく、すべての人のこころを濡らすという「純粋な涙」を探して。
昔、それほど昔ではない昔、ある村にひとりの子どもが住んでいた。その子には、ほかの子どもとは違う、特別なところがあった。みんなが...
porvenirbookstore.stores.jp
September 12, 2025 at 6:12 AM
【新刊】 『涙の箱』 (ハン・ガン著,きむふな訳/評論社)。ノーベル文学賞作家ハン・ガンがえがく、大人のための童話。この世で最も美しく、すべての人のこころを濡らすという「純粋な涙」を探して――。童話と銘打ちながらも、深い絶望や痛みを描き、そこを通過して見える光を描くハン・ガンの作品世界を色濃く感じられる。本国韓国では2008年刊行。日本語版の装画はハン・ガン自身、長年ファンだったというjunaida。
porvenirbookstore.stores.jp/items/68a840...
porvenirbookstore.stores.jp/items/68a840...
悩みに悩み抜いた末、文学より哲学を選ぶことにした。
阪大や東大には師事したい文学の先生がいるのだがしかし、京大にはいない。
それでも私は京大を選ぶことにした。
何故なら、まず京都学派で思想的土台を作ってから文学批評に入りたいと考えたからだ。
共テが評論から小説の順番であるのと同じである。
第一志望は、京都大学文学部哲学科。それを再確認した。
阪大や東大には師事したい文学の先生がいるのだがしかし、京大にはいない。
それでも私は京大を選ぶことにした。
何故なら、まず京都学派で思想的土台を作ってから文学批評に入りたいと考えたからだ。
共テが評論から小説の順番であるのと同じである。
第一志望は、京都大学文学部哲学科。それを再確認した。
September 11, 2025 at 10:19 PM
悩みに悩み抜いた末、文学より哲学を選ぶことにした。
阪大や東大には師事したい文学の先生がいるのだがしかし、京大にはいない。
それでも私は京大を選ぶことにした。
何故なら、まず京都学派で思想的土台を作ってから文学批評に入りたいと考えたからだ。
共テが評論から小説の順番であるのと同じである。
第一志望は、京都大学文学部哲学科。それを再確認した。
阪大や東大には師事したい文学の先生がいるのだがしかし、京大にはいない。
それでも私は京大を選ぶことにした。
何故なら、まず京都学派で思想的土台を作ってから文学批評に入りたいと考えたからだ。
共テが評論から小説の順番であるのと同じである。
第一志望は、京都大学文学部哲学科。それを再確認した。
【告知】9/14文学フリマ大阪サークル「パナトリエ」で参加いたします!(す05.06)映画評論漫画、リアル叔父の版画作品復刻版とグッズ。おやじメイドも夏コミ新刊持っていきますので良かったら見に来てね!
翌週9/21はBIGLOVEFESTA2(歌舞伎町)に参加!よろしくお願いいたします。 #創作漫画 #OC #文学フリマ大阪 #BIGLOVEFESTA
翌週9/21はBIGLOVEFESTA2(歌舞伎町)に参加!よろしくお願いいたします。 #創作漫画 #OC #文学フリマ大阪 #BIGLOVEFESTA

September 11, 2025 at 4:09 PM
【告知】9/14文学フリマ大阪サークル「パナトリエ」で参加いたします!(す05.06)映画評論漫画、リアル叔父の版画作品復刻版とグッズ。おやじメイドも夏コミ新刊持っていきますので良かったら見に来てね!
翌週9/21はBIGLOVEFESTA2(歌舞伎町)に参加!よろしくお願いいたします。 #創作漫画 #OC #文学フリマ大阪 #BIGLOVEFESTA
翌週9/21はBIGLOVEFESTA2(歌舞伎町)に参加!よろしくお願いいたします。 #創作漫画 #OC #文学フリマ大阪 #BIGLOVEFESTA
坪内祐三「『別れる理由』が気になって」
伝説的な小説について、10年以上にわたる連載の雑誌と単行本との文章などの比較や、時代背景(の変遷とそれが小説に与えた影響)についての精緻な記述は読み応えがある。
そして物語の後半、柄谷行人や大庭みな子がといった実在の文学者が出てきたり、登場人物が様々に変身したりといった破天荒な(大まかな物語は知っていたが、ここまでとはと驚くような)展開についての考察も面白い。
この評論を読まずにいきなり「別れる理由」を読み始めていたら、読了できなかったのでは思うくらいで、さまざま興味をかき立てられる。
伝説的な小説について、10年以上にわたる連載の雑誌と単行本との文章などの比較や、時代背景(の変遷とそれが小説に与えた影響)についての精緻な記述は読み応えがある。
そして物語の後半、柄谷行人や大庭みな子がといった実在の文学者が出てきたり、登場人物が様々に変身したりといった破天荒な(大まかな物語は知っていたが、ここまでとはと驚くような)展開についての考察も面白い。
この評論を読まずにいきなり「別れる理由」を読み始めていたら、読了できなかったのでは思うくらいで、さまざま興味をかき立てられる。

September 3, 2024 at 1:15 PM
坪内祐三「『別れる理由』が気になって」
伝説的な小説について、10年以上にわたる連載の雑誌と単行本との文章などの比較や、時代背景(の変遷とそれが小説に与えた影響)についての精緻な記述は読み応えがある。
そして物語の後半、柄谷行人や大庭みな子がといった実在の文学者が出てきたり、登場人物が様々に変身したりといった破天荒な(大まかな物語は知っていたが、ここまでとはと驚くような)展開についての考察も面白い。
この評論を読まずにいきなり「別れる理由」を読み始めていたら、読了できなかったのでは思うくらいで、さまざま興味をかき立てられる。
伝説的な小説について、10年以上にわたる連載の雑誌と単行本との文章などの比較や、時代背景(の変遷とそれが小説に与えた影響)についての精緻な記述は読み応えがある。
そして物語の後半、柄谷行人や大庭みな子がといった実在の文学者が出てきたり、登場人物が様々に変身したりといった破天荒な(大まかな物語は知っていたが、ここまでとはと驚くような)展開についての考察も面白い。
この評論を読まずにいきなり「別れる理由」を読み始めていたら、読了できなかったのでは思うくらいで、さまざま興味をかき立てられる。

